

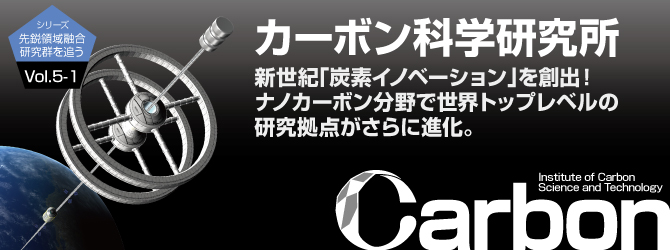
昨年4月からスタートした先鋭領域融合研究群5つの研究所の特集も、いよいよ今回最後のカーボン科学研究所の紹介となった。部門がフレキシブルに連携する組織的"進化"、以前広報誌で特集した「エキゾチック・ナノカーボン(ENCs)」を発展させる研究的"深化"、さらに産学連携を加速するための施設的"発展"が研究所の特徴になる。今回、研究所長・部門長・遠藤特別研究室長にお話を聞いた。
「もともとカーボン科学研究所は、CNT(カーボンナノチューブ)の発見・発明者で世界的権威、遠藤守信特別特任教授が、10年ほど前に学部や学科の枠を超えた研究グループを作るために始めたものです。前身としては、優れた研究者を国内外から招へいし共同研究する事業、ENCs(エキゾチックナノカーボン)ドリームチームがありました。ただ、外部企業などとの共同研究といった展開には、その受け皿となる研究部門が必要でした。そのため、大学組織内の一部門としてリニューアルされ、このたびの新生・カーボン科学研究所が誕生したのです」
1964年生まれの50歳。カーボン科学研究所長に就任した橋本佳男教授は、新しい組織についてこう語る。カーボン科学研究所は、遠藤特別研究室、基礎科学研究部門、応用材料工学研究部門、共用・プラット事業・ナノテクプラットフォーム研究部門、運営・マネージメント室の4部門1室で構成されている。研究と産学連携のグローバリゼーションを見据えた新しいタイプの組織だ。
遠藤特別研究室は、海外の研究者も参画する研究部門で、CNTの新規物質の創成や応用を目的とする。基礎科学研究部門と応用材料工学研究部門の両部門でも、革新的なCNTの創出や物性の確認、それらを応用した構造材や各種デバイスの開発を行う。また、共用・プラット事業・ナノテクプラットフォーム研究部門では、外部企業などが製作したナノカーボンの物性試験や構造解析の受託、あるいは各種測定機器の貸出しの他に、外部企業や研究者との共同研究なども積極的に支援・実施する。

林 卓哉 (はやし たくや)
信州大学学術研究院 教授(工学系)
先鋭領域融合研究群 カーボン科学研究所
基礎科学研究部門長
東京大学卒業、同大学院(工学系研究科)修了、工学博士
1999年より信州大学工学部助手、2013年同教授、2014年より現職。
林卓哉部門長が率いる基礎科学部門は、新規ナノカーボンの合成と物性評価、理論的解析などを行う。基礎科学という名称はついているが、物理、化学の研究者が単に理論に特化するというよりは、新規創成を目指したいと考えている。
CNTは、炭素の同素体の一つ。炭素六角網平面シートを丸めた筒状構造なので、軽くて強いだけでなく、ナノ構造の一部を他の元素に置き換えることで、従来は考えられなかった広範な機能が期待されている。鉄の20倍の強度や、低い摩擦係数、高い導電性。ナノ構造を変えれば、強度も化学的性質も変えられるので、応用範囲は極めて広い。
この部門では、電子顕微鏡内でCNT自体を動かして、新しい性質、特性を見出し、電気的な特性や、従来のカタチと違うCNT、結晶性の差、異種元素の付着や、結晶の大きさの違いなど、発見した結果を物性制御や構造制御に役立てていく。新しいものを発見し、フィードバックして理想のカタチに近づけていくことが目標だ。
例えば農林水産省で採択された、もみ殻、稲わらからナノカーボンをつくり出すプロジェクト。細いCNTの周囲にグラフェンが付いた結晶を生成する。環境に配慮し、農業廃棄物から価値あるものをつくろうという発想だ。

新井 進 (あらい すすむ)
信州大学学術研究院 教授(工学系)
先鋭領域融合研究群 カーボン科学研究所
応用材料工学研究部門長
信州大学理学部卒業、工学博士
長野県精密工業試験場研究員などを経て、1999年より信州大学工学部助手、2004年助教授、2011年同教授、2014年より現職。
部門長の新井進教授は、もともとめっきの専門家だ。カーボンは素材としての斬新さが企業にとって魅力なため、連携の範囲は相当広く、100社以上との連携が進行している。
CNTは、水と油と同じ位、水に分散しにくい。それをめっき液の中に均一に分散させる技術を開発したため、金属とCNTの複合膜ができるようになった。めっきできる金属なら、ほとんどCNTが複合できる。特性として、CNTがもともと持っている小さな摩擦係数がめっき膜に複合され、めっき膜の摩擦が小さくなる。摩耗しなくなる。ネジとネジ、車のピストンなど、よりスムースに動くようになる。
また触媒としての性能も画期的だ。無電解めっき法と呼ばれるめっき法を用いれば、VGCF(遠藤ファイバー)を金属コーティングしたり、VGCF表面に金属ナノ粒子を形成することが可能となり、これを触媒として用いることができる。例えばCNTに金のナノ粒子をつけると非常に優れた触媒になる。
連携事例としては、ブドウ糖を分解する素晴らしい触媒になり、グルコースをグルコン酸に分解できる。血糖値を下げるような働きがあり、体温と同じ40度で分解できる。
またCNTは、鉄鋼の20倍の強度を持った繊維状の材料であることも応用範囲を広くしている。次世代リチウムイオン電池の材料として、ナノチューブめっきで現行の材料を凌駕する特性を発現できる。
この他にも、テレビの次世代ディスプレイ。フィールドエミッションディスプレイでは、スマートフォン並みの輝度、1000時間くらいの耐久性を持たせることができる。また、燃料電池の触媒としては、CNTの上に白金をめっきする。人工関節への利用。CNTは、体の中に埋め込む際に、悪さをしないきれいな物質、しかも劣化しない。潤滑作用もある。自己潤滑できる。耐摩耗性能があり、ジョイントのすべりが良くなる。石油の掘削に使うゴムの中にナノチューブを混ぜれば、気圧、温度の高い状態に耐える。まだまだ、応用の可能性は多様にある。

新井部門長に持参いただいた、いろいろな種類の「複合めっき」サンプル。カーボン・ナノチューブ(CNT)を多彩な材料でめっきコーティングすることで予想もしなかった新しい特性・機能が生まれることも。
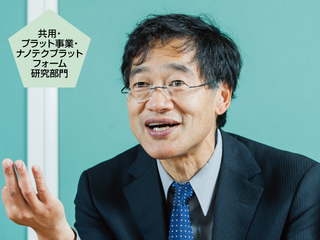
橋本 佳男 (はしもと よしお)
信州大学学術研究院 教授(工学系)
先鋭領域融合研究群 カーボン科学研究所長
共用・プラット事業・ナノテクプラットフォーム研究部門長
東京大学卒業、同大学院(工学系研究科)修了、工学博士
1994年より信州大学工学部助手、1995年同助教授、2007年同教授、2014年より現職。
所長の橋本教授が部門長を兼任する、共用・プラット事業・ナノテクプラットフォーム研究部門は、文部科学省との連携事業として、二つの事業を行う。
共用・プラット事業は、産業界に対し、カーボン科学研究所に設置されている、ナノカーボン・デバイス試作・評価装置群を貸与し、ナノカーボン産業拡大のためのカーボンバレー構築支援事業を行う。
ナノテクプラットフォーム研究部門は、対象を限定せず、幅広い研究連携を行うことが目的。新しい材料をつくる装置を貸与し、研究連携をマネージメントする。
この2事業は、ナノカーボン産業拡大のためのカーボンバレー構築支援事業として位置づけ、世界トップレベルの“ナノカーボンファウンダリー”の構築を目指していく。
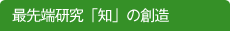
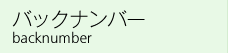
 X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02
X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02環境・エネルギー材料科学研究所
白熱議論で踏み出した新たな一歩
 信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」
信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」ナノセルロース、ナノカーボンの“ナノ・ナノ複合化”で、革新的な素材を創り上げる
 シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所
シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所「炭素の世紀」の開花へ 遠藤特別特任教授が熱く語るカーボンイノベーション
 シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所
シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所新世紀「炭素イノベーション」を創出!ナノカーボン分野で世界トップレベルの研究拠点がさらに進化。
 シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所
シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所5つの研究部門とミッション