

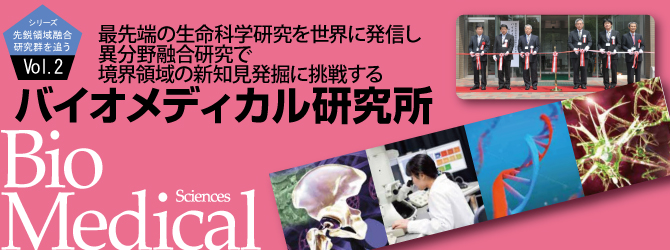
信州大学は、世界レベルの特色ある研究を推進するために、今春、新たに「先鋭領域融合研究群」を設置した。この新組織は、カーボン科学、環境・エネルギー材料科学、国際ファイバー工学、山岳科学、バイオメディカルの5つの研究所をコアにして構成されている。
前回より、この「先鋭領域融合研究群」の全体像を浮き彫りにする特集を連載している。シリーズ2回目は、バイオメディカル研究所に焦点を当てた。医学―農学の架け橋の上に独自の生命科学研究を創造発展させ、同時に、分野横断的融合研究で境界領域に潜む新知見の発掘を目指している。

平成26年5月25日、先鋭領域融合研究群バイオメディカル研究所の設立記念式典が信州大学松本キャンパスで盛大に挙行された。
テープカットには山沢清人学長、福嶋義光医学部長(※当時)、中村宗一郎農学部長、齋藤直人研究所長らと共に、医学部の地元から平尾勇松本市健康産業・企業立地担当部長、農学部の地元から酒井茂伊那市副市長が参列。地域の熱い期待が浮き彫りになった。
記念式典では齋藤研究所長をはじめ4人の部門長が、部門の研究理念やミッションなどを紹介。板倉康洋文部科学省研究振興局振興企画課長ほか、多くの来賓の方々から祝辞を賜った。続いて行われた記念講演会では、「ゲノム解析と医療:1000ドルゲノム時代を迎えて」の演題で、横浜市立大学大学院医学研究科の松本直通教授が講演を行い、県内外から集まった産学官の関係者が熱心に聴講した。

信州大学学術研究院 教授(保健学系)
先鋭領域融合研究群 バイオメディカル研究所長
バイオテクノロジー・生体医工学部門長
齋藤 直人 博士(医学)
1988年信州大学医学部卒業。信大医学部附属病院医員。1996年信大医学部助手。1999年信大医学部講師。2004年信大医学部教授。2014年より現職
「信州大学ではこれまでも医学部と農学部の英知を結集して、独自の生命科学の研究を進めてきました。その成果を継承発展させながら、同時に、分野横断的な研究の融合により境界領域に潜む新知見を多数発掘し、新たな挑戦を牽引できる若手研究者を輩出したいと思っています」。
バイオメディカル研究所長に就任した齋藤直人教授は現在の抱負をこう話す。
1959年生まれの55歳。信州大学医学部で学んだ後、整形外科・リハビリテーション科の医師として活躍する一方、生体材料や再生医療などの研究を進めてきた。
2004年からは、信州大学が世界に誇るナノカーボンを含んだ複合材料を、安全性を担保しながら世界で初めて、人工関節として生体材料の臨床に用いることをめざし、信州大学と長野県、長野県経営者協会が共同で開設した信州メディカルシーズ育成拠点をベースに実践的研究を進め、医療界から高い期待が寄せられている。
「学問としての生命科学の基本を守りながら、他領域の研究との境界にある新しい宝を見つけ出し、世界的水準の研究に発展させていく。そういうワクワクする仕事を推進したいですね」。─齋藤所長の視線は常に世界に向けられている。
バイオメディカル研究所は、先端疾患予防学、神経難病学、バイオテクノロジー・生体医工学、代謝ゲノミクスの4つの部門から構成される(9-10頁参照)。それぞれが高度な専門性を持ち、独自の粘り強い研究が求められるが、それぞれの研究部門にのみ注力するのではなく、プロジェクト主導の流動的な組織を構築することにより、研究所内から分野横断的融合を創出することを目指すという。
研究所としての目標は、冒頭の齋藤所長の言葉にもあるように、第一に信州大学独自の生命科学研究の推進。第二に、先鋭領域融合研究群の他の研究所や学
部間の連携、他大学との連携、産学官地域の連携、さらには国際的な連携を通じた、特に境界領域に潜む新知見の発掘。
そして第三に若手研究者(ライジングスター)を育成し、世界と戦えるスーパースターを輩出することだ。

その中でも、齋藤所長が強調することは、同研究所と、先鋭領域融合研究群の他の4つの研究所(カーボン科学、環境・エネルギー材料科学、国際ファイバー工学、山岳科学)との連携・融合。
自身が、ナノカーボンを生体材料に応用する研究を進めていることもあり、生命科学と材料工学、ファイバー工学、高地自然科学などとの境界領域に様々な研究テーマが潜んでおり、その発掘と研究の進化が、信州大学の特色ある研究を〝世界オンリーワン〟に押し上げていく大きな糸口になると確信している。
「そもそも、先鋭領域融合研究群は、そういう目的を持って新しく設置されました。地方の国立大学が、総合大学という強みを活かして独自の発展を進めるには、それぞれの領域の核になる研究を、分野を超えて融合させ、新たな〝知〟を創造しなければなりません。バイオメディカル研究所は、この取り組みを生命科学の領域から牽引したいと思います」と力をこめる。
先鋭領域融合研究群と各研究所の発展の展望については、「若手研究者の育成」も軸にして構想されている。
2014年の現時点で、信大の生命科学研究を担う医学系・農学系の分野に、〝宝〟ともいうべき最先端研究がいくつも展開されている。同研究所では、「ネイチャー」や「サイエンス」クラスの世界的研究誌への論文掲載や、文部科学省などの競争的資金の獲得状況などの実績を評価し、研究テーマの選択と集中を進め、世界と戦える重点研究が研究所全体を牽引できるようにマネジメントする。
特に、次世代を切り拓く可能性のある研究を重視し、それを進める有望な若手研究者を、研究環境・待遇などを含めてバックアップする。(※「ライジングスター(RS)制度」参照)同時に異分野融合による基盤研究を充実させながら、5年後の2019年には、世界と戦える最先端研究を推進する理想的な体制の構築を目指す。
バイオメディカル─この世界激戦区の研究領域でも、信大は他に類例を見ない、新たな一歩を踏み出そうとしている。
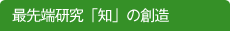
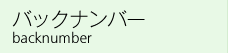
 X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02
X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02環境・エネルギー材料科学研究所
白熱議論で踏み出した新たな一歩
 信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」
信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」ナノセルロース、ナノカーボンの“ナノ・ナノ複合化”で、革新的な素材を創り上げる
 シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所
シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所「炭素の世紀」の開花へ 遠藤特別特任教授が熱く語るカーボンイノベーション
 シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所
シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所新世紀「炭素イノベーション」を創出!ナノカーボン分野で世界トップレベルの研究拠点がさらに進化。
 シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所
シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所5つの研究部門とミッション