


山沢学長の強力なリーダーシップのもと、いよいよスタートした大胆な信大改革。「学術研究院」の設置とならんで、その柱となるのが、信大の特色ある研究領域に集中的に資源を配分するための「先鋭領域融合研究群」の設置だ。
当面はまず、カーボン科学、環境・エネルギー材料、ファイバー工学、山岳科学、バイオメディカルの5つの領域に資源を集中し、学内の若手研究者の育成と、外部の卓越研究者の招聘によって大学総体の研究力の飛躍的アップを図る。
この組織を先導役として抜本的な教育改革・組織改革を進め、持続可能な社会の構築にグローバルな力を発揮する人材、日本の産業界を牽引し成長の原動力となる人材を育成することを目指したものだ。
「信大NOW」では本号より5回にわたり、「先鋭領域研究群」の各研究所の新たなチャレンジに焦点を当てた特集を連載する。そのオープニングとして、初代群長に就任した濱田州博(くにひろ)副学長・繊維学部長に、今後の展開方向、中長期ビジョンを含めて、インタビューした。

信州大学 副学長・繊維学部長・教授(繊維学系)
濱田 州博 群長
(繊維学部 化学・材料系応用化学課程)
1982年東京工業大学工学部卒業。1987年同大学院博士課程修了。1987年通商産業省工業技術院繊維高分子材料研究所研究員。1988年信州大学繊維学部助手。1996年同助教授。2002年より同教授。2010年より繊維学部長。2012年より副学長。2014年より同職。著書に「繊維の高次機能加工」(シーエムシー出版)、「はじめて学ぶ繊維」(日刊工業新聞社)、「繊維の百科事典」(丸善出版)など
信大では様々な領域の研究が行われていますが、その中から特に現在、先導性があり、特色あるものとして挙げられる5つの研究領域―カーボン科学、環境・エネルギー材料、ファイバー工学、山岳科学、バイオメディカル―を選び、若手を中心に研究所を設置して、資源を集中して研究を進めることにしました。この先鋭領域の選択は固定的なものではなく、相互に重なり合い、融合的に研究を進めた方が効果的なので、5つの研究所を有機的につなぎ、創造的に連携・発展させていくために、「群」としてまとめたものです。
これまでも研究所はありましたし、教員は、教育者であると同時に、研究者として、それぞれの研究を進めてきました。しかし、それぞれの研究はそれぞれの組織に任されてきた傾向が強く、大学として、また、直接研究を担う同一領域の研究者のグループとして、総合的な目的のもとに、研究の領域と役割を分担し、研究全体をマネジメントしていくといった戦略的な機能はたいへん弱かったと思います。新しい体制では、その点を克服するために、特色ある研究領域を選択し、そこに資源を集中しながら、各領域の内部で、またそれを包括、横断する形で、信大の研究が世界をリードできるものになるよう、群長が中心になり各研究所が相互に協力する体制を整え、研究をマネジメントすることを目指しています。
確かに、5つの研究所で総勢40人ほどになる専任教員は、比較的若い人が中心です。今後の信大を担っていく世代の人に、先鋭領域での研究に専念して欲しいという思いがあります。また、担当する学術分野や領域を超え、一つの共同の事業として研究を進めていくという新しい仕組みを作るためにも、若い人が中心になっていった方が良いという判断もあります。
これまでは学部単位で教育組織と教員組織が一体だったわけですが、今度の改革では、戦略的な人事、全学的研究マネジメントを可能にするために、教員組織として学術研究院を設置しています。これにより、先鋭領域融合研究群の専任教員には研究エフォート8割の環境を提供すると同時に、学部横断的な教育を実現しようとしているわけです。ですから、研究所専任は、研究や大学院での指導に軸足を置いてもらうことになりますが、皆さん、学部生にも人気のある教員ですから、一年次生の共通教育でオムニバス形式の講義を受け持ってもらうことになっています。
学内の若手研究者の相乗的な成長を進めるためにも、学外から優れた研究者を招いて研究水準の引き上げを図ることが重要です。国内外の教育研究機関はもちろんですが、産業界で活躍する実践的研究者などもどしどし招いて、日本の産業界を牽引する研究を進める必要があるし、それを通じて、社会の発展の原動力となれるようなグローバルな人材を育成することが重要だと思います。
5つの先鋭領域のすべてです。カーボン科学、環境・エネルギー材料、ファイバー工学は現状で世界的に注目される信大の看板研究だと言えますし、医農工にまたがるバイオメディカルについては、医学系の先生方が積極的に関わってくださろうとしています。また、理学から農学・林学、社会学に裾野を広げる山岳科学も長野県に相応しい研究領域だと思います。
記者会見でも同様の質問が出て、お答えしましたが、5つの先鋭領域は、どれも、人文科学や社会科学の知見・視点からのアプローチも必要不可欠な研究領域だと思います。5つの先鋭領域は相互に融合して研究するべきだし、それぞれの領域でも、文理融合の視点からのアプローチが必要です。各領域の研究は、1年ごと、また3年、5年の区切りをつけて研究成果を検証して行く予定ですが、その時点で、人文系の視点をもっとクローズアップして領域として設定するべきだということになれば、先鋭領域が増えていくことになります。こういう発展を望んでいます。
そうですね。環境・エネルギー材料科学研究所の先生たちが盛んに「クロス・ブリード」という研究手法を提唱しています。できるだけ、いろいろな人が融合して研究に関わるということを表す言葉ですが、これは、先鋭領域融合研究群の基本的考え方・手法でもあるわけです。現代世界が直面している問題は複合的で、文系とか理工系とかいうような従来の学問の領域区分を超える多角的で融合的なアプローチが求められています。旧帝大系ではなく、地方の国立大学法人として、こうした点を明確に示しているのが信州大学の挑戦の大きな特徴であると言っても良いでしょう。
なにより研究を進め、世界に認められる成果を生み出すことが第一の課題です。しかし、一朝一夕に成果が出るものではありませんから、年度ごと、また3年、5年のごとのスパンで、群としての研究も、各研究所の研究も検証して、創造的発展を目指していくつもりです。先にも述べたように、先鋭領域融合研究群の設置は、戦略的な人事マネジメントを実現する教員組織である学術研究院の設置と、セットになったものです。研究群の研究者である教員に、研究重視の環境を提供し、そこでしっかりとした研究成果が出てくれば、学部や大学院での教育の充実、また教員組織のさらなる発展につながっていきます。そのような形で、先鋭領域研究群での研究が、大学改革の先導役になることを願っています。
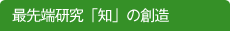
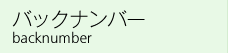
 X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02
X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02環境・エネルギー材料科学研究所
白熱議論で踏み出した新たな一歩
 信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」
信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」ナノセルロース、ナノカーボンの“ナノ・ナノ複合化”で、革新的な素材を創り上げる
 シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所
シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所「炭素の世紀」の開花へ 遠藤特別特任教授が熱く語るカーボンイノベーション
 シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所
シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所新世紀「炭素イノベーション」を創出!ナノカーボン分野で世界トップレベルの研究拠点がさらに進化。
 シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所
シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所5つの研究部門とミッション