


環境・エネルギー材料科学研究所のキックオフシンポジウムでは、手嶋所長の設立趣旨と概要説明に続いて、6つの研究部門について部門長から紹介があった。

手嶋 勝弥 (てしま かつや)
学術研究院 教授(工学系)・学長補佐
先鋭領域融合研究群
環境・エネルギー材料科学研究所長・蓄電池部門長 博士(工学)
名古屋市生まれ。2003年名古屋大学大学院工学研究科博士課程後期課程修了。2005年信州大学工学部助手、2010年同准教授。2011年同教授。日本フラックス成長研究会副会長。2014年3月より現職。
部門紹介の先頭に立ったのは蓄電池部門。手嶋勝弥所長が部門長を兼任する。
蓄電池は、自動車産業を中心に日本経済界の熱い視線が集まる研究分野。経済産業省・資源エネルギー庁のCool Earth―エネルギー革新技術計画・運輸部門でも、2030年以降に電気自動車(EV)およびプラグインハイブリッド自動車(PHEV)の本格普及を掲げおり、その技術的課題の一つが、圧倒的に高性能な次世代革新蓄電池の開発なのである。先進的な自動車電動化のコア技術であり、信州大学でも重点研究領域に定めている。
「当部門では、次世代蓄電池開発の根幹となる基礎科学の体系化と新材料開発に取り組み、信大が切り拓くEVとスマートシティの未来を追い、その普及の一翼を担います」。手嶋教授は力強く語った。
具体的な一例として、「フラックス法」という信大が有する環境調和型結晶育成技術を基盤にした高品位結晶デザイン電池の5年以内の社会実装、さらに、様々な独自性の高い先端技術などの複合による一層高性能な全結晶型電池の開発、また、より大きな電気エネルギーを蓄えることのできる次々世代電池の創出などを目指すという。

杉本 渉 (すぎもと わたる)
学術研究院 教授(繊維学系)
先鋭領域融合研究群
環境・エネルギー材料科学研究所
燃料電池部門長・課題探索・横断研究部門長 博士(工学)
東京都出身。早稲田大学理工学部卒、早稲田大学大学院理工学研究科博士課程修了。1995年株式会社東芝1997年日本学術振興会特別研究員1999年信州大学繊維学部助手、2007年同准教授、2013年同教授、2014年4月より現職。趣味は「暴飲暴食」。
燃料電池部門の説明は杉本渉部門長が行った。水素と酸素を化学的に反応させてエネルギーを取り出す燃料電池は、燃料の製造・貯蔵、ガス・液体・イオン・電子の輸送、触媒反応など多くの科学的現象が関与している。
「幅広い技術の融合が必要な領域であり、だからこそ、多種多様な学問領域や分野にまたがった先鋭の研究者が力を合わせる必要がある。ハードルは高いが、実現できれば、高効率でクリーンなエネルギーを手に入れることができ、裾野の広い新規産業の創出につながる」と杉本部門長は訴えた。
さらに先を見越しては、「新しい機構による次々世代の発電デバイスを生み出すために、これまでの延長線上にはない着想が必用であり、従来の課題解決型の共同研究開発を超えた取組み、すなわち、ブレーンストーミング・アイデア集会などを通したゲーム・クリエイティング・コンセプトの創始が必用」と力説した。

森 正悟 (もり しょうご)
学術研究院 准教授(繊維学系)
先鋭領域融合研究群
環境・エネルギー材料科学研究所 太陽電池部門長 博士(工学)
愛知県出身。1998年トレド大学大学院(アメリカ)物理専攻博士前期課程修了。1999年ノキア・ジャパン(株)。2004年大阪大学論文博士。2005年信州大学研究員、2006年同助手、2007年同助教、2009年同准教授。2014年4月より現職。
燃料電池部門の説明は杉本渉部門長が行った。水素と酸素を化学的に反応させてエネルギーを取り出す燃料電池は、燃料の製造・貯蔵、ガス・液体・イオン・電子の輸送、触媒反応など多くの科学的現象が関与している。
「幅広い技術の融合が必要な領域であり、だからこそ、多種多様な学問領域や分野にまたがった先鋭の研究者が力を合わせる必要がある。ハードルは高いが、実現できれば、高効率でクリーンなエネルギーを手に入れることができ、裾野の広い新規産業の創出につながる」と杉本部門長は訴えた。
さらに先を見越しては、「新しい機構による次々世代の発電デバイスを生み出すために、これまでの延長線上にはない着想が必用であり、従来の課題解決型の共同研究開発を超えた取組み、すなわち、ブレーンストーミング・アイデア集会などを通したゲーム・クリエイティング・コンセプトの創始が必用」と力説した。

飯山 拓 (いいやま たく)
学術研究院 准教授(理学系)
先鋭領域融合研究群
環境・エネルギー材料科学研究所
革新創製・高度解析部門長 博士(理学)
福島県出身。1998年千葉大学大学院自然科学研究科博士課程修了。1999年信州大学理学部助手、2008年同准教授。日本化学会コロイドおよび表面化学部会役員会幹事、日本吸着学会評議員。2014年4月より現職。
革新創製・高度解析部門については、飯山拓部門長から、「環境・エネルギー材料科学研究所では、材料開発、新規測定の方法や結果を軸にしながらクロスブリードを進める必要がある。また有害物質除去、温室効果ガス抑制、物質貯蔵、物質分離のための新しい材料や方法論を提供するのがこの部門の役割だ」という説明があった。
例えば、様々な条件において、材料の界面付近で生じる分子の動き・現象を、特殊なセンサーやコンピューター解析により視覚的に掌握できるようにする(可視化・「見える化」)ことは、蓄電池や太陽電池の性能の向上や、新たな方法論の提案につながることであり、同部門の担当領域となる。また、有用な物質の回収と有用利用の方法の創出、有害物質(温室効果ガスを含む)の低減のための材料や方法論の提供、環境センサーや吸着スイッチング・低エネルギー消費型の物質分離法などの具体的提案なども担当する。

宮丸 文章 (みやまる ふみあき)
学術研究院 准教授 (理学系)
先鋭領域融合研究群
環境・エネルギー材料科学研究所・光デバイス部門長 博士(工学)
2004年大阪大学大学院工学研究科応用物理学専攻博士後期課程修了。2006年より,信州大学理学部物理科学科に勤務し,現在に至る。現在の主な研究内容は,固体や人工構造物におけるテラヘルツ波応答特性に関する物性とその制御。2014年4月より現職。
光デバイス部門については、宮丸文章部門長が「可視光線に限らず、電磁波スペクトルの広い領域にわたって、材料の電磁気的な応答を調べ、それらの特性をデバイス(光学素子)への応用につなげていきたい」と、同部門の基本的考え方を紹介した。
これまでにない新たな手法により作製された材料について、マイクロ波からテラヘルツ波、赤外光、可視光、さらには紫外光まで幅広い周波数領域で電磁気的な応答を測定することにより、新たな物性を見出し、それらをデバイス開発に役立てていくことを目指す。例えば、今日では無くてはならないものになっている半導体レーザーは、半導体分野の研究と、レーザー分野の研究が融合して生み出されてきた。
これと同じような新たな融合による発見を目指して、様々な材料について広い領域での電磁気的応答特性を調べようというのだ。
最後に課題探索・横断研究部門の杉本渉部門長が説明に立ち、「各部門が連携融合しつつ研究を進めていくうちに、そこで繰り広げる議論などの中から、新たな課題が浮かび上がってくることがあると思う。それを抽出し、新たな研究部門として設定するなど、部門間の横断的研究や意見交換を活性化させ、環境・エネルギー材料科学研究所全体のクロスブリード的展開を促進するのが、この部門の役割です」と話した。
そのために、研究所内外を対象した各種講演会や意見交換会などを企画・開催する予定だが、「単なる講演会やディスカッションではなく、相手の研究領域のことも深く理解し合った上で、異分野・異領域の発想やアイデアを出し合い、それまでの延長線上にはない、飛躍的な展開が起こるようなディスカッションを創出して行きたい。それが私たちが提唱するクロスブリードなのです」とまとめた。

環境エネルギー材料科学研究所ホームページ: http://www.shinshu-u.ac.jp/project/xbreed/
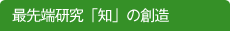
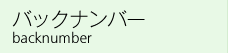
 X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02
X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02環境・エネルギー材料科学研究所
白熱議論で踏み出した新たな一歩
 信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」
信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」ナノセルロース、ナノカーボンの“ナノ・ナノ複合化”で、革新的な素材を創り上げる
 シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所
シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所「炭素の世紀」の開花へ 遠藤特別特任教授が熱く語るカーボンイノベーション
 シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所
シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所新世紀「炭素イノベーション」を創出!ナノカーボン分野で世界トップレベルの研究拠点がさらに進化。
 シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所
シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所5つの研究部門とミッション