


信州大学農学部と中国の浙江省農業科学院との間に国際交流協定が締結したことを記念し、平成24年11月20日(火)に農学部(南箕輪キャンパス)にて記念講演会が開催された。
中村宗一郎副学長・農学部長は「国際交流協定が締結したことで、今後一層、両機関で協力し合い、相互に発展していくことを期待しています」と開会挨拶を行なった。
講演には、浙江省農業科学院の潘建治教授をはじめ、動物バイオテクノロジーの研究における最先端の研究者らをお呼びし、世界の動物バイオテクノロジーについて俯瞰した。
さらに、生命科学の進歩が、人間生活の質的・精神的豊かさに如何に貢献し得るかについて、田園都市工学の観点からも展望した。"世界最先端の研究"、"研究の現状"、そして研究の成果を"人間生活へと取り入れていく展望"、という3つのテーマを軸に講演は進められた。
同講演には、200名を超える参加者が集まり、大成功のうちに終わった。
鏡味教授は「今後は、潘先生をはじめとする農業科学院の方々との交流を一層深め、共同研究を進めていきたい。更にこうした国際交流を通して、学生達にも海外というものを身近に感じてもらいたい」と話した。

200名以上の参加者が集まり、信州大学と浙江省農業科学院、両機関の繋がりを深めた
| ○ 歓迎挨拶: | 信州大学副学長・農学部長 中村宗一郎 教授 |
| ○ 記念講演: | 浙江省農業科学院・畜牧獣医研究所 潘建治 教授 |
| 「中国における畜産の現状と展望」 | |
| 麻布大学・獣医学部 押田敏雄 教授 | |
| 「意外と知らない畜産のはなし―畜産はどのように人々の暮らしと係っているのか」 | |
| 名古屋大学大学院・医学系研究科 小林孝彰 教授 | |
| 「遺伝子改変ブタを用いた異種移植:臨床への現状と展望」 | |
| (独)畜産草地研究所・家畜育種繁殖研究領域 田上貴寛 主任研究官 | |
| 「ニワトリ始原生殖細胞の性分化」 | |
| (大法)基礎生物学研究所・生殖細胞研究部門 中村隼明 研究員 | |
| 「ニワトリおよびマウスにおける生殖細胞移植」 | |
| 信州大学農学部・田園環境工学分野 上原三知 助教 | |
| 「より良い景観、より良い生活」 | |
| ○ 閉会挨拶: | 実行委員長・信州大学農学部 鏡味裕 教授 |
| ○ 抄録集 [The 2nd Memorial Lectures for Establishment of International Academic Cooperation Relationship between Faculty of Agriculture Shinshu University, Japan & Zhejiang Academy of Agricultural Sciences, China](1.66MB) | |


近年、動物バイオテクノロジーへの期待が高まっている。家畜の肉や牛乳、卵などの食料生産の効率化や安全な食料生産への期待はもちろんだが、現在は家畜の体内を用いて医薬品を生成する取り組みや一時的に畜産動物の臓器を人間へ移植する「異種移植」の分野も大きく進歩している。
記念講演で浙江省農業科学院の潘建治教授は、「中国における畜産の現状と展望」を語った。
現在、世界の豚肉生産量、消費量の半分以上は、中国が占めており、中国では、養豚技術の発展が求められている。同時に消費者の需要は二極化が進んでいる。富裕層には高級な豚肉の需要が高まっており、高くても美味しいものが食べたいというニーズが広がっている。潘教授は「その一方で貧困層の人たちは依然厳しい生活が強いられており、こうした層へ重要なタンパク源としての豚肉生産を進めていくことが必要です」と話した。
現在、中国の大勢は後者であり、今後さらに人口が増えていく中で、畜産の効率化を進めると同時に食の安全性を高めていく事が急務になっていることを示唆した。
健康的な家畜を生産するために必要な事について麻布大学の押田敏雄教授は「畜舎環境を清浄化し、家畜の抗病性を向上させて、家畜の健康を維持していくことが重要です」と話した。環境作りを進めていくことで、良質で美味しい畜産物の生産につながり、また生産の向上にも繋がっていくのだ。

動物の臓器を用いた異種移植への取り組みが世界で進んでいる。臓器移植は現在までに世界ですでに50万例以上行われている。欧米を中心にアジア各国でも定着してきている。しかし近年、各国では深刻なドナー不足が大きな問題となっている。多くの患者が移植を受けられずに亡くなっているのだ。
日本においては、97年に脳死の立法化が行なわれたが、未だ事例は少なく、多くの移植適応患者が亡くなっている。こうした事例を減らしていくためも、名古屋大学の小林教授は「急性の劇症肝炎や多機能不全に陥ったときに、一時的な対処として豚の肝臓を移植するという異種間の移植を視野にいれていく必要があります」と語った。しかし、倫理的な問題や技術の確立など課題も多いのが現状だ。
日本では、毎年ニワトリの雛が億単位で産まれている。しかし、採卵養鶏では雄が不要になり、ブロイラー養鶏では、雌が不要になってしまい、毎年多くの雛が淘汰されているのだ。
家禽学において、雌雄の産み分けというのは、最重要課題とも言われている。
(独)畜産草地研究所の田上主任研究員は、雄において精子、雌においては卵子になる始原生殖細胞をキメラの技術を用いて性転換出来ないか、という研究を進めている。効率は決して高くないが、卵子になるはずの始原生殖細胞を精子に分化させる研究に成功した。
「こうした技術を発展させていくことで雌雄の産み分けが可能になり、生産性があがり、淘汰される命も少なくなるのです」と田上主任研究員は語った。
また、(大法)基礎生物学研究所の中村研究員は、ニワトリなどの家禽類、ほ乳類であるマウスの発生と分化機構の解析を進めており、貴重な絶滅危惧種などの保存や再生への取り組みを講演した。

本記念講演会は、ニワトリとブタを主なキーワードに、世界の動物バイオテクノロジーの現状の俯瞰や実際に進みつつある研究の最前線が報告された。
最後に、こうした研究の成果がどのように人間社会に影響を与えるかという観点で、信州大学農学部の上原三知助教が田園都市イギリスを例に挙げて講演。
「実際の研究や技術論などを活用して田園都市を再生させていくことが重要です。その中で、いかに家畜との共存や協栄を果たしていくのかを考え、農業を再生させていくことで、美しい景観が蘇り、人々の生活も良くなっていくのではないでしょうか」と上原助教は力強く話した。
本記念講演実行委員長の鏡味教授は、「今後は、相互の機関から学生が行き来し、単位修得が出来る体制を作っていきたい。今回の記念講演では、世界の中でも最先端の研究者に講演をしてもらいました。本講演をキッカケにし、学生達が刺激を受け、世界を見据えて成長していく事を期待したい」と語った。
信州大学農学部と浙江省農業科学院の両機関が技術提携や共同研究を通して、相互に発展していくことに期待したい。
鏡味教授と潘教授は、2010年から親交があり、技術提携などを行なって来た。昨年9月12日、中村宗一郎農学部長と鏡味裕教授が浙江省農業科学院を訪れ、信州大学農学部との国際交流締結を結び、同日第1回記念講演が開催された。
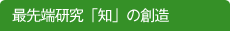
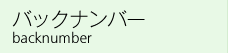
 X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02
X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02環境・エネルギー材料科学研究所
白熱議論で踏み出した新たな一歩
 信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」
信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」ナノセルロース、ナノカーボンの“ナノ・ナノ複合化”で、革新的な素材を創り上げる
 シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所
シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所「炭素の世紀」の開花へ 遠藤特別特任教授が熱く語るカーボンイノベーション
 シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所
シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所新世紀「炭素イノベーション」を創出!ナノカーボン分野で世界トップレベルの研究拠点がさらに進化。
 シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所
シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所5つの研究部門とミッション