



宮原 裕一(みやばらゆういち)
信州大学学術研究院 准教授(理学系)
先鋭領域融合研究群 山岳科学研究所
大気水環境研究部門長
東京理科大学卒業、同大学院(薬学研究科)修了、薬学博士
国立環境研究所を経て、2001年より信州大学理学部助教授、2014年より現職。
深刻化する地球環境問題の解決と人類を含む生態系の永続的な保全を目指し、自然環境のダイナミズムの解明とその再生・保全・活用および防災の実践方法を示すのが、本部門の目標だ。そのために山岳域での大気・水環境の諸現象を解明し、個別的問題の解決策から総合的施策までを構想する。宮原裕一准教授が部門長を務める。
具体的には、①地球規模での温暖化の現状と影響、対応策を練るための中部山岳域における気象観測の継続、②諏訪湖をはじめ山地湖沼の水文・水質・生物相に関する各種情報の集積の継続と分析・公開。特に諏訪湖の、生態系モデルによる水質変動の解析、③酸性雨やPM2.5など越境汚染の実態を明らかにするために、高標高での気象観測情報の活用と、他地域の研究者との共同により、山岳域での大気汚染物質の分析とその生態系への影響に関する調査と分析、④河川上流域における生態系保全や河川管理・防災に資するため、信濃川上流域の瀬・淵など異なる空間の生物生産の構造解明―などである。
高標高地点での気象観測装置、諏訪湖や信濃川上流域の観測ポイント、上高地ステーションや乗鞍ステーションなど、これまで以上に学内外の拠点を継続して活かす予定だ。

原山 智(はらやまさとる)
信州大学学術研究院 教授(理学系)
先鋭領域融合研究群 山岳科学研究所
地形地質・防災研究部門長
東京教育大学卒業、京都大学大学院(理学研究科)修了、理学博士
工業技術院地質調査研究所を経て1997年より信州大学理学部助教授、1999年同教授、2014年より現職。
御嶽山の噴火や南木曽町の土砂災害など、本年、信州では山岳域ならでは災害が続いた。東日本大震災・長野県北部地震なども記憶に新しく、地震・火山活動の突発現象や人間活動の拡大による災害と防災に関わる研究は喫緊の課題となっている。原山智教授が部門長を務める地形地質・防災研究部門は、山地および山岳の成立プロセスの正確な把握と、その理解に基づく環境保全と防災の方策の提案がミッションだ。
①北アルプスの「マグマ活動とプレート活動の相互作用」に関わる研究成果を追証・展開させ、中部山岳域全体の地形地質特性と形成プロセスを究明すること、②松本盆地の顕在・潜在活断層の位置情報と活動性の評価を皮切りにした、長野県内、また内陸盆地一般の活断層と地形形成史の研究、③南・北アルプスを主対象にした大規模地形変動(地すべり・深層崩壊・斜面災害など)の研究、④大陸衝突型山脈(ヒマラヤ)と島弧―陸弧型山脈の形成過程の研究、⑤湖成堆積物、雪渓・氷河の分析に基づいた中部山岳地域の16万年前からの環境変遷の研究、⑥長野県地形地質データの数値化と活用方法の開発、⑦ヒマラヤ―チベット山岳に関する国際共同研究の推進―などに取り組む。

平林 公男(ひらばやしきみお)
信州大学学術研究院 教授(繊維学系)
先鋭領域融合研究群 山岳科学研究所
水生生態系研究部門長
信州大学卒業、同大学院(医学研究科)修了、医学博士
山梨県立女子短期大学などを経て、1999年より信州大学繊維学部助教授、2008年より同教授、2014年より現職。
平林公男教授が部門長を務める水生生態系研究部門では、山地水域での水生生物などの分布やその生態系構造の解析を行う。地形や環境変動に影響を受けやすい水生生物の状況をビビッドに掌握することは、とりもなおさず、自然と人間との共生、地球環境保全の有力な導きの糸となる。
具体的な目標の一つは、諏訪湖の環境変動に対する生態系の応答の解明。諏訪湖は、水質浄化において先進的な湖であり、日本の陸水学の拠点の一つ。過去35年間にわたり信州大学理学部と同山岳科学総合研究所もその先頭に立ってきた。こうした歩みも踏まえて、同研究部門では、大気水環境研究部門とも共同・連携し、地球規模での気候変動や、下水道整備に伴う水質浄化などによって、諏訪湖の生態系がどのように変化したのかを明らかにし、国内外の環境保全や、湖沼における資源活用などの方策を提示する。
二つ目は、山岳域に生息する動物(主に水生生物)や、山岳形成が障壁となって特殊な個体群構造を有すると予想される動物種群を対象にして、その生息(分布)状況を詳細に究明すると同時に、分子レベルまでの解析方法で系統進化学的解析を行い、その保全や資源活用に資する。

泉山 茂之(いずみやま しげゆき)
信州大学学術研究院 教授(農学系)
先鋭領域融合研究群 山岳科学研究所
陸上生態系研究部門長
麻布獣医科大学卒業、京都大学霊長類研究所、株式会社野生動物保護管理事務所を経て、岐阜大学大学院(連合農学研究科)修了、農学博士
2006年より信州大学農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センター准教授、2010年同教授、2014年より現職。
寒冷・高山地帯の野生生物の長期にわたる基礎的生態研究、グローバルな気候変動や自然変化による陸上生態系の推移の把握と将来予測、さらには、急速に消滅しつつある生物多様性の回復や人間の生産活動と自然とが共存できる新しいシステムの究明―こうした広い範囲に及ぶ問題を、日本の中部山岳地帯をベースに、全世界と結んで研究するのが、泉山茂之教授が部門長を務める陸上生態系研究部門だ。
①山地帯から亜高山帯にかけて分布する山岳植物の遺伝的・生態的分化と「保存すべき単位」の確定(ポリネーター=花粉を運ぶ虫などの役割分析などを含めて)、②温暖化による気候変動がもたらす亜高山帯から高山帯の植生分布への影響予測、③森林土壌において有機物分解を担っている土壌微生物、特に、その活動のカギを握る制限因子についての究明と森林整備などへの活用、④生物多様性保全のための外来植物対策に向け、GPS(全地球測位システム)データの整理・可視化と、より高度なGPS(地理情報システム)を活用したモデル選択と管理プログラムの解明、⑤ニホンジカ、ツキノワグマ、ニホンザルなどの行動追跡調査・生息密度調査、対応策の提示―などが具体的取り組みテーマになる。

加藤 正人(かとうまさと)
信州大学学術研究院 教授(農学系)
先鋭領域融合研究群 山岳科学研究所長
国際山岳連携研究室長、森林資源研究部門長
宇都宮大学卒業、北海道大学大学院(農学研究科)、農学博士
北海道立林業試験場などを経て、2000年信州大学農学部非常勤講師、2001年より同アルプス圏フィールド科学教育研究センター助教授、2005年教授。2014年より現職。
加藤正人研究所長が部門長を兼務する森林資源部門は、国土の約3分の2を占める森林の持続的な資源利用、里山の放置による生物多様性の激減・野生鳥獣被害などへの対策と効果の検証をミッションとしている。そのためにレーザーセンシングなどの最新鋭の技術も導入し、森林資源研究の分野における国際的ネットワーク構築を目指す。
具体的テーマは以下の通り。①地形や森林状況などを広範かつ詳細に三次元計測するセンシング技術の開発。全世界で進む研究を日本の信州の地からリードしようという意欲的なテーマだ。②センシング技術も活用し、また、他の研究部門とも協力して、地球温暖化に伴う気候変動がもたらしている森林への影響を評価する。国内のスギ・ヒノキへの影響、国外の永久凍土地帯に生育する樹木への影響などが中心になる。③上記の研究などにも活用していくため、年輪に刻まれた過去の気候変動などもデータ化して利用するシステムの構築・拡大を図る。④南信州の企業等で作る伊那谷アグリイノベーション推進機構と連携し、中山間地の在来作物、山林で採れる山菜など食用野生植物の利用について、生物学的、生態学的また社会学的観点から調査を実施する。
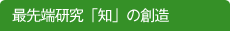
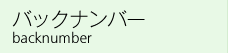
 X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02
X-Breed最前線 先鋭領域融合研究群最前線02環境・エネルギー材料科学研究所
白熱議論で踏み出した新たな一歩
 信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」
信州大学カーボン科学研究所「ナノアグリ―コンソーシアム」ナノセルロース、ナノカーボンの“ナノ・ナノ複合化”で、革新的な素材を創り上げる
 シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所
シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-2 カーボン科学研究所「炭素の世紀」の開花へ 遠藤特別特任教授が熱く語るカーボンイノベーション
 シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所
シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.5-1 カーボン科学研究所新世紀「炭素イノベーション」を創出!ナノカーボン分野で世界トップレベルの研究拠点がさらに進化。
 シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所
シリーズ先鋭領域融合研究群を追うVol.4-2 山岳科学研究所5つの研究部門とミッション