


近年、我が国において大学の「地域貢献」・「地域連携」は、教育・研究に続く第3の使命として明確に位置づけられた。本学の採択された「文部科学省の「地(知)の拠点整備事業」(以下、COC事業)」は、この第3の使命を軸に学生や教職員の"地域志向"を養い、地域と協働した教育や研究機能の強化を狙うものである。一方、欧米の大学では、このような取り組みを「University Engagement」と呼び、かなり以前から行ってきた。ボランティアやサービス・ラーニングなどは大学と地域とのつながり(約束)として全学的かつ体系的に教育・研究活動の中に位置づけるケースが多い。地域と連携した教育や研究を進めるために、日本の大学には何が必要なのか。平成26年2月9日~16日、米国での著名な事例を学ぶため、ウィスコンシン州立大学とジョージ・ワシントン大学の地域"連繋"部署へ、本学地域戦略センターの教員3名が訪問した。


モーグリッジ・センターは18年前に卒業生の家族(モーグリッジ氏)の寄付によって設立された組織である。「当初は、地域のボランティア活動と学生をつなぐことを主な目的としていたが、サービス・ラーニングが活発化するにつれて8年ほど前から大学の教育(学部)と地域のコミュニティをつなぐ機能も拡大してきた」と、ナンシー・センター長は語る。
現在、モーグリッジ・センターでは、地域の約200のNPOやNGOとパートナーシップを結び、全学的にボランティア活動やサービス・ラーニングの企画・実施・支援をしている。

ウィスコンシン大学では、年間約1300人、卒業までの期間で捉えると80%を超える学生がボランティア・プログラムに参加するという。
その中心となるのがバジャー(Badger)・ボランティア・プログラムである。バジャーとは、ウィスコンシン大学のキャラクターとなっているアナグマから名付けられており、参加者はみなお揃いのTシャツを着て参加する。これが地域での周知を促進したのか、2008年に学生50人、4つの地域コミュニティでスタートした取り組みが、2014年春には、実に学生700人、90コミュニティが参加するほどに成長したというのは驚くべきことであった。
バジャー・ボランティアは、学部の学生がプログラムを企画してリーダーになる。一学期の間、継続して同じコミュニティに通い、少しずつ変わっていくニーズにもうまく対応しながら、地域課題の解決に取り組む。
モーグリッジ・センターでは、専任コーディネーターを配置し、ボランティア参加のための研修(オンライン含む)を始め、地域での活動チームづくりを支援する。他にもボランティア達の移動課題を解決するためフリーの輸送サービスも地域と協働で整備し、チーム同士が調整して利用できるようにするなどの仕組みづくりに日々取り組んでいるという。


ウィスコンシン大学では、現在、年間75~80のサービス・ラーニングのコースを提供し、1年間に3,000人(全学部の5%)ほどが受講している。
驚いたのは、コースの作成にあたって、地域からの申し込みを受付ける仕組みができていることである。地域向けにサービス・ラーニングの定義を説明し、単なるボランティアではないこと、正課の授業として学部・学科の教育ポリシー、学習基準を説明し、事例等を紹介している。これに加えてモーグリッジ・センターの専任インストラクターが各学部・コースと協力するなど学習コースを創るプロセスが体系化されている点も特徴的であった。
近年は、地域内に拠点・組織をつくり、教員や学生が主体的に地域課題に関する調査・研究を行い、課題解決をするという、サイエンスショップの仕組みを活用した「コミュニティ--ユニバーシティ・エクスチェンジ」プログラムに力を入れているとのことであった。
ウィスコンシン大学のサービス・ラーニングに関する調査によれば、参加しない学生よりも参加した学生の方が、テスト等の平均点が高く、単位を落とす確率も低いことや、卒業までにかかる時間も短いことが示されているという。
地域を活かした教育・研究の成果・有効性が示されていることに感心したが、同時に、コミュニティ・パートナー達が、どんなことを求めているのか、どれぐらい満足しているのかを把握することを重要視している。
当然ではあるが、コミュニティーベース・ラーニングは大学の教育にとって有効であるだけでなく、地域にとっても価値がある、Win-Winの関係ができて初めて成り立つのである。我々の活動においてもこのことを常に意識しなければならない。
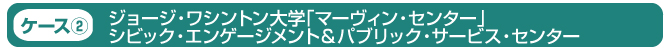
「ジョージ・ワシントン大学では、まず行動することを第一としている。だから、ボランティア・マインドなどを言葉で教えるよりも、活動の機会提供を重視している」「ジョージ・ワシントンの言葉どおり!」とコーディネーターのモーリスは語る。
アメリカでは、幼少時から教会やスカウト活動などを経験する機会が多く、大学入学の時点でボランティア・マインドが既に形成されている者も多い。そのため、入学時には、プログラムや活動事例を優先的に紹介し、多様な方法で活動する機会があることを伝える方が、全体的な学生のニーズにも適合しているとのことである。
ただし、学生は世界中から来ており、それぞれの経験知も同じではない。そこで各学部のアカデミック・サービス・ラーニングは、入門レベルから上級レベルまで65のコー
スを設定し、ボランティアやサービス・ラーニングもローカルなプログラムだけでなく、ワールドワイドにも用意しているという。

我々は、仮説としてボランティアに対する認識が異なる日本では、同じような地域“連繋”活動の実現が難しいのではないかと考えていた。しかし、エイミー・センター長らは「ジョージ・ワシントン大学でのボランティアやサービス・ラーニングのコアは、“アイデアの交換”や”能力の交換”」にあるという。
ジョージ・ワシントン大学は、首都という特殊なロケーションに加え、全部で6万人の学生を抱える巨大な大学である。センターのプログラムには、それぞれさまざまな文化を持つ国・コミュニティから出てきた学生たちが参加してくる。これを活かして彼らが、お互いに持っているアイデアや能力を交換し、またそれを地域とも交換しあうことで、社会問題の解決や新たな創造活動が可能になる。ジョージ・ワシントン大学は、さまざまなプログラムを通じて、その交換の場所をシステマティックに提供しているという。
ジョージ・ワシントン大学でのディスカッションは、まさに大学の地域“連繋”の定義を考える上で重要なアイデアの交換になった。
今回の調査で最も印象的なことは、両大学のスタッフ達がとても「自然体」で、「楽しそう」に仕事に取り組んでいることであった。我々の急な訪問を厭わずに歓迎し、自分の部署を超えて他学部や他部門に声を掛けてくれた。これは、「違う文化や取り組みをしている者達とディスカッションすることは、アイデアや能力の交換であり、自分たちにとっても時間を割くメリットがある」との考えを実践していることに他ならない。地域戦略センターのミッションとして、学内外で地域との連繋によるメリットを伝えるとともに、参加しやすい仕組みを構築する重要性を強く感じた。
また、「対話・アイデア交換」をする場・拠点の整備や環境・空間の創り方が印象に残った。モーグリッジ・センターはストリート・モールに近く、非常に目立つ建物であり、産学連携や同窓会など関連する組織の建物は同じエリアに集約されていた。ジョージ・ワシントン大学のマーヴィン・センターも一つの建物に関連する機能が集約されていた。さらに、どちらも地域から人が自由に入ることができ、新しいアイデアを生み出すために「対話」をする空間・環境が用意されていた。近年、欧米ではその最たる例として「フューチャー・センター」と呼ばれる「対話と創造」の空間や仕組みづくりが注目されているが、残念ながら我が国ではまだ一部で始まったばかりである。本学において地域と連繋した教育・研究による特徴づくり、ひいてはイノベーションを生み出していくためには、今後新たに大学学内や学外において「対話と創造」の場を整備していくことも必要であると感じた。
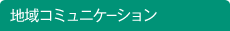
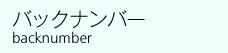
 教育学部発!地域志向研究
教育学部発!地域志向研究[ブナの実活用プロジェクト]ブナプロ!
 防災・減災 機能の強化を考える
防災・減災 機能の強化を考える平成26年度信州大学地域連携フォーラム
 ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり
ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり信州大学×日本ケーブルテレビ連盟 信越支部長野県協議会 連携協定
第3回連携 フォーラム
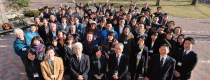 信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ
信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ 全コース合同成果報告会+修了式
 信州大学COC「信州アカデミア」
信州大学COC「信州アカデミア」 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ開講!