


松本市洞地区にある「桜柿羊の里」農事組合の里山活性化事業をお手伝いしながら、野菜づくりやビオトープに取組む、「里山ボランティアサークル洞楽村」(代表:理学部2年鏡味恭英さん)。その活動内容が評価されて、今年6月「第2回食育推進ボランティア表彰」(内閣府)にて受賞した。
地域や子ども達との交流を大切にする、「ほのぼの、ゆったりしたサークル」という彼らの活動の様子を追った。
・・・・・ 信州大学広報誌「信大NOW」第65号より

洞楽村は、農事組合長の飯沼さんから借りた畑で、野菜の有機栽培に取り組んでいる。夏の畑といえば、そこは草との戦いの場。油断すると「畑で雑草を育てています…」と思われかねない有り様になってしまう。
8月末の日曜日も朝6時30分から、草を刈っていた さん(人文学部3年)に、伊那からかけつけた中谷元彦さん(農学部3年)と井川桂佑さん(同2年)が加わり、草刈に精を出した。
さん(人文学部3年)に、伊那からかけつけた中谷元彦さん(農学部3年)と井川桂佑さん(同2年)が加わり、草刈に精を出した。
中谷「 ゴーヤ…、ああもう食べられるよ」
風間「 いや~、でけえ。黄色くなっちゃって、もうダメだ、これは・・」
井川「 大丈夫なのもあるよ。から揚げにすると上手いんだよねえ」
風間 「え~、そんなふうに食べたことない…」
皆からほめられるという手作り堆肥のおかげか、草は多くも、なるものは立派になっている。ほかに枝豆、トマト、なす、とうもろこし、唐辛子、ピーマン、メロン、スイカ、パセリ、バジル、さつまいも、じゃがいもに、レタス…と、かなり種類が多い。育ちすぎの野菜もあるけれど、風間さんは「有機栽培で作ったトマトって甘くてホントおいしいんです」と胸を張る。その堆肥とは、「魚のあらに豆腐かす、近所の精米所から頂いた糠ともみ殻、そして羊の糞と落ち葉」。自分なりに調べて、人からアドバイスを受けて作った自慢の堆肥だ。この畑は農家のように立派ではないけれど、彼等の一生懸命さが込められている。
風間さんが畑から道路脇へ出ると、ご近所から声がかかった。「がんばってるう? 草、気になったんだけど、手は出さなかったわよぉ」。

桜を植えて花を愛で、柿を植えて実を食べて、羊を育てて子ども達が命の尊さを学べるような里山活性をしようと『桜柿羊の里』農事組合ができてから13年目。洞楽村ができたのは、5年前。たまたま近くを通った2人の学生に飯沼さんがお昼ごはんを誘ったのがきっかけだった。その後、学生たちはお昼ご飯のおいしさにつられ、おもしろそうな活動だと農事組合を手伝い始めた。何度か通ううちに、今度は自分たちで畑をやりたい、遊休農地を使ってビオトープをやりたいと、夢を語りだす…。そこで飯沼さんのネーミングのアイディアを借りて「里山ボランティアサークル洞楽村」と名付けて本格的なサークル活動に突入した。

活動を始めた当初、ビオトープづくりにも力を注いだ。耕す人がいなくなった荒地を農事組合の方々と一緒に草を刈り、畦をととのえ、田んぼの形の見事なビオトープをつくりあげた。しばらくすると、そこには30年ぐらい前、この地で当たり前に生えていた植物の種(休眠種子)から芽が出てきた。また、ここにしかないのでは?という希少種も育ち始め、ビオトープはほんの数年で多様な生物の楽園となった。
現在は維持管理するための課題も多いが、風間さんや中谷さんはこの先もなんとか方法を見つけて続けていきたいという。
洞楽村の活動で「五感が刺激を受けるのを実感した」という風間さん、「洞の方々や子どもたちとのつながりを大切にしたいから」と伊那から通う中谷さん、「今年は肥料の醗酵熱を利用した苗床に挑戦したい」という鏡味さん。メンバーは里山という舞台で、それぞれに伸び伸びと、時には黙々と汗を流し、作物と一緒にたくさんのものを収穫している。
この夏、うれしいニュースが飛び込んだ。ビオトープづくりを頑張っていた先輩たちのカップルに赤ちゃんが生まれたという。メンバーも農事組合の方々も新しい命に会えることを楽しみにしている。
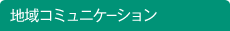
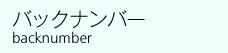
 教育学部発!地域志向研究
教育学部発!地域志向研究[ブナの実活用プロジェクト]ブナプロ!
 防災・減災 機能の強化を考える
防災・減災 機能の強化を考える平成26年度信州大学地域連携フォーラム
 ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり
ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり信州大学×日本ケーブルテレビ連盟 信越支部長野県協議会 連携協定
第3回連携 フォーラム
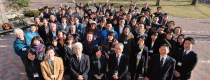 信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ
信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ 全コース合同成果報告会+修了式
 信州大学COC「信州アカデミア」
信州大学COC「信州アカデミア」 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ開講!