


農学部には農学部らしいサークルがある。
学生たちは「せっかく伊那谷にいるんだから」という思いと、「授業で習ったことを実践してみたい」という気持ちが重なり、実践の場を地域へ求めて繰り出している。
「草むら組合」「田んぼの会」「かーみやん」など第一次産業系サークルと呼ばれるグループは伊那谷の人々から、伊那谷の昔っからのことを教えてもらいながら活動している。
その一つ、「伊那守」の作業に同行した。
・・・・・ 信州大学広報誌「信大NOW」第63号より
授業で習ったチェーンソーなど、もっと上手く使えるようになりたい、そして伊那谷を守るお手伝いをしたいと始められたのが「伊那守」。もともと4ヶ所で森林整備や植林、地域の方々のお手伝いをしていたグループがまとまったサークルで、それぞれ部奈課、漆戸課、水無課、森ぷ課と4つの現場がある。
昨年水無課は、伊那市手良地区の地区行事、ハイキングを成功させようと地区公民館、南信森林管理署と協働し、ルート整備やガイドブックづくり、当日は森林ガイド役を務めた。郷学官が一体となったこの活動は、なんと林野庁長官賞を受賞した。

4月24日、朝7時30分に農学部に集合。本日の作業参加者は男4人、女3人の計7人だ。お手伝いに行くのは松川町生田部奈地区、1時間以上のドライブを経て到着した。始めに立ち寄ったのは、「部奈店」という雑貨屋さん。
「おはようございま~す」と車から降りた学生たちを迎えてくれたのは、作業の指導をしている林貞喜さんだ。林さんは、部奈を楽しんでもらえる里山に、集落全体を「公園」にしようと活動する「アルプスビューファームズ部奈」というグループの一員でもある。
「森林整備の仕方にはいろいろあります。ここは子ども達やいろいろな世代の人が楽しんでもらえることを目的に整備しているんですよ」と林さん。
学生たちと部奈との出会いは2年ほど前。林さんは伊那のお店で信大生のつぶやきを聞いた。「授業では少ししか実習できないチェーンソーをもっと使いたい。木を伐ってみたい」と。それなら「公園集落作りの森林整備を手伝ってみるかい」と林さんが誘ったのが、きっかけだった。
「もうねえ、いい学生さんばかりで、ここの地区の人はみんな感謝していますよ」と言うのは部奈店の店主伊東清子さん。ここで学生たちが来るとお茶を出し、お昼ごはんを作り、地元のことをいろいろ教えてくれる。
学生たちは、到着と同時に用意されたお茶を飲んでくつろぐと、林さんから作業の説明を受けた。
本日は、クリタケの種菌の接種(菌を木に埋め込む)と植樹作業をするという。部奈店を出て作業現場に向かった。山支度をして、チェーンソーに不備はないか確認をして、いざ。整備された道と違い、ズリズリと滑り落ちそうな山の急斜面を降りていく。赤い目印の紐がついた木を数本伐って、枝を刈り、1mぐらいの長さに揃え、その側面にチェーンソーで細長い溝を5、6本入れた。ここにクリタケの種菌がびっしりついた割り箸を埋めて、クリタケの栽培をする。学生の一人がチェーンソーで木を伐り始める。細い木でも14.5mあれば、倒れる時はそれなりの迫力。ドサーッと倒れると「ウォー」と歓声があがり、「上手、じょうず」と伐った仲間に声をかけていた。
山仕事の緊張感を感じつつも、楽しそうにこなしていく学生たち。「やらなきゃいけないとかじゃなくて、楽しいからやっています」と前サークル長の藤田ゆうさん。小柄だけれどチェーンソーをもつ姿が様になっている。「自分が農学部にいる意義を実感できます。伊那守めちゃいいです」山や木が大好きだという高主知佳さん。「鳥の声や山菜など詳しい仲間がいて、いろいろ教えあったりするのも楽しくて、伊那守はやめられない」と、「か~みやん」でも活動している真山寿里さん。
作業が一段落すると、そろそろお昼にしようと山を下ることになった。部奈店に戻ると、今度はお皿にあふれんばかりに盛られたカレーが待っていた。


林さんは学生たちを迎えるために、作業を考え、その準備をする。結構、手間がかかるが厭わない。学生たちは林さんから様々なことを学びながら力を尽くしていく。
部奈地区里山整備利用推進協議会の会長伊藤頼人さんは「学生さんに来てもらって地域がにぎやかになっています。部奈という地域のことを覚えていてもらい、活動して得たことを、将来、活かしてほしいと思います」という。
人口が減少するような地域にあっても、夢を抱きコツコツと実現させようと頑張る人々がいる部奈。学生たちの活力と吸収力、何より楽しみたいという気持ちが一緒になって生まれた、コミュニケーションパラダイスだ。作業の効率よりも、お互いの持っている“いいもの”の交換ができて、一緒に歩く事ができればそれでいい。
午後の作業は、斜面にクワで穴を掘ってミツバツツジなどの苗木を植えた。結構急な斜面を掘るのは大変だったが、途中で林さん宅のお茶をご馳走になって一息をつく。最後に午前の現場に戻ってクリタケの種菌を埋めたほた木に葉を被せて、本日の作業は終了。午後5時を回った。
サークル長の宮本隆志さんは「私たちはこの伊那谷にいる、ということを活かしたいと思っています。お祭りなどに参加して、地元の方と仲良くなり、地元の方々を通して、林業を見ていけるようにしたいと考えています」。なるほど伊那を守りたいというのは、地元の人の視点を共有することなのだ。
学生たちと伊那谷の方々とのお付き合いは、これからも末長く続けられそうだ。
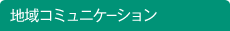
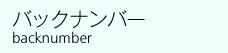
 教育学部発!地域志向研究
教育学部発!地域志向研究[ブナの実活用プロジェクト]ブナプロ!
 防災・減災 機能の強化を考える
防災・減災 機能の強化を考える平成26年度信州大学地域連携フォーラム
 ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり
ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり信州大学×日本ケーブルテレビ連盟 信越支部長野県協議会 連携協定
第3回連携 フォーラム
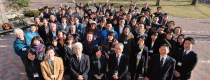 信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ
信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ 全コース合同成果報告会+修了式
 信州大学COC「信州アカデミア」
信州大学COC「信州アカデミア」 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ開講!