

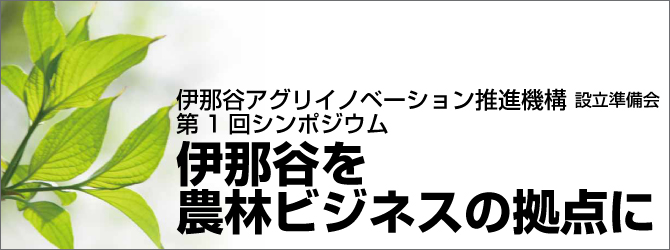
信州大学農学部の研究シーズを、伊那・駒ヶ根・飯田の3市を中心とした伊那谷地域の企業や各種団体のニーズと結び付けることで農林ビジネス拠点の構築を目指す「伊那谷アグリイノベーション推進機構」の設立準備会が9月18日、第1回となるシンポジウムを開催した。当日は、伊那谷の産業界や3市を中心とした周辺の地域自治体、大学等の関係者202人が参加し、伊那谷地域の具体的な課題や農学部が保有する2件の研究シーズを共有した。
伊那谷アグリイノベーション推進機構は2013年春の設立を目指し、今年度は3回のシンポジウムを計画している。今回は、地域再生の核となる大学づくり「COC:Center of Community」の実現を目指して動き出した農学部の思いと、設立準備会の今後の方針、更には地域自治体のさまざま期待などを報告・意見交換した。

シンポジウムではまず、同機構設立準備会の会長である電子部品製造会社㈱KOAの向山孝一社長が座長を務め、伊那谷を代表する3市(飯田市・駒ヶ根市・伊那市)の各市長を迎え、パネル形式で期待と要望を聞いた。
各市長の意見を受け、向山座長は、「農学部でどんな研究が行われていて、どのようなシーズがあるのかを教えていただき、地域社会がそれを理解することからはじめたい」とまとめた。

伊那谷は養蚕や繊維工業にはじまり、農業・工業を問わず産業の集積地だ。学術研究推進都市を目指す試みは、この地域にとって大変意味があり、地域の将来を考える上で非常に重要な取り組みである。飯田下伊那地域では、これまで南信州飯田産業センターが、産業界や行政との連携の中心となって、拠点として機能してきた。また大学連携についても、知のネットワーク「学輪(がくりん)IIDA」というものを立ち上げ、20以上の大学と連携をしながら取り組んでいる。こうした経験に加えて、信州大学農学部との連携は、きっと気付きがあるだろうと期待している。

地域の特色を活かし、地域全体の活力を生み出すべく6次産業化を推進しているが、その活動の中でいくつかの限界を感じることがある。そのような課題を、農学部あるいは新しい機構と一緒に解決することができればうれしい。農家の高齢化で問題になる農業の省力化の研究や、一般住宅との共生に向けた農業機械の小音化などにも取組んでほしい。農業関係の連携はこれまで主に県の団体や施設を活用することが多かったが、今後は、地元の農学部がもっと地域に出て、地域の企業とも連携し、行政主導ではなく、大学主導で人材育成などを進めて欲しい。

将来的には伊那谷全体が自活・自立できる地域にして行きたい。特に伊那谷の共通テーマである農業・林業・景観・観光の分野では、行政区域を越えて広域的に連携する必要性がある。大学のシーズやマンパワーにも限りがあり、リソースを有効にかつ効率的に活用する具体的な提言が重要だ。期待は大小さまざまあるが、まずは農学部が地域に対して門戸を開いている大学であって欲しい。教育の分野では、地域をフィールドとして使ってもらったり、子ども達をはじめ、地域の人達が自分の事として地域に目を向けることのできる仕組みづくりに、一緒に取り組んでいきたい。
シンポジウムでは、地域振興における具体的テーマをめぐり2つのパネルディスカッションが行われた。一つ目のテーマは「ソバ・雑穀の品種開発」。農学部の食料生産科学科の井上直人教授が話題提供し、高遠そば組合理事の伊藤亨氏が座長を務めた。 井上教授は、「省エネ生産が可能、気象ストレスに強い、保存性が高い、栄養価が高くバランスが良い―などの特長を持つ雑穀は、伊那谷でも馴染みの深いもの。特に、その中でも気候や風土、文化などとの関係からソバがブランド力のある食品になっている」と話し、28年にわたり地元企業と一緒に研究を続けている「高嶺ルビー」という赤蕎麦を挙げて地域連携について言及した。 そして「イノベーションの精神を大切にしながら、50年・100年と研究を続けられる大学の体制を構築しなければならないと感じている」とまとめた。 パネリストの登喜和冷凍株式会社の社長で、伊那アマランサス研究会会長の登内英雄氏は、「研究会活動で最も難しかったのは栽培だ。10年後に残る仕事にしていくためには、人・もの・お金、それに計画など、さまざまな観点から内容を自立させて行かなければ難しいだろう」と話した。 また、伊那市長谷地区の道の駅にあるレストランで、雑穀を提供し始めて7年目になる吉田洋介氏は、「メニューの中心に雑穀を据えてお客様に提供しているが、栽培する人が増えない、雑穀は食べられることの認知度向上、生産者のための販路開拓が必要であり、信大には、手間のかからない栽培方法の確立や加工品開発で期待する」と述べた。
二つ目のテーマは、「里地・里山保全と持続的な街づくり」。景観計画・造園学が専門の農学部森林科学科の上原三知助教より話題提供が行われた。 上原助教は、「持続可能とは、少なくとも25年以上の期間、機能や価値が保たれることであると定義し、260年以上続いている里地・里山の文化から、現在の街づくりにおいて学ぶべき事が多い」として、小さなスケールで適地適作が行われ、複合的な活用方法が多様な環境を生み出している里山のことや、ランドスケープ的な、総合的で包括的な空間デザインによって、多様な街づくりを考えることも可能であるとことなどを話した。 そして景観計画は、「森林だけ」とか「住宅だけ」とかいう学問ではなく、全体を見る学問であるため、伝統的な土地利用などを考慮して再評価を行うことでき、新たな産業の創出にも繋がるとまとめた。 これを受けてパネリストの伊那食品工業株式会社会長の塚越寛氏は「かんてんぱぱガーデンに代表される伊那食品の取り組みは、競争社会において、目先の効率よりも、自分たちの活動が社会にどの様な影響を与えるのかを良く考える、長期的視点で経営を行っている」と発言。 また、県産材で住宅を作る株式会社フォレストコーポレーション社長の小澤仁氏は、「森林組合や製材所など、多くの人たちの協力もあって、建築主が自分の山あるいは地元の山に入って木を切るところから始まる家づくりに取り組んでいる。人々が山に入って山の資源を活用することで、里山のある暮らしがもっと身近に感じられるような社会を作りたい」と話した。
(※その他にも多くのパネリストが発言されましたが、紙面の都合上、紹介を省略させていただきました。ご了承ください。)
 信州大学 副学長(特命戦略担当) |
大学の使命は研究と教育に加え地域貢献であると考えており、特に大学は地域に貢献してこそ、その価値を見出すのだと常々考えてきました。伊那谷を一つの運命共同体として、地域の課題や大学の研究情報を共有化することは効果的であると思います。そのような機能を持つ共同事務所、あるいは新しいことを考えるインキュベーションセンターの様な拠点を作りたいというのが、そもそもの構想の発端です。
農学がカバーする範囲は大変広くなっているにも関わらず、日本の第1次産業が占める割合はおよそ1.7%であることは大きな課題です。「農業が元気であれば、地域が元気になるし、産業も元気になる。」という信念の基、今いちど農業・農学の意義をきちんと考え直す必要があると思っています。
農業の意義を再考するにあたり、第一に農業は市場経済の一翼を担うという内部経済の観点、第二に、農業の公益的機能と言われている外部経済の観点、そして第三に、リスク管理の観点における食料安全保障―これはTPP関連の諸問題も含みます―が重要です。このような観点を踏まえて、例えば可決されたばかりの「株式会社農林漁業成長産業化支援機構法」などの仕組みに対しても、しっかりと分析して確実にコミットできるような機構をつくっていきたいと考えています。
なお、そのために、現在の農学部に足りないであろう政策や経営の分野については、8月22日に慶應義塾大学総合政策学部、環境情報学部及び政
策・メディア研究科と包括的な連携協定を締結し、私達の日頃からの自助努力と平行して外部からも支援を受けられる体制を構築したところです。決して短
期的な取り組みではなく、10年、20年といった長期スパンの視点で、世界のゲートウェイとしての伊那谷を目指したいと思います。そして、この地を伊那谷の
特長を活かした学術研究都市に育てていきたいと思っています。
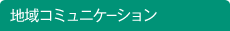
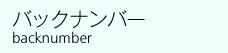
 教育学部発!地域志向研究
教育学部発!地域志向研究[ブナの実活用プロジェクト]ブナプロ!
 防災・減災 機能の強化を考える
防災・減災 機能の強化を考える平成26年度信州大学地域連携フォーラム
 ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり
ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり信州大学×日本ケーブルテレビ連盟 信越支部長野県協議会 連携協定
第3回連携 フォーラム
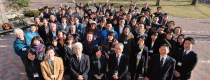 信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ
信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ 全コース合同成果報告会+修了式
 信州大学COC「信州アカデミア」
信州大学COC「信州アカデミア」 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ開講!