


信州大学繊維学部と上田市立豊殿小学校との連携プロジェクト「豊殿サイエンスキッズ」の一環として、森川裕久 学術研究院教授(繊維学系)とバイオメカニクス研究室(森川研究室)の学生らが7月23日、豊殿小学校に出向き、6年生に向けた理科の出張授業を行なった。
本プロジェクトは、上田市教育委員会からの要請を受け、児童に科学に対する親しみを沸かせ、不思議がる感性を育てようと、豊殿小学校と信州大学とが連携して企画したもの。
今回の授業では、一人ひとりに配られた材料を使って自分なりのメカフィッシュ(アクリル製のヒレを振って進む木の船)を制作し、最後にそれをプールで競争させる、という内容で、子供たちは目を輝かせてメカフィッシュ作りに没頭した。

森川教授の現在の研究テーマは、イルカの遊泳挙動解析。水棲動物の動きを工学的に応用する研究をしている。エンジンをつけた船は、環境に負荷を与えるが、ヒレを振って水中を進む魚がたくさん居ても環境に不都合はない。水生動物からその推進方法について学び、安全で環境にやさしい推進機の開発を手がける。
今回子供たちと一緒に作るメカフィッシュも、水棲動物のようにヒレを左右に振って進む仕組みだ。メカフィッシュの制作に入る前に、森川教授は水棲動物の推進について、水の中の生物たちはどのように泳ぎ、なぜ速く泳ぐことができるのかを子供たちに説明した。尾びれの形ひとつ取っても生物ごとに様々で、その形によって泳ぎの速さにも差がでてくるという説明を、子供たちは真剣な表情で聞いていた。

その後、班ごとに、信州大学繊維学部バイオメカニクス研究室の学生が指導につき、メカフィッシュの制作が始まった。メカフィッシュは、ゴムの回転を動力とし、アクリル製のヒレを左右に動かすことによって進む。子供たちはヒレの形や輪ゴムの結び方などに、工夫を施し、思い思いのメカフィッシュを制作した。
試作品を水の上に浮かべ、その進み具合を何度も試し、まっすぐ進まない、うまくヒレを振らない、などと苦労しながらも、自分なりの改良を重ね、真剣に物作りを楽しんでいた。
ちなみにメカフィッシュの材料となる木の板や針金等は、バイオメカニクス研究室の学生たちが、6年生児童48名分のものを一から準備したもの。信州大学の学生たちも、普段あまり経験しない子供と接する機会を楽しんでいた。

完成後は、学校のプールにメカフィッシュを浮かべ、その速さを競った。子供たちは水着に着替えてプールに入り、順位に一喜一憂しながらも、楽しそうに自作のメカフィッシュを競争させていた。
授業終了後には、子供たちから、班ごとに指導を受けた信州大学の学生に対し、感謝の言葉が送られ、学生たちも充実の表情を覗かせた。
参加した生徒は、「楽しかった。自分で手作りしたメカフィッシュはこれからも大切にしたい」と笑顔を浮かべた。
また豊殿小学校校長の宮下啓一氏は、「授業の一番の目的は、子供たちに理科の楽しさを感じてもらうこと。今日の授業は、自分で物を作る楽しさと、その苦労と、両方味わえたことがとても良かったと思う。子供たちはとてもいきいきしていた」と、満足げに語った。
授業を企画した森川教授は、学びを通し、環境や安全について考える子供たちになって欲しいと話す。
「今、手作りの機会は昔に比べてずっと少ない。今日の制作を通し、針金1つとっても思うようには曲がらないのだということを経験できたと思う。うまくいかない場面が出てきたら、そこでどうしたらうまくいくのかを自分で考え、試してみることが大切。モノづくりや生物の不思議さに触れ、それらに関心を持って欲しい。自然の不思議に触れることは、命の尊さを知ることに結びつくと思う」。そう語った。
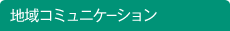
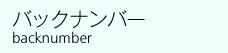
 教育学部発!地域志向研究
教育学部発!地域志向研究[ブナの実活用プロジェクト]ブナプロ!
 防災・減災 機能の強化を考える
防災・減災 機能の強化を考える平成26年度信州大学地域連携フォーラム
 ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり
ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり信州大学×日本ケーブルテレビ連盟 信越支部長野県協議会 連携協定
第3回連携 フォーラム
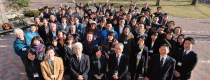 信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ
信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ 全コース合同成果報告会+修了式
 信州大学COC「信州アカデミア」
信州大学COC「信州アカデミア」 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ開講!