

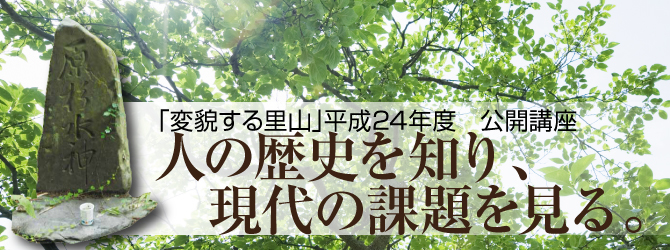
信州大学農学部では、一般市民向けに毎年2回の公開講座を行っている。今年度の第1回目が、農学部森林科学科の中堀謙二講師が「変貌する里山」と題して平成24年8月7日に開催された。地元の高校生や地域、県外等から17名の参加者が集まった。
午前中の講座では、伊那谷を例にとり近世(江戸時代)以降の森林開発や土地利用の歴史などを辿り、人々の生活と里山の関係がどのように変わってきたのかを講義。午後には、実際にフィールドに出て、信州大学農学部キャンパスの土地利用の変遷について見て回った。最後には、実際にスコップで演習林の土を掘り、どのように土地が活用されていたかという調査も行った。

「現代人の生活には光と影の両方がある。光の部分は、便利な生活や飽食と言われる食環境です。しかし、その裏側にある影の部分、つまり熱帯林の減少や種の絶滅、地球温暖化などの上に成り立っていると言う事を忘れてはいけません」と中堀謙二講師は指摘する。
現代の日本の生活は、「地域外資源」や「生物圏外資源」によって支えられており、食料や材木などの海外への依存度は高まっている。食料自給率は40%を下回り、木材の自給率においては、30%以下である。エネルギーは、化石燃料や原子力などが中心となり、“生物圏外”の資源を活用している。その結果、国内の耕地は減少し、肥料や燃料を採取していた採草地や薪炭林は衰退した。それに伴い日本の森林面積は増大している。
「多くの日本人は里山や森林を見ると、昔ながらの自然が残っている、と言います。しかし実際はそうではありません」と中堀講師。江戸時代中期以降、人々は里山の資源を利用して生活していたため、現在のような鬱蒼とした森ではなかった。「戦前まで昔は中央アルプス山脈を歩いている人が下から丸見えだった。今はもう森に囲まれて一切見えないけれど、と地域のおばあさんが話してくれました。今と昔の里山では風景が全く違うのです」と中堀講師は力を込める。
昔ながらの風景というのは、実は手入れが十分になされた里山のことなのである。

「里山というのは、地域住民が生活に必要な資源を得る土地のことであり、昔は里山のことを“ヤマ”と呼んでいたました」という。原生林だった森に地域住民の手が入り、少しずつ“ヤマ”になっていったという。燃料を採取する“薪炭林”や農業用肥料である枯敷などを採取する“枯れ敷山”や“採草地”、また馬の餌を得る“秣場(まぐさば)”などとして、広く利用されるようになる。
里山と人との関係は、人口の増加に伴い変化してきた歴史がある。江戸時代初期に1230万人だった人口が江戸時代末までに3300万人に増加した。食料増産のため、里山は使用されるようになった。新田開発が行われ、肥料が採取された。田畑1町歩(≒1ha)の地力を維持していくためには10~12町歩程の採草地が必要だと言われており、森は更に切り拓かれていった。明治時代になると、緑肥となるレンゲや金肥(魚粉・油かす・石灰など)が普及し、採草地などは針葉樹植林地の薪炭林、柴山へと姿を変えてきた。
時代の変化とともに里山と人との関係性は変化してきたが、人の生活の隣には常に里山があった。しかし、戦後になると、木質エネルギーは化石エネルギーへと変わり、農業用肥料は、化学肥料へと変わり、日本中の里山は薪炭林や採草地としての需要を失った。これまで利用されていた低木や枯れ枝が、物資的資源として利用されなくなり、里山は現在の針葉樹の深い森へと変貌したのだ。地域から地域外へ、生物圏外資源へと依存を強めていくことで、里山は放棄されるようになっていったのだ。

フィールドワークでは、農学部のキャンパス内を巡り、植生と土壌と遺跡から土地利用の変遷を辿った。
信州大学農学部のキャンパスは、中央アルプスの複合扇状地の扇央部に位置しており、生活水が得がたかった。そのため、江戸中期から明治中期までは馬の飼料採取の採草地として利用されてきた。しかし、明治30年代になると、馬の採草地の必要性が低下。そのため、この地で芋を作っていた原杉蔵氏が総延長720mの横井戸を掘削して水田を拓いたという。こうした歴史を記した石碑などがキャンパス内に多数あり、石碑や横井戸の跡地などを見学した。
中堀講師は最後に、「多くの人が、日本の森林は減少していると思っています。しかし、実際は逆なのです。明治以降、日本の人口増で国内の森林は増えたが、海外の森林が減少してきているのです。過去から人間の生活の営みがどのように変わってきたのかを見る事で、今、私たちが置かれている状況が分かります。実際はどうなのか、ということを惑わされない視野を持って下さい。そして、光だけでなく、影の部分に目を向けて欲しい」と締めくくった。
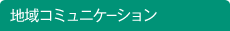
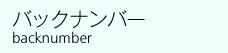
 教育学部発!地域志向研究
教育学部発!地域志向研究[ブナの実活用プロジェクト]ブナプロ!
 防災・減災 機能の強化を考える
防災・減災 機能の強化を考える平成26年度信州大学地域連携フォーラム
 ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり
ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり信州大学×日本ケーブルテレビ連盟 信越支部長野県協議会 連携協定
第3回連携 フォーラム
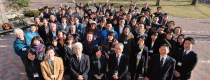 信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ
信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ 全コース合同成果報告会+修了式
 信州大学COC「信州アカデミア」
信州大学COC「信州アカデミア」 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ開講!