




伊那市は中央アルプスと南アルプスという二つのアルプスに抱かれた街。登山や山岳観光に関する歴史的蓄積も多い。南アルプスの世界自然遺産登録とも関連付けながら、こうした歴史的蓄積をどのように継承・発展させていくかも連携事業のテーマである。(文・毛賀澤明宏)
中ア・西駒山荘、南ア・塩見小屋 ― 特色を生かした建て替えを
現在の課題は、中央アルプス駒ケ岳の登山道にある西駒山荘と、南アルプス塩見岳の頂上に最も近い塩見小屋の建て替えだ。工学部建築学科の土本俊和教授研究室が設計を進めている。
西駒山荘は、新田次郎が小説「聖職の碑」に書き記した学校登山での悲しい事故の舞台にもなった場所。学校教育の歴史においても重要なスポットになっている。この建て替え計画について、「歴史のある山小屋なので、文化遺産として残しながら、利用客のための利便性も高めたい」と土本教授は話す。古くから伝わる石積みの部分はモニュメントとして残す一方、小屋の内部には床に意図的に段差をつけるなどして、広がりのある空間を保ちながらも、グループごとのスペースの区切りをつける、現代的な構造を組み入れる。
南アルプスの塩見小屋は、厳しい自然環境の中、何回も雪で壊れながらも、古材を有効に使って建てなおされてきた痕跡がうかがえるという。「塩見小屋の規模や形態は、塩見岳に関わる人々の長い経験によって培われたものだ。それを承け継ぎながら、周辺に山小屋が少ないという条件下で、比較的収容人数が多い、シンプルな形の山小屋を目指す」と話す。
中部山岳地帯の山小屋は、近世からの山岳信仰の歴史と、ウォルター・ウエストンに始まる近代登山の歴史の交点に位置する独自の文化的意味を持つ。「伊那谷には農学部と演習林もあるので、それらと山小屋を結んで、高山帯から里山をつなぐ広大な研究フィールドを拡げていきたい」と夢を語った。

平成23年から始まっている「子どもの健康と環境に関する全国調査」、通称「エコチル調査」も連携事業の現在的な大きな柱だ。上伊那地域が対象地域の一つで、伊那中央病院を中心に、2712組の親子に、子どもが13歳になるまで継続調査をお願いする壮大な事業だ。(文・毛賀澤明宏)
健やかな環境づくりのための「次世代への贈り物」
全国15地域で合計10万組のお母さんと子どもを対象に進む調査で、環境中に含まれる化学物質等の影響と子どもの健康状態の関係を統計的に明らかにすることを目指している。信大医学部が山梨大学医学部とともに甲信地域のユニットセンターとなり、長野県では上伊那が調査地域に選定された。上伊那の中心市である伊那市をはじめ行政・市民の協力なしにはできない調査だ。
昨年1年間に上伊那地域で調査に同意してくれたご家族は577組。目標数字からすれば達成率は7割だが、日に日に同意率が高まってきている。「調査の目的や協力をお願いする項目などをできる限り丁寧に説明している」と伊那中央病院の中山ゆかり看護師長補佐は話す。エコチル調査の最前線に立つリサーチコーディネーターの一人だ。
「当病院だけでは到底受け入れきれない調査だが、民間の産婦人科の先生も積極的に協力して下さり、地域を挙げて調査を進めようという良い雰囲気になってきた」と同病院産婦人科の上田典胤医師は手ごたえを感じている様子だ。
取組みのリーダーである信大医学部の野見山哲生教授は、「伊那市など行政の強力なバックアップに感謝したい。地域にとっても全国的にも有意義な調査にするため努力したい」と意気込みを話す。調査2年目に向けて、伊那市等自治体―信大―地域の医療・教育関係者のスクラムはますます固くなりそうだ。
信大との連携で市長のご感想は?
医療・教育関係から、産業、自然環境保全まで大小含めれば30近い連携事業を進めている。中には数十年続いているものもある。信大の研究にヒントをもらい、教職員学生の人的力をお借りして初めてできているものもあり、伊那市にとっては大きなメリットになっている。
特に注目している連携のテーマは?
獣害対策は、年々成果が目に見えてでてきている。全国的にも誇ることができる画期的ケースではないか。防護柵の作り方や、くくりわなの仕掛け方など、農学部の教員や学生が、地元の人や猟友会の人と一緒になって研究・普及してくれた。夜昼なく、高山から里山まで、現地に出かけてくれることに頭が下がる思いだ。シカの食害で壊滅的だった仙丈ヶ岳の高山植物が戻ってきたことに感動した。
製造業への信大研究シーズの活用は?
自分は民間製造業企業の出身なので、その重要性は以前から注目してきた。最先端素材技術、医療関係、食品関係など伊那谷で、「次の一手」を探っている企業は数多くある。そういうところと信大の研究とをマッチングできるようにしたい。企業サイドからは「大学は敷居が高い」という声をよく聞く。利益を目的とする企業と、学問研究の府である大学とは、目的も性格も違うから仕方ない面もあるが、地域の声、企業の声を大学に届けるのも行政の一つの仕事ではないかと思う。
福祉や生涯学習面ではどうでしょう?
エコチル調査には全面的に協力している。公立の保育園を持っている伊那市ならではの協力ができているのではないか。市町村にも色々な特性があるので、それを見極めてうまく活用してくれると、具体的成果が増えるだろう。学部を越える協力体制で連携事業に取り組んでもらえるシステムの強化も重要だ。特に、未来を担う子どもたち、大学にとっては次世代の研究者の卵だが、それへの関わりを強めてほしい。大学院工学系研究科中島厚先生が、伊那市創造館で体験学習の講義をして下さっているが、科学に関心を持つ子どもを育てるためにとても重要だ。そういう取組みをこれからももっと増やしていってほしい。

伊那市長
白鳥 孝(しろとりたかし)氏
伊那市出身。地元の伊那北高校在学中は野球部のエースとして活躍。立教大学卒業後、地元の民間企業に就職。2004年に伊那市収入役に就任し、2010年の選挙で当選。山歩き・渓流釣りなどに造詣が深く、自然環境保全についての問題意識が強い。
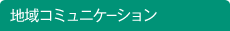
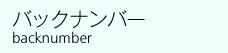
 教育学部発!地域志向研究
教育学部発!地域志向研究[ブナの実活用プロジェクト]ブナプロ!
 防災・減災 機能の強化を考える
防災・減災 機能の強化を考える平成26年度信州大学地域連携フォーラム
 ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり
ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり信州大学×日本ケーブルテレビ連盟 信越支部長野県協議会 連携協定
第3回連携 フォーラム
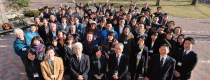 信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ
信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ 全コース合同成果報告会+修了式
 信州大学COC「信州アカデミア」
信州大学COC「信州アカデミア」 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ開講!