


“長野の方言をしゃべる建築” ─ なんて素敵な表現だろう。そういう建築物に興味と愛情を持ち、「自分たちの学びも活かして、蘇らせ、長野の町を生き生きさせたい!」と活動する学生たちがいる。
工学部建築学科の有志15人で作るteam HACILA(ハシラ)。手探りの活動開始から1年半が過ぎた彼らの、最近の“現場”を訪ねた。
・・・・・ 信州大学広報誌「信大NOW」第62号(2010.3.26発刊)より

カンカンカンカン・・・ 長野市東町。2階建ての立派な土蔵の前で、のみと槌を一心に使って、レンガを切断している男性がいる。
「お施主の花岡儀八さんです」。チームのメンバーに紹介されたが、えっ? お施主さんが作業するの? 花岡さんは慣れた手つきで、レンガを綺麗に二等分すると、「できたよー」とメンバーに声をかけた。「おー、すごい。ありがとうございます!」。なんだか孫と祖父みたいだ。
花岡儀八さんは花岡儀八本店6代目。「3代目の明治4年からは、酒屋だったという記録が残っていますが、その前は記載がなくて」。106年前に建てられた土蔵は、「冬は凍みず、夏は涼しい」ため、お酒の保管庫として使われたが、妻の紘子さんが嫁いだ1967年にはすでに物置と化していた。さらに歳月は流れ、土の上に直に張った木の床は、腐ってぼろぼろの状態に。HACILAの面々は、現在、土蔵の床をレンガ敷きにする作業を行っている。

「嫁は蔵には入りにくい。嫁いで5年目に初めて入りました」と紘子さん。そこには、冠婚葬祭用の何十組もの器や炭火を入れてお燗する器具、木製の大きな看板、蔵元が作った美人画の販促ポスター、飾り金具が美しいすずり箱などがひしめき、紘子さんには「宝の山」。けれど、価値観や生活様式が変わり、それらは「生活には不要」なものに変化していた。
「でもね、店に飾ったり、店の横に小さな展示室を作ったら、多くの人が喜んでくれて・・・」うれしかったが、老朽化した土蔵はやはり悩みの種だった。そんな時、長野市大門町の土蔵を地元出版社と協力して、豆製品を扱う期間限定セレクトショップ「信州豆蔵」に改修したHACILAの存在を知った。
「紹介記事を見つけた時、これだ!って思ったんです。このチャンスを逃したら、この蔵はいつか駐車場になってしまう」。紘子さんが祈るような思いでメールを送ると、代表の新井拓也さん(4年)ら6人がやって来た。「素晴らしくて驚きました。床は使い物になりませんでしたが、屋根も外壁も改装され、問題はない。2階の梁はそれは見事!」。
「こんな若い人たちが、素晴らしいと言って、蔵を大事に扱ってくれて・・・」。「宝物」を飾るギャラリーや演奏会などができる空間にと紘子さんの夢は広がり、次女の若林慶子さんも作業に参加。家族中で完成を楽しみにしている。

HACILAの実績は、アパレルショップのインテリアデザインと施工、レストランバーの改装補助、豆蔵の改修などわずかなもの。学びは半ば。溢れているのは「長野の町を盛り上げたい!」という熱い思いだけだ。「全員、学生なので、作業もまったくの手探り。その上みんな自己主張が強いので、言い合いばかりです。現場に出ないとわからないことがいっぱいあった」と口を揃える。
人通りの多い豆蔵の現場には『ただいま作業中。お気軽にお入りください』という看板を立て、多くの人に関心を持ってもらえる工夫をした。看板の効果はてきめん。励ましの声や差し入れが届き、近所の人は毎日覗きに来る。その中に「大工の棟梁がいて、あれこれとアドバイスを頂きました」。地域の人との縁で見つけた物件は、地域の人との縁で完成にこぎ着けた。マスコミにも取り上げられ、花岡さんとの縁にも恵まれた。
材料費の10%をチーム運営費として貰うが、お施主さんとは、同じ目標に向かう同志のような関係という。お施主さんが作業に加わることで、建物への愛情も理解も深くなるというメリットも。

実測調査、内装デザインの打ち合わせ、蔵の中の片付け、床板の撤去、2階の壁の撤去・・・作業は楽ではない。でも学生たちは「現場は楽しい。自分たちにはまだたくさんの勉強が必要。けれど、大学で模型ばかりを作っていると、何のためにやっているのかわからなくなる時がある」。「建築学科は服飾科や美術科みたいに、学生時代に『実物』を造れない」。「自分の中だけで、『これはいい、これは悪い』と決めてしまうことが怖かった。HACILAの中で意見をぶつけ合い、それぞれが、できることを探し当て、判定は、町の人たちがしてくれる」。成長する迷いの中で、彼らが、自らの手で見つけだした道だ。
町の人たちの判定は「第5回信州イノベーション大賞・地域チャレンジ賞受賞」という形になって表れた。これは、信州大学イノベーション研究・支援センターと経営大学院が、県内の革新的な技術や地域連携の取り組みに功績のあった企業・団体を表彰するもの。授賞理由は『地域に希望や活力を与え、再開発型のまちづくりへのアンチテーゼとして、今後のまちづくりに大きな影響を及ぼす可能性が高い』。まちづくりグループとのネットワーキング力も評価された。
身近すぎて見過ごしていた「長野の方言をしゃべる建築」の魅力を発信してくれたのは、長野の方言をしゃべらない若者たちだった。
「古い建物は、土地の文化や歴史を記憶している。そういう建物がある風景も長野の魅力。壊してしまってはもったいない」「古い蔵を初めて見る人もいる。物理的には古いものだけれど、『自分には新しい』という価値観を持ってくれる人がいるはず」。
新井さんは「中心市街地に人がいないと嘆くけれど、古い建物を貸すことはしない。そういう物件を扱う不動産業者もいない。古い建物に住みたいというニーズは絶対にあると思うので、応えるシステムを作りたい」という。それは「長野面影不動産」と名付けられた今後のHACILAの取り組みだ。
大学で学び、その学びを元に学外に出ることで、さらに深まる。「町の人たちと直に触れ合えたというのが本当に嬉しかった。信大だから、長野だからできることをしたい。未熟さを隠さず、未熟だから出来ることをやっていきたい」と語る彼らは、とても頼もしく見えた。
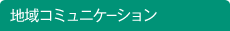
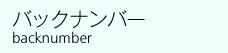
 教育学部発!地域志向研究
教育学部発!地域志向研究[ブナの実活用プロジェクト]ブナプロ!
 防災・減災 機能の強化を考える
防災・減災 機能の強化を考える平成26年度信州大学地域連携フォーラム
 ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり
ふるさと信州の祭再発見 映像で学び再評価する霜月まつり信州大学×日本ケーブルテレビ連盟 信越支部長野県協議会 連携協定
第3回連携 フォーラム
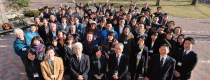 信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ
信州アカデミア 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ 全コース合同成果報告会+修了式
 信州大学COC「信州アカデミア」
信州大学COC「信州アカデミア」 地域戦略プロフェッショナル・ゼミ開講!