


環境省の「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」が来年1月より、全国15ヵ所でスタートする。
唯一の内陸地域の調査エリアとして長野県上伊那地域と山梨県内2地域が選定され、山梨大学医学部と本学医学部が連携し、地元自治体、医師会、教育関係団体と協力して調査を開始する。
本学で調査の先頭に立つ医学部野見山哲生教授に、調査の概要と信大が果たすべき役割を聞いた。
・・・・・ 信州大学広報誌「信大NOW」第66号より
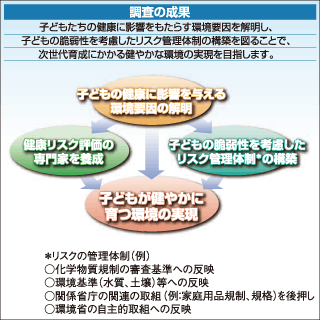
Japan Environment & Children's Study -略して「エコチル調査」。
子どもの健康に影響を与える環境リスクを、都市と農漁村、海沿いと山間部、寒冷地と温暖地など、全国15ヵ所の地域で、総計10万組の子ども(新生児)とその親を対象に調査する。妊娠中の母親と父親に協力を仰ぎ、3年間にわたり調査対象者を募り、子どもが13歳になるまで調査する。主として親からの採血・採尿検査や、生活条件、子どもについての質問票調査を継続する壮大な疫学調査だ。
本学医学部が担当する上伊那地域では、伊那中央病院と駒ケ根高原レディスクリニックで出産を予定し、同地域の産科のある病院・医院に通院される方を対象に、年間904組、3年間の募集期間合計で2712組に協力していただく予定だ。
調査の目的について「子どもに増加している病気があります。それらと、特に環境中の化学物質との関連を解明することです」と野見山教授は話す。
小児アレルギーやアトピー、ぜん息などの免疫系の疾患を持つ子どもが急増している。ダウン症や水頭症などの先天異常の発生頻度も上昇している。小児肥満や小児糖尿病などの代謝・内分泌系異常、自閉症や切れやすい子・LD(学習障害)・ADHD(注意欠陥・多動性障害)などの精神神経発達障害、男児の出生率低下などの生殖異常。こうした子どもの健康に関する原因不明で看過できない傾向を、胎児期から小児期における化学物質の影響との関連を調査し、解明しようというわけだ。

「なにより調査に応えてくださる親子、そして地元の自治体、医師会、教育界など広範な協力なしにはできない重要な調査です」と野見山教授。
扱うテーマは子どもの成長に関わるデリケートな問題であり、個人情報の厳重な管理なども不可欠だ。13年間にわたり調査を継続することは、調査される側も、また調査する側も、少なからぬ負担になるものでもある。
だが、「現在、誰もがおかしいと思い始めている子どもの病気や不健康増加の原因を究明することは急務であり、明日の子どもたちの健康を保証し、健やかな社会を作ることにつながるのです」と調査の重要性を指摘する。
まず広範囲に調べ、統計学的に分析し、個々の疾病や症状の原因究明への道筋をつける。「それが『次世代への贈り物』になるのです。ぜひ、多くの皆さんのご協力をお願いしたい」と力を込める。

医学部を先頭にして信大が果たすべき役割は大きい。なにより対象地域である上伊那での調査を、正確に、かつ着実に進めるために、関係する諸機関・諸団体との連携を強めるカギを握る。調査に協力してくれる親子に対して、丁寧に説明し、同意(インフォームドコンセント)を頂くことが重要だ。その基本的方向性を示すのは信大医学部の役割であり、責任は重大だ。
それだけではない。調査結果がある程度蓄積されてくると、その時点で、特定の問題について、医学・医療的に、また教育的に対応する必要が迫られることも予想される。
身体や知的な障害や発達障害の子どもを治療し、育成していく『療育』を今以上に充実していくことが重要であると思います」と野見山教授は言う。小児医学、発達心理学、臨床心理学などの知見や研究成果を現場に活かしていくことが求められる。
長野県も健康長寿課において「療育」に更に力を入れはじめているが、この動きや地域とも連携・共同して、地域の子ども、親にとって役立つような充実した制度・体制を作り出していく必要があるという。そのための、人材育成も重要だと指摘する。
いよいよ、エコチル調査に協力してくれる親子の募集がはじまる。「県民の皆さんの、医療面での信大・信大病院に対する大きな信頼と期待に応えられるよう、最大限の努力でエコチル調査を進めて行きたいと思います」。野見山教授は最後をこう締めくくった
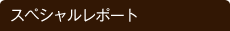
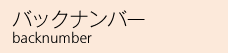
 信大には、独創力を育む環境がある。
信大には、独創力を育む環境がある。信州大学伝統対談 Vol.2 濱田州博学長×スタジオジブリ 宮崎吾朗さん
 どくとるマンボウと信大生のDNA
どくとるマンボウと信大生のDNA信州大学特別対談 山沢清人学長×エッセイスト齋藤由香さん
 信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力
信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力北海道から九州まで、全国へ栽培拡大!
 信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム
信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム理念と信念を持って行動 経営者に聴く、起業の心構え
 CITI Japanプロジェクト
CITI Japanプロジェクト研究倫理教育責任者・関係者連絡会議