

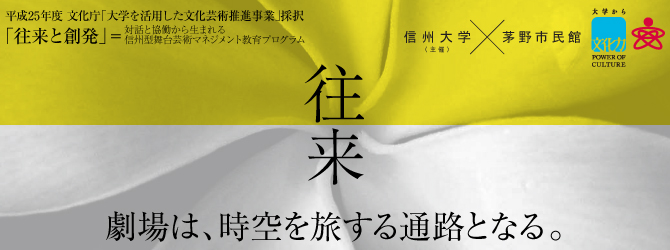
「往来と創発=対話と協働から生まれる信州型舞台芸術マネジメント教育プログラム」は、文化芸術施設の制作・技術スタッフや民間団体を対象とし、大学の持つ資源、人材のネットワークを活用しながら、企画・制作、広報、施設設備、運営技術の向上を図り、地域の個性を活かした高度な専門性を有する「舞台芸術マネジメント(文化芸術経営)」人材の育成を目的とした事業だ。舞台は、茅野市民館(長野県茅野市)。「映像」「音楽」「ダンス」の3部門を設け、様々なワークショップや情報提供を行いながら大学と市民館の両者が協働で作品を制作、それを4回に亘り広く一般に公開していく。
本事業は、平成25年度文化庁「大学を活用した文化芸術推進事業」に採択された事業だ。実施期間は平成25年7月1日~平成26年3月31日。
劇場運営を支えるスタッフと大学が協働して作品を制作していくという実験的な試みであると共に、そのプロセスを一般にも公開しながら、「地方都市」における新たな「舞台芸術マネジメント」の在り方を追求した本事業を紹介する。
「往来と創発」では、いわゆる「本番」を「見えるかたち」、その裏側のプロセスである創作過程や準備、打ち合わせの部分を「見えない力」として位置づけている。本プログラムのカリキュラムが、「実践演習プログラム」と「基礎演習講座」に分かれているのはそのためだ。
「実践演習プログラム」は「見えるかたち」(各イベントの実施、作品)のことであり、それを支える「基礎演習講座」が「見えない力」(打合せ、準備)の部分。「基礎演習講座」の中で、大学が持つ資源を共有しながら、より実験的な作品づくりを行い、「実践演習プログラム」で一般に公開、スタッフの経験知と応用力を養っていくことを目的としている。また、本プログラムは、教える側と教えられる側という、二極化された関係性ではなく、協働事業として展開することに主軸を置いていることも特徴的だ。
今年度の「実践演習プログラム」は全4回。映像部門では2013年9月22日(日)に「老いの時空」、12月8日(日)に「バリの光と影」と題した映像上映とレクチャーを行った。音楽部門では2013年11月22日(金)にマルチメディア音楽コンサート「Anabiosis Passage-蘇生路」を開催した。ダンス部門では2013年12月25日(水)にマルチメディアダンスパフォーマンス「Emotional Strata-記憶の往来」を開催し、観客を魅了した。
「基礎演習講座」は、ひとつの「実践演習プログラム」に対して2~3回実施している。茅野市民館のスタッフを中心に10名前後が参加し、外部講師と共にワークショップや情報交換を行いながら、作品づくりが進められていく。「基礎演習講座」は一般にも公開しており、市民の皆さんには完成品だけでなく、それに至るプロセスにも触れて貰う。
信州大学からは、北村明子准教授をはじめ、認知心理学などを専門とする高瀬弘樹准教授、広報・ドキュメンタリー指導として美学美術史学を専門とする金井直准教授、産学官連携推進本部より鳥山香織助教がプロジェクトメンバーとして加わっている。そして、外部講師として、「映像」「音楽」「ダンス」の分野から多彩な専門家やアーティストが多数参画し、様々な分野からの示唆が与えられる。
 金井 直 准教授 専門はイタリア美術史および近現代美術批評・キュレーション。1996年京都大学大学院文学研究科博士後期課程修了。1999年同大学にて博士号取得。豊田市美術館学芸員を経て、2007年より現職。 |
 高瀬 弘樹 准教授 専門は身体心理学、生態心理学および認知心理学。2002年早稲田大学大学院人間科学研究科博士後期課程単位取得満期退学。2003年同大学にて博士(人間科学)取得。早稲田大学助手、東京電機大学COE助手を経て、2008年より現職。 |

鳥山 香織 助教 専門は建築計画、産学官連携、地域連携まちづくり。2011年八戸工業大学大学院工学研究科博士後期課程修了。同年博士(工学)取得。建築設計事務所を経て、2012年より、リサーチ・アドミニストレータ就任。 |

北村 明子 准教授
専門は舞台芸術論、舞踊演出論、身体表現。1998年早稲田大学文学研究科修士課程修了。2001年より現職。振付家・ダンサー。バレエ、ストリートダンスを経て早稲田大学入学後、ダンス・カンパニーLeni-Basso結成。2010年からソロ活動を開始。コンテンポラリー・ダンスを中心とするパフォーマンス論を研究する。
企画・総合プロデュースを行う北村明子准教授は、茅野市民館を「挑戦的で様々なものにオープンな劇場」だと評する。
茅野市民館の開館は2005年。もともと、中心市街地活性化事業の中心プロジェクトとして建設が計画された施設だ。また、計画段階から市民が直接参加し、数多くのワークショップを繰り返しながら開館に至ったという経緯を持つことも特徴的だ。市民との関わりが強く、当初から地域に開かれた文化芸術施設としての役割に重きを置いており、地方都市における施設の在り方に対して高い意識を持っていた。
そうした経緯、特徴を踏まえ「大学側から提案することで挑戦的な取組みが出来る場として思い浮かんだのが茅野市民館だった」と北村准教授。
また、市民館が建つ諏訪エリアでこの事業を行うのには、もうひとつ理由がある。日本三大奇祭として数えられる「御柱祭」を始めとして、諏訪エリアには祝祭・儀礼文化が数多く残る。舞台芸術はもともと祭礼的な要素に深く関わるものが多い。「そうした共通項を地域の中に見出したことも、プログラムを進めていくに当って大きな要素でした」と北村准教授は語る。


ここで、平成25年12月8日(日)に行われた映像部門第2回実践演習プログラム「ドキュメンタリー映像上映とレクチャー」(講師:村尾静二氏)の様子を紹介する。
会場となった茅野市民館のアトリエには、壁伝いに小さなモニターがいくつも並べられ、正面のスクリーンにはバリの無形文化遺産「ワヤン・クリ」(影絵人形芝居)の映像が映し出されていた。その裏側に回ると今度は人形を操る「ダラン」と呼ばれる人が「ワヤン・クリ」を演じる姿が映し出され、そして、実際に使われる色鮮やかに着色された実物の人形が1体飾られていた。
この空間は、人は「影」によって神の世界を垣間見ており「影」の裏側に神々の世界が広がっている、という「ワヤン・クリ」の世界観を再現したものだと、この後の講演で知ることになる。小さなモニターには、ダランの日常、ワヤン・クリの上演風景など、バリにおける文化と人々の暮らしが、ほぼ無編集の「アーカイブズ」映像として映し出されていた。
「バリの光と影」と題されたこのプログラムは、世間に溢れる「映像」の意味をもう一度見つめ直し、娯楽としてではなく、文化継承のための「アーカイブズ」としての役割を参加者に考えてもらうことが目的だ。バリの文化・社会背景、そして人々の暮らしについてのレクチャーと共に、アーカイブズとしての映像制作、編集といったプロセスを文化人類学・映像人類学の視点から学んだ。
「成果にはプロセスがあります。映像の多くは編集されたもの。しかし、それとは無関係の膨大な時間が現地で流れているということを感じて貰いたい」(村尾静二氏)。
完成品の裏側に流れる膨大な時間は、「映像」だけでなく「音楽」「ダンス」、また芸術、文化、すべての領域に共通する。


本プログラムは、「ダンス」「音楽」「映像」という3部門を設けることで、それぞれの分野における多様な視点を捉えながら、舞台芸術の新たな可能性を探るという目的も持っている。
「音楽」部門では、サウンドデザインの領域で、ステージ全体を使った演出を行うことで、音という素材を楽しむ新しいコンサートの形を提供した。
「ダンス」部門では、信州大学人文学部芸術ワークショップゼミの学生とアーティストらが共にワークショップを繰り返しながら、独自の演出によるダンスパフォーマンスを模索した。
そして、市民館スタッフは、制作過程そのものに関わりながら、様々な要素を持った作品をいかに人々に見せ、提供していくかのプロセスを経験することで、新たな舞台芸術の可能性を見出すきっかけを与えられたことになる。市民らはそうしたプロセスに触れつつ、市民館における新たな芸術文化の「往来」を楽しむ。
市民館スタッフの河西誠さんは、「芸術作品の意味を理解し、活用していくためのヒントを毎回与えられている。大学を通じた出会いと刺激がこれからの事業の発展に繋がっていく実感がある」と話す。
この実験的な試みは、新しい「信州型舞台芸術マネジメント」の在り方をつくり、人からまちへの「往来」を生み出し、地域文化の継承と創造を担う文化芸術施設のモデルケースを提示していく活動でもある。それが徐々に形作られていけば、次世代へ続く、時空を超えた文化の「往来」が実現していくことになるだろう。
「往来と創発」の主軸は、協働にあると思っています。信州大学とのプロジェクトは、地方都市における地域文化の継承と創造へ繋がるもの。アカデミックな世界と協働することで、「地域文化の確立」が確かなものになります。この「地域文化の確立」は、茅野市民館の初心の目的でもありました。
また、私たちは文化芸術施設という現場の世界に、ただただ集中してしまうことが多々あります。茅野市民館がこの事業に参加する上での受益は、実践のプロダクションを論理的に学ぶことが出来る点にあると思っています。この事業により、教育というネットワークに広がりを持たせることが出来たことも、今後の事業に繋がる広い視野を与えてくれています。
また逆に、信州大学としての受益は、現場の力や声がそのままフィードバックされることにあるのではないでしょうか。
市民館、大学、市民が協働してこの事業を進めることで、新しい地域文化の継承と創造へ繋がっていくと感じています。
映像 |
音楽 |
ダンス |
||
 |
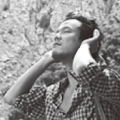 |
 |
 |
 |
| 村尾静二 | 森永泰弘 | Endah Laras | 金井圭介 | 兼古昭彦 |
| Seiji Murao | Yasuhiro Morinaga | エンダ・ララス | Keisuke Kanai | Akihiko Kaneko |
早稲田大学大学院で映画学を専攻後、国立民族学博物館で映像人類学を研究し、この分野で日本最初の学位を取得する(文学博士)。また、近年では、国立天文台ハワイ観測所や国立極地研究所において、映像アーカイブズの構築に向けた制作活動を展開する。 |
サウンドデザイナー、サウンドアーキビスト、ミュージックコンクレート作曲家。東京藝術大学大学院映像研究科博士課程を単位取得満期退学ご、映画理論家/ミュージックコンクレート作曲家のミシェル・シオンに師事。近年はマレーシアやインドネシア、イタリア南部でフィールドワークを行っている。 |
1976年インドネシア中央ジャワのソロに生まれる。ワヤン・クリの影絵師である父親の影響もあり、幼少時から芸術世界に親しむ。1996年、プロの歌手として活動をはじめ、レコーディング活動も積極的に行い、その豊かで魅力的な歌声で、芸術領域の境界線を越えて活動し、その芸術性を洗練させている。 |
2002年、フランス国立サーカス大学(CNAC)を卒業し、フィリップ・デュクフレ演出のサーカス「CYRK13」に出演。2009年に帰国後は4人組のサーカスパフォーマンス「くるくるシルクDX」のメンバーとしてヨーロッパ、アジアなど各国のフェスティバルに招待参加。現在、松本市在住。 |
東京藝術大学大学院美術研究科絵画(版画)専攻修士課程修了。98年より北村明子主宰コンテンポラリー・ダンスカンパニーLeni-Bassoの映像制作・演出を手掛ける。舞台作品への映像制作とともに、ギャラリー空間でのインスタレーション作品を多数発表している。東京家政大学造形表現学科准教授。 |
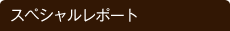
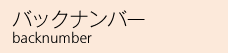
 信大には、独創力を育む環境がある。
信大には、独創力を育む環境がある。信州大学伝統対談 Vol.2 濱田州博学長×スタジオジブリ 宮崎吾朗さん
 どくとるマンボウと信大生のDNA
どくとるマンボウと信大生のDNA信州大学特別対談 山沢清人学長×エッセイスト齋藤由香さん
 信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力
信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力北海道から九州まで、全国へ栽培拡大!
 信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム
信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム理念と信念を持って行動 経営者に聴く、起業の心構え
 CITI Japanプロジェクト
CITI Japanプロジェクト研究倫理教育責任者・関係者連絡会議