


平成27年3月6日(金)、上智大学四谷キャンパスで「CITI Japanプロジェクト 研究倫理教育責任者・関係者連絡会議」が開催された。連絡会議の前に開かれた外部評価委員会では、プロジェクトを担う6大学が集まり、今年度のプロジェクト事業報告と外部評価委員による事業評価が行われた。その後の関係者連絡会では、全国から参加した233大学・約630名が来賓の講演やグループディスカッションの場を通じて、倫理教育の現場が抱える課題や対策を共有した。

「研究倫理教育責任者・関係者連絡会議」に先駆け、CITI Japanプロジェクトを推進する信州大学を中心とした、主要6大学による第4回外部評価委員会が開催された。本会儀には、より質の高い日本独自のCITIプログラム作成のために、外部評価委員として、CITIプログラムディレクターでマイアミ大学のセルジオ・リフテカ教授と、来賓として、韓国カトリック大学生命倫理学・Byung-in Choe教授をお招きした。外部評価委員長には早稲田大学・土田友章教授が選出され、会議が始まった。
まず始めに、CITI Japanプロジェクト副統括をつとめる信州大学・市川家國特任教授が平成26年度のCITI Japanプログラムの事業について、「CITIの受講登録者数は当初の予定をはるかに上回り、2014年12月末で4万人に達し、来年度には12万人を越える勢い。受講者のアンケートでは、CITIのような倫理教育の義務化に賛成の声が多数あったこともうれしい」とこれまでを振り返り、今後も教材作成において外部の専門家やユーザーと連携し、日本の文化やシステムに合致した独自の研究倫理教育を築いていく大切さを伝えた。
つづいて、外部評価委員のセルジオ・リフテカ教授、Byung-in Choe教授よりそれぞれの見解が示された。リフテカ教授は、「研究倫理の規制そのものを教えるだけでは不十分」という視点から、道徳的な基本を盛り込まないことには研究倫理の規則を遵守すること自体ができないこと、その上で柔軟性をもって日本のニーズに見合った倫理教育モデルを構築していく必要性を示された。「そのために、外部評価委員として今後もできる限りのサポートをしたい」とリフテカ教授。同様に、Choe教授からも「官庁が先導するのではなく、大学などの研究機関が研究倫理プログラムをリードし、様々な価値観を取リ入れた教材を作成することが重要」と、韓国の事例をご紹介いただいた。
大学間連携共同教育推進事業を進める、文部科学省・高等教育局大学振興課の堀之内氏からは、「CITI Japanプロジェクトは他省庁からも期待を寄せられている活動である。世界標準の研究者を輩出する教材づくりに引き続き協力していきたい」とコメントをいただいた。
外部評価委員長の土田教授は「研究倫理は社会と密接に関係し、我々の生活の中にある。CITI Japanの教材は日本の倫理観、行動様式に見合うものにしなければ成功しない」と委員会の総評を述べられた。
最後にプロジェクト事業統括をつとめる信州大学医学部・福嶋義光教授は「CITI Japanプログラムの普及は順調に進んでいる。教材の作成・改訂とともに、残りの2年間の事業計画の中で、CITI Japanを継続的に運営できるような法人化についても、しっかりと準備をしなければならない」と来年度への意気込みを伝え、委員会を閉会した。
「研究倫理責任者・関係者連絡会議」は全国から233大学・約630名が参加。
会議は上智大学・早下隆士学長の開会の挨拶から始まり「昨今、大学などの研究機関における不祥事が頻繁に報道されている。このような時期にCITI Japanプロジェクトが文部科学省によって採択され、活動していることは大変意義深い」と話された。
会議の主旨について、CITI Japanプロジェクト事業統括・福嶋義光教授は「今までの研究倫理教育の普及や充実は国からのトップダウンだった。これからは研究倫理に携わる現場の一人一人が考え、ボトムアップで研究倫理教育を発信していかなければならない。また、今回初めて行うグループディスカッションのような場づくりが大切。参加者の専門分野や立場、地域をシャッフルしたグループをつくり、ディスカッションすることで研究者への教育普及のアイデアや現場の苦労などを知るきっかけにしたい」と述べ、研究者自らが学習のモチベーションを保てるような質の高い教材や勉強会を提供していくことを伝えた。。
来賓挨拶では文部科学省人材政策推進室室長補佐・沼田勉氏、(独)日本学術振興会理事・浅島誠氏、(独)科学技術振興機構総括担当理事・大竹暁氏からご挨拶をいただいた。
沼田氏は2014年8月に決定した不正行為対応の新ガイドラインの実施を基にした環境整備に触れるとともに、「実効性の高い倫理教育実施のため、これまで明らかになった課題や対策を共有し、今後の取り組みとしてCITI Japanプログラムの開発を支援していきたい」と語られました。
浅島氏は「科学の健全な発展のために、日本学術振興会の教材とCITI Japanの教材とは両輪のように発展させていきたい」と述べられ、大竹氏も「科学研究は公共財になっているので、社会の信用を得なければ研究をすることはできない」と、研究倫理教育の重要性を説かれました。。
講演では3名の先生方から研究倫理教育の取組例を紹介していただいた。
東京医科歯科大学産学連携研究センター長・飯田香緒里教授は「利益相反マネジメント体制と課題」について「産学連携無しに研究が成り立たない現在、研究成果を社会に生かすことが必要。研究の社会的信頼を守るために、外部との経済的な利益関係に不正があってはならない」と語られ、研究倫理教育と利益相反マネジメントを一緒に行うことで、不正行為の抑制力も高まると強調された。。
続いて、筑波大学生命領域学際教育センター講師・岡林浩嗣氏は筑波大学大学院で2008年から行われている「研究倫理」の授業を紹介し、「研究倫理と一言で言っても、研究分野は多岐に渡っている。また、分野により考え方やルールが違うなど、様々な要素が絡み合っているために、研究倫理を“教育”することは難しい。しかし、科学者としての教育を受ける初期段階から研究倫理について意識することが必要で、研究倫理に関するインプット・アウトプットのトレーニングを通じて研究倫理に対する“感覚”を磨くことが大切。それと同様に指導者にあたる研究者が研究倫理を学ぶことも必須である」と説明。。
最後に「研究データを正確に扱う方法」について、京都大学大学院生命科学研究科・上村匡教授は、「ケーススタディを基に具体的事例を挙げ、研究データの画像処理や統計について、学生が実践の場で利用出来る内容を学ぶことが重要。これは研究者だけの問題ではなく、データを扱う場合には共通のコンプライアンスである事も意識付けなければならない」と述べられた。
指定発言として、韓国カトリック大学生命倫理学・Byung-in Choe教授からは、韓国の倫理教育の現状が伝えられ、「単なるシステムや教材として倫理教育を履修するだけでなく、倫理教育をなぜ必要とするのかという、研究の社会的責任を研究者自身が考えなければならない」と研究者が倫理教育そのものを捉えなおす必要性を説かれた。。
会議の終盤、参加した約630名が15のグループに分かれ、「研究者に研究倫理教育を考えてもらう有効なアイデア」や「大学や研究機関が直面している問題」など様々な議題についてのディスカッションを行った。。
その中の1つのグループでは、
「倫理教育の必要性は重々承知しているが、それを教える人材が不足している」
「倫理とは、人間の根源の在り方であり、大学教育だけで解決できるのか」
「現在は無償だが、有償になったときに大学側がコストを負担できるか」
「倫理教育委員会を学内でどのように組織化できるか」
など、倫理教育について、現状抱えている問題や今後の要望を共有した。
ディスカッションでの意見や要望はCITI Japanプロジェクトにフィードバックされ、今後の教材開発に活用される。
初めての試みであったグループディスカッションは活発な意見が飛び交い、今回の連絡会議は幕を閉じた。
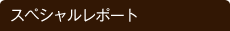
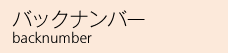
 信大には、独創力を育む環境がある。
信大には、独創力を育む環境がある。信州大学伝統対談 Vol.2 濱田州博学長×スタジオジブリ 宮崎吾朗さん
 どくとるマンボウと信大生のDNA
どくとるマンボウと信大生のDNA信州大学特別対談 山沢清人学長×エッセイスト齋藤由香さん
 信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力
信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力北海道から九州まで、全国へ栽培拡大!
 信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム
信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム理念と信念を持って行動 経営者に聴く、起業の心構え
 CITI Japanプロジェクト
CITI Japanプロジェクト研究倫理教育責任者・関係者連絡会議