

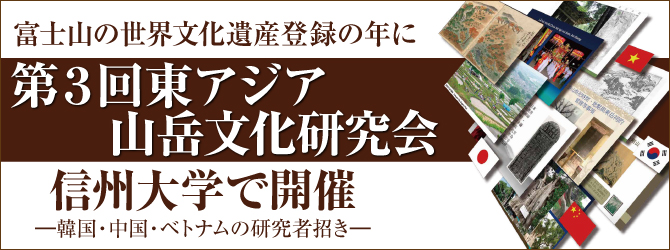
富士山がユネスコの世界文化遺産に登録されることが決まった記念すべき本年、山岳文化研究を進める中国・韓国・ベトナム・日本から研究者が集い、現状報告と意見交換を行う東アジア山岳文化研究会が、信州大学山岳科学総合研究所の主催で開催されました。6月1日には信大松本キャンパスでシンポジウム、2日は富士山の周辺で現地見学会が行われました。
韓国からは、韓国のシンボル・智異山の文化などを研究する慶尚大学校慶南文化研究院の張源哲院長らが参加。中国からは、ユネスコの世界遺産・泰山のすぐ近くにある泰山大学の周郢副教授らが、また、ベトナムからはベトナム社会科学院所属宗教研究院のグエン・クオック・トウアン院長らが参加し、山岳に対して畏敬の念を抱く東アジアの精神文化の共通性をふまえつつ、各国の山岳生活・山岳文化の特徴を論じ合いました。

欧米では、山岳は、スポーツ登山の対象、つまり人間が征服する対象として捉えられているのが常のようですが、それとは異なり、東アジアでは、山岳は畏敬の念を持って接する聖地として、宗教的・文化的象徴として捉えられています。東アジアに共通する傾向だと聞きます。
そうした山岳に関する精神的風土を踏まえて、東アジアにおける山村の文化や生活のあり方を探ることが、現代の人間社会の進路を考える上で重要になっています。このテーマについて信州大学では山岳科学総合研究所を中心にして、学問の領域を超える文理融合の視点で考察を進めています。今回の研究会を通じて、東アジアの研究者の皆さんと協働して、この研究をさらに深化させていきたいと思います。(開会の挨拶より要旨)

山岳地域は、陸上に残された貴重な自然資源であり、同時に、様々な負荷の影響を受けやすい脆弱な環境でもあります。高山から里地・里山までのこの環境系は、マクロの自然変動の影響はもとより人類の進化に伴って、人間の生活系との相互作用によって大きく変動している地域なのです。
信州大学では、このような山岳環境の様々な要因による変化と人間の営みとの関係を総合的に探求する学問領域「山岳科学」を創造することを目指し、人文科学・社会科学・理学・工学・農学・医学などの研究者が、既存の学問領域を超え、共同して研究を進めています。2002年9月にバーチャルな研究所として発足。2006年7月に研究所として再編し今日に至っています。(研究所紹介より要旨)

平成23年の3.11東日本大震災―3.12長野県北部地震以後2年、食と水とエネルギーと情報の大切さが浮き彫りになっています。特に日本では、食とエネルギーの問題が緊急の課題です。
中山間地の農村集落は危機的状況に陥っていますが、その地に古くから継続されてきた農業や林業を基本とする山間集落の生業と暮らしのあり方を考察すると、そこから、現代の危機を克服する道しるべを引き出すことができます。米や麦だけでなくそれ以外の雑穀や木の実を食べてきた食文化や、山の木を薪として利用してきた自給的エネルギー循環などは、今日の世界に継承するべき営為だったのです。
山村の生業と暮らしは、祭祀や伝統儀式など山村の文化の土台であり、切り離せない一体のものなのです。だから、産業・生活・文化を多角的・一体的に考察することが重要です。それは、日本だけでなく東アジア全域の山間集落の未来を決するものだと思います。(研究会趣旨の説明より要旨)

長野県飯山市の小菅集落は、小菅山の麓、標高約500mに位置する山村です。中世は修験の霊場として栄え、現在も神仏習合の建築遺構や祭礼が伝えられています。一方、小菅集落は冬季には3mほどの雪が積もり、1年の3分の1の期間が雪に覆われる日本有数の豪雪地です。そのため、人々の暮らしを守ってきた民家には、豪雪地に育まれてきた独特の山村建築文化が色濃く伝えられています。
同地の伝統的民家の建物を調査してみると、建物の縦軸を構成する柱などにはスギが多く使われ、一方、横軸を構成する梁や扠首にはブナが多く使われています。建材としてはなじみの少ないブナが多く使用されているのは、ブナが豪雪地域でも成長しやすかったため、里山林に多く植えられたからだと推測されます。
また、この地の伝統的民家には雪を溶かすための「タネ」と呼ばれる小さな池が建物周辺に設けられますが、このタネの水源は里山林(さとやまりん)であり、この点でも人々の暮らしと里山林の関係が良く見て取れます。(講演要旨)

日本の山間地域では、中小河川やため池を利用して水利システムを発達させ、小規模な棚田を中心とした農地を拓くことで、特徴ある文化が蓄積・形成されてきました。棚田は、山村の重要な生活・生産基盤の一つです。山村の人々は、棚田を中心にして、森林に包括される豊富な自然資源を活用し、資源循環型生活スタイルを構築してきました。
しかし、こうした山間集落は、いわゆる近代資本主義経済による国家の高度成長過程において、急速な人口減少に直面し、現在では、高齢化と耕作放棄、森林荒廃が急速に進んでいます。
こうした中、棚田をはじめ過去に築かれた文化形態を再度見直し、そこから学ぶ「文化的景観」の考えが注目を集めています。この考えは重要ですが、単に過去への郷愁や文化理解にとどまらず、農業技術や水利のシステム、それを運用する人々の相互信頼関係とそれを基礎とした地域共同体のあり方にまで掘り下げて考えることが必要です。社会に新たなパラダイムを提示してこそ意味があると思います。(講演要旨)

富士山は、「万葉集」の時代から、多くの文人によって扱われています。その中で、特に、「漢詩」という、日本にとっては外来文学のジャンルに注目してみます。
中国では、古くから名山を崇拝する伝統があり、その結果、山水詩のような山を題材にした漢詩文学が生まれました。この漢詩の形式が日本に持ち込まれると、日本でも、富士山を、日本を代表する叙景的題材のひとつとして扱う漢詩が、禅宗の僧侶を中心にした「五山文学」などで現れ、江戸時代になると林羅山や石川丈山などが「三国第一山」として富士山を讃えるようになりました。
一方、韓国と日本は、豊臣秀吉の朝鮮侵攻があったものの外交関係が回復。朝鮮通信使が日本を訪れるようになると、彼らも富士山を漢詩に詠むようになりました。その内容は、富士山と朝鮮の金剛山との優劣を争うようなモノであり、最初は単純な競争心や対決意識だったのでしょうが、次第に文化的交流が進むと、両国相互の国土景観に対する具体的な自覚の高揚へとつながって行く大きなきっかけになったと言えます。(講演要旨)

中国の名峰・泰山は、古くから神聖な山として多くの人々の信仰の対象になってきました。記録によれば西暦665年に日本から来た使節も泰山に登っていますから、その時代に既に広く東アジア全域に、泰山への信仰が広がっていたことがうかがい知れます。
泰山の頂上にある石敢當(いしがんとう)と同趣旨の石碑は、沖縄県や鹿児島県を中心に、秋田県や青森県まで日本全国に建立されており、中国と日本との長い交流の中で精神的・宗教的な共通性が育まれてきていることが感じられます。
しかし、泰山の社会的位置づけは時代の流れとともに変遷しています。秦や漢の時代が「政治山」、魏から南北朝時代が「宗教山」、唐や宋の時代が「文化山」、明や清の時代が「民
俗山」で、中華民国以降が「精神山」―とする泰山歴史文化五期説があります。特に「文化山」期には、李白や杜甫が歌に詠み、歴史学などの対象になり、儒教など思想的にも重要な位置付けが与えられるなど、今日の泰山の文化的位置を確立することにとって大きな貢献がありました。(講演要旨)

現在のベトナムには、山岳文化に関わる伝統的祭礼が数多く継承されています。
バーヴィー(傘円)山の神の祭は、ベトナムで「四不死」と呼ばれる4人の不死の神の1人を祭るもので、治水、豊穣、暖衣飽食を祈念します。神を神輿に乗せて祠を渡るなどの荘厳な儀式があり、その後に、綱引きや、弩(おおゆみ)による射撃競技、棒倒しなどの独特で賑やかな民間伝統遊戯が行われます。
その他にも、バーデン(黒婆)山の祭礼、サーム(讖)山バーチユアスー(主処婆)生誕日の祭礼、クメール民族の伝統行事であるバイー山耕牛競争の祭礼、西部高原の水牛供養などが有名です。特に、バイー山の耕牛競争は、人々の農業生産とその文化に密着したものであり、ベトナムの伝統的祭礼が山村の人々の暮らしと共にあるという根本的性格を如実に物語っています。
ベトナムの伝統的祭礼の要素は、山の姿の美しさと山岳の霊気への称賛、農林業作業の模写で・反映、自然との和合などです。日本・韓国・中国にも共通するものであり、ぜひ、共同で研究しましょう。来年はベトナムで研究会を開きましょう。(講演要旨)
2日目には、「富士山とその文化」の現地見学会が行なわれました。
現地見学会では、まず山梨県立博物館にて葛飾北斎「富嶽三十六景」の数点を特別に見学させて頂きました。最も有名な神奈川沖浪裏(かながわおきなみうら)を始め、凱風快晴(がいふうかいせい)、山下百雨(さんかはくう)、諸人登山(もろびとはくざん)の4点を観覧し、皆さんその見事さに見入っていました。
博物館の見学を終え、富士吉田市内へと移動。笛吹市と富士河口湖町を繋ぐ新御坂トンネルを抜けると、富士山が姿を現し、車内は大きな歓声に包まれました。笹本教授も「これだけ綺麗に見えるのは珍しい」と語っていました。
富士吉田市内では、御師(おし)宿坊「旧外川(とがわ)家住宅」を見学しました。この御師というのは、富士山へ信仰登山する人々に自らの住宅を宿坊として提供し、登山の世話を行なってきた人たちのことです。更に、祈祷によって寺院や神社に参詣する人々と神仏の仲立ちをする宗教者でもあったと言います。
現地見学会の最後には、北口本宮冨士浅間(せんげん)神社を訪れました。両側に美しい杉並木が立ち並ぶ長い参道を歩いていくと、富士登山の玄関口が現れます。
グエン・クオック・トウアン院長は「とても素晴らしい体験だった。信州大学の先生方も周到な準備をしてくれており、とてもありがたかった。この素晴らしい大学で是非ベトナムの留学生を受け入れていって欲しい」と語って下さいました。
梅雨の晴れ間に恵まれた現地見学会は、富士山の歴史、食、文化、そして富士山そのもの出会うことが出来、素晴らしい会となりました。
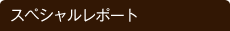
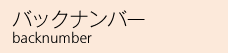
 信大には、独創力を育む環境がある。
信大には、独創力を育む環境がある。信州大学伝統対談 Vol.2 濱田州博学長×スタジオジブリ 宮崎吾朗さん
 どくとるマンボウと信大生のDNA
どくとるマンボウと信大生のDNA信州大学特別対談 山沢清人学長×エッセイスト齋藤由香さん
 信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力
信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力北海道から九州まで、全国へ栽培拡大!
 信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム
信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム理念と信念を持って行動 経営者に聴く、起業の心構え
 CITI Japanプロジェクト
CITI Japanプロジェクト研究倫理教育責任者・関係者連絡会議