


「省エネ」が差し迫った課題としてクローズアップされた2011年。(独)新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)から研究開発委託され、工学部・藤縄克之教授が清水建設(株)とともに2010年から取り組んできた「地下水制御型高効率ヒートポンプ空調システム」の実証実験プラントが、工学部キャンパスに完成。11月15日(火)午前、信州科学技術総合振興センター(SASTec)で記者会見・設備見学会が行われた。また、午後には地下熱利用などをテーマに記念特別講演会が開催された。
・・・・・信州大学広報誌「信大NOW」第72号(2011.11.30発行)より


このシステムは、年間を通じて温度がほぼ一定(約14℃)の地下水を、冬は暖房用、夏は冷房用の熱源水として利用する。具体的には暖房・冷房に供する二層の帯水層を使い、冬は暖房用の帯水層から取水し、水温が下がった水を冷房用の帯水層に、夏は冷房用の帯水層から取水して、水温が上がった地下水を暖房用の帯水層に戻す。半年後には冷暖それぞれ理想温度の地下水を利用できるよう地下水の流量を制御する世界初のシステムである。ヒートポンプの省エネ効果を最大限に高めるものと期待され、取水による地盤沈下の心配もほとんどないなど、環境への負荷が少ないことも特徴だ。
また、本委託事業で新たに開発した水冷式ヒートポンプは、地下水温度が冷房用の水温より低い期間は、地下水を直接空調の熱源として使用する「フリークーリング」を実現でき、水温によって最も効率的な運転モードを自動的に選択して省エネを図る。
今後は工学部講義棟の2教室で冬季実証運転(暖房運転)、夏季実証運転(冷房運転)を実施し、2013年2月まで従来タイプのビルマルチ式空調システムと比較しながら性能を実証していく。

記者会見では、最初に山沢清人学長が、信大のエコキャンパスづくりの展開を紹介しながら、「地下水が豊富な長野県からこの実証プラントの成果を伝えていきたい」と挨拶。続いてNEDO省エネルギー部長の佐藤嘉晃氏が、本システムの省エネ効果への期待を述べ、清水建設(株)技術研究所百田博宣氏が本プラントの概要を説明した。その後で質疑応答が行われたが、マスコミ各社からは、地下水利用や地層調査、クローズト方式との違い、環境への影響など活発な質問が出され、社会的関心の高さがうかがわれた。
記者会見に続いて、揚水井・注水井やヒートポンプ、空調に本システムを導入した教室、モニタリングシステムなどの設備見学会が行われた。実際に稼働している揚水井・注水井、ヒートポンプ、講義棟の廊下天上の配管やモニタリングシステムなどを見ながら、記者からは「井戸の深さは?」「地下水流の速度は?」など次々に質問が出され、藤縄教授らは一つひとつていねいに答えていた。記者会見、見学会は予定時間を1時間近くオーバーして続けられた。


午後2時からは、約100名の参加者を前に記念講演会が開催された。信大三浦義正理事・副学長が「地下熱利用をアピールするいい機会にしたい」と挨拶したのに続き、NEDOの佐藤部長が「NEDO次世代型ヒートポンプシステム事業について」講演した。佐藤部長は、震災以降、省エネと再生可能エネルギーが二つの大きな課題となっている。とくに家庭用・業務用ビルの冷暖房・給湯の需要が増えると予測され、産業・運輸・家庭及び業務の部門横断的な省エネ技術として、次世代型ヒートポンプが位置づけられると述べ、従来型より1.5倍以上の効率を実現することと、本システムの具体的目標を示した。
続いて「信州大学における地下熱利用ヒートポンプシステムについて」と題して事業概要を説明した藤縄教授も、2010年度からの取り組みや従来型ビルマルチ空調システムとの違い、クローズド方式、オープン方式の違いに触れながら、本システムでは1.5倍以上の高効率を目指す自信を示した。


特別講演では、NPO法人地下熱利用促進協会の笹田政克理事長が「東日本大震災と地下熱利用技術の普及について」講演した。笹田理事長は、地下熱は節電にもっとも効果のある再生可能エネルギーとして関心が高まり、市民2万人を対象として8月に行われたアンケートでは、太陽光発電に次ぐ2位となって関係者を驚かせた。すでに震災復興のプランのなかで地下熱を取り入れた案が検討されている。今後加速度的に地下熱利用が進むだろうと語った。
また、昨年は信大で客員教授として指導に当たった北海道大学大学院工学研究科の長野克則教授は、「地下熱利用技術の研究最前線について」講演。ヒートポンプユニットの開発と普及状況、クローズド型による地下熱の利用状況を紹介し、今後の普及のカギを握るのはコストであると語った。
続いて長野県環境部温暖化対策課の田中信一郎企画幹が「長野県における自然エネルギー利用の動向について」と題した講演のなかで、今後の課題はクリーン熱利用であり、長野県はその先進県になっていきたいと地下熱利用への期待を述べた。
最後に信大岡本正行工学部長が、信大全体で取り組んでいるグリーンイノベーションと、地下熱のエネルギー源としての質の高さを訴え、講演会を終えた。講演会全体を通じ、これまで自然エネルギーといえば、太陽光発電や風力発電など発電のためのエネルギー源が注目されることが多かったが、電気を介さず地下熱をより直接的に熱源として利用する方向に、多くの期待が集まっていることが確認された。
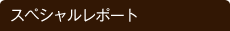
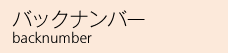
 信大には、独創力を育む環境がある。
信大には、独創力を育む環境がある。信州大学伝統対談 Vol.2 濱田州博学長×スタジオジブリ 宮崎吾朗さん
 どくとるマンボウと信大生のDNA
どくとるマンボウと信大生のDNA信州大学特別対談 山沢清人学長×エッセイスト齋藤由香さん
 信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力
信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力北海道から九州まで、全国へ栽培拡大!
 信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム
信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム理念と信念を持って行動 経営者に聴く、起業の心構え
 CITI Japanプロジェクト
CITI Japanプロジェクト研究倫理教育責任者・関係者連絡会議