

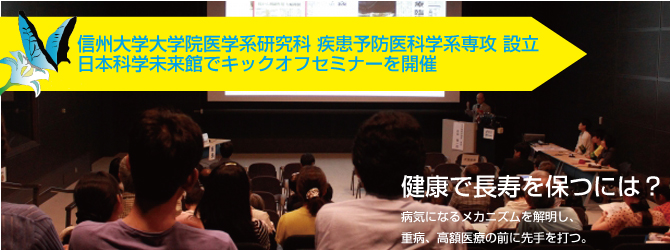
「健康で長寿」は、誰もが願うことであり、超高齢化社会の日本の願いでもある。高齢者が多くなればどうしても医療費は増えてしまうが、健康であったなら、医療費増加も抑えることができる。信州大学大学院医学系研究科では、生命科学の著しい発展とこれからの新しい医療に対応するために「予防医学」を超えた新しい枠組み「疾患予防医科学」を推進する「疾患予防医科学系専攻」を立ち上げた(平成24年4月)。7月28日(土)には、日本科学未来館で専攻の研究内容を紹介するキックオフセミナーを開催。およそ200名の参加者は、楽しくわかりやすい講演に聞き入った。

キックオフセミナーの前に、なぜ「疾患予防医科学専攻」ができたのかを専攻長の樋口京一教授に聞いた。その背景には、日本の医療の新しい流れ「先制医療」(*注1)がある。
健康診断の結果を受けて、気になる数字を見つけたことはないだろうか。たとえば血清中のGOTやGPTの数値が上がったりすると、肝機能の障害を疑う。こういった数値を示すものはバイオマーカーと呼ばれ、多くの製薬企業やバイオベンチャーによって、研究開発が盛んに行われている。
今や、病気の発症に関連した遺伝子の解明や、病気の兆候を細胞レベルで発見する方法で、まったく症状が現れない時期に診断できる疾患もある。つまり発症する前に治療をして発症を食い止めたり、遅らせたり、進行しないうちに治癒したりができる可能性があるということだ。そうした医療が実現すれば、症状が進んでしまった場合より個人の痛手は少ないし、医薬品も減る。高額医療も受けることは少なくなり、医療費は軽減するだろう。これが「先制医療」と呼ばれるもので、近い将来、「先制医療」は日本のスタンダード、当たり前の医療形態になるかもしれない。
専攻は、こうした時代の要請に応えるべく、これまでにあった加齢適応医科学系専攻と臓器移植細胞工学医科学系専攻を統合して設立され、「疾患予防医科学」を推進することとなった。「疾患予防医学」とは、「予防医学」にとどまらず、人体がいかに健康の状態を維持し、いかにして破綻するのかという、健康と病気のメカニズムを解明する「病態科学」を融合させたもので、「先制医療」の基盤ともなる。
樋口教授は「日本で最も長寿である長野県における研究であること。これまで以上に地域の人々と共に歩める専攻でありたい」という。
(*注1)先制医療:井村裕夫先端医療振興財団理事長が提唱した新しい医療システム


すっかり夏休みモードになった7月28日(土)、お台場にある日本科学未来館でキックオフセミナーが開催された。
日本科学未来館は、元宇宙飛行士の毛利衛館長のもと、さまざまな先端科学技術の展示・実演・イベントが行われている。ここには研究施設も備わっていて、直に科学者の話を聞くこともできる魅力ある施設だ。ここで「疾患予防医科学専攻」7講座の教授による一コマ30分の講演とポスター展示やデモンストレーションが行われた。
午前の部 「どうしてヒトは年をとるの?」(樋口京一教授)
「歩くだけで若返る!?」(能勢博教授)
午後の部 「善玉菌でがんの治療!」(谷口俊一郎教授)
「ネズミで探る遺伝子のヒミツ!」(新藤隆行教授)
「脳の話はおもしろい!」(鈴木龍雄教授)
「肝心要(かんじんかなめ)」(青山俊文教授)
「胃粘液でがんの予防!」(中山淳教授)
筆頭の講演は樋口教授の「どうしてヒトは年をとるの?」。
年を取って老いるのは当たり前、などと言っていたら話は進まない。老化現象のメカニズムを解明し、老化を引き起こしている原因をコントロールできればアンチエイジング(抗老化)は可能になる。
例えばマウスに食事のカロリー制限を設けると自由に摂取しているものに比べて明らかに長く生きる。こうしたカロリー制限によるメカニズムが世界的に研究されている。
あるいは、細胞のミトコンドリアにあるCoQ(コエンザイムQ: CoQ10)という物質が抗老化のカギを握ると注目されている。ミトコンドリアで生命活動のエネルギーの分子、ATP(アデノシン三リン酸)をつくるのに必要な物質だが、加齢と共に減少するため、つくられるATPも減少してしまう。さらにCoQは、強力な抗酸化物質で細胞の酸化を防ぐ効果もある。
CoQを投与すると肝臓などで加齢による機能の低下を抑えられたという実験結果もあり、確かな抗老化が期待できるが、そのメカニズムの詳細はわかっていない。
ほかにタンパク質を異常な構造に変えてしまう、アミロイドーシスという病気(総称で、アルツハイマー病もその一つ)のメカニズムや、運動による生活習慣病予防効果の個人差の決定要因(遺伝子)を探るなど、樋口教授の講座では多方面から抗老化に挑んでいる。
次は、能勢博教授による「歩くだけで若返る」。
松本市の熟年体育大学を中心に実施されている、インターバル速歩トレーニングについて解説した。インターバル速歩とは、早歩きとゆっくり歩きを交互にして歩く方法。20~30分を週に4、5日ほど歩く。これだけで5ヶ月以上続ければ、最大20%程度、体力がアップし、高血圧、高血糖、肥満などの改善もみられる。普通に長時間歩くだけでは、このような効果は期待できないという。
また、インターバル速歩のあとに乳製品を摂ると、肝臓の働きが増し、血液中の水分量が増え、熱中症の予防にもなる。
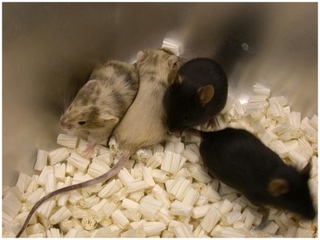

「となりの合衆国へ行かなくてよかった。知りたいことを知ることができた!」とは、参加者の声。午後も医学最先端の話題に興味津々の参加者、およそ200名が詰めかけた。
第一声は谷口教授。がん組織の性質を見つめ、非常識と言われながらも挑んだビフィズス菌を薬の「運び屋」として利用した治療法「善玉菌でがんの治療!」を語った。がん組織は酸素が少なく、ビフィズス菌は酸素が少ない環境を好むという。
続く語り手は新藤教授。もっとも小さな哺乳類のマウスは、人の病気の代わりになってくれる存在として、医学研究の上では欠かすことができない。従来何年もかかっていた病気のマウスをつくるのに、世界最速でつくる方法を開発した教授は、日本科学未来館にも研究ラボを持っている。「ネズミで探る遺伝子のヒミツ」で受精卵から始まる遺伝子改変マウスのつくり方とそのマウスを使った研究について紹介した。
後半には、脳機能を発揮させるシナプス分子の情報処理部分(PSD:シナプス後肥厚部)について探った「脳の話はおもしろい!」、潜在患者数1300万人といわれる慢性の腎臓病と700万人の慢性肝臓疾患の治療法や発症を阻止する方法など、国民にとって「肝腎要(かんじんかなめ)」な話、さらに私たちが元々備えている、ピロリ菌感染や胃癌発生を抑制する胃の腺粘液(*注2)に含まれる糖鎖(化合物)の不思議な性質「胃粘液でがんの予防!」の講演が、それぞれ鈴木教授、青山教授、中山教授によって語られた。
「私たちがこれらの研究をしているということを多くのみなさんに知っていただき、関心を高めていただきたいと思います。そして私たちと一緒に研究をしてくれる院生も広く募っています」と樋口教授。
専攻の目的は新しい医療の基盤として貢献することでもある。
会場で高校生が「先生方みなさん、とても面白く、わかりやすく話してくださるので、もっと知りたい…という思いが強くなりました。今は外科医になりたいと思っています」と話していた。このセミナーは「初めの一歩」として、とても有効だったようだ。
医学系研究科では、11月にも再び同様のセミナーを行う予定とのこと。乞う、ご期待!!
(*注2)胃の腺粘液:胃の粘液には、粘膜の表層から分泌される表層粘液と、粘膜下層から分泌される腺粘液の2種類がある。
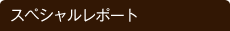
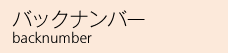
 信大には、独創力を育む環境がある。
信大には、独創力を育む環境がある。信州大学伝統対談 Vol.2 濱田州博学長×スタジオジブリ 宮崎吾朗さん
 どくとるマンボウと信大生のDNA
どくとるマンボウと信大生のDNA信州大学特別対談 山沢清人学長×エッセイスト齋藤由香さん
 信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力
信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力北海道から九州まで、全国へ栽培拡大!
 信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム
信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム理念と信念を持って行動 経営者に聴く、起業の心構え
 CITI Japanプロジェクト
CITI Japanプロジェクト研究倫理教育責任者・関係者連絡会議