

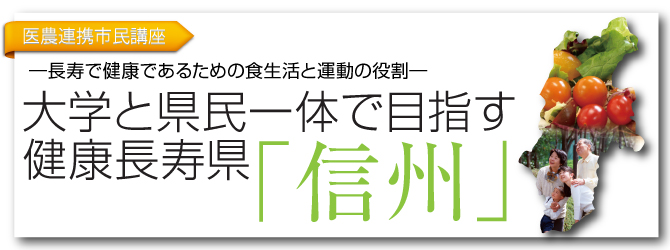
食生活と運動の役割に焦点を当て、健康長寿の秘訣を考える信州大学医農連携市民講座が平成25年1月28日、ホテルモンターニュ松本で開催された(主催=信州大学医学部・農学部)。
現在、日本では高齢化が急速に進み、医療費の増加や福祉施設への入居待ち、自宅介護など様々な問題が生じている。今後も、高齢化は進んでいく事が懸念されており、健康に長生きすることが重要なテーマになっている。
そうした中で講座は、「大学の知識や技術を市民に還元し、地域への貢献を深める。また、県民が健康に年齢を重ねていくために、医農連携を進め、地域の活性化を目指す。」(中村宗一郎副学長・農学部長のあいさつより)ことを目的に開催された。
講座の第1部では、「栄養素と食」の観点から。第2部では、「医学と運動科学」の観点から計4名の講演が行なわれた。

信州大学大学院農学研究科
大谷 元 教授
研究分野:食品機能学、畜産物利用学、1991年~信州大学農学部教授、2001年~大学院農学研究科(独立専攻)教授
“栄養素”とは、生命を維持していくために不可欠な成分のことです。その中でもタンパク質、脂質、糖質、ビタミン、ミネラルを5大栄養素と言い、生命活動において特に重要なものです。だからと言って、栄養素を摂取しすぎるのもよくありません。1日の適正摂取量があります。例えば、脂質の過剰摂取が続くと、肥満やそれに伴う生活習慣病にかかりやすくなってしまいます。
飽食の時代と言われる現代。栄養素の過剰摂取による生活習慣病が大きな社会問題になっています。
この時代の流れを受け、生活習慣病への予防効果が期待される食品が注目されるようになりました。1991年に特定の疾病に対する予防効果が期待できる食品へ“トクホ” (特定保険用食品)の表示を認める法律が制定されました。トクホやサプリといった健康食品の市場は大きくなり、現在では、2兆円の市場だと言われおり、活用されている方も多いと思います。
しかし、こうしたトクホにも限界があり、予防出来る疾病も限られています。そのため、トクホやサプリに頼る事はベストではありません。
こうしたものに依存するのではなく、穀物や野菜など様々な食資源に含まれる栄養素を知り、バランスの良い食事をすることが健康に生きる上で重要です。

松本大学大学院健康科学研究科
廣田 直子 教授
研究分野:栄養・健康教育 栄養調査、2007年~松本大学教授
健康長寿は、食品の中に含まれる特定の機能性成分によって達成される訳ではありません。私たちの身体は、約60兆個もの細胞で形成されていると言われています。その細胞は常に作り替えられているのです。こうした生命維持のために、私たちが外界から摂取する成分として重要なものとしては、まずは、空気や水、次に五大栄養素があり、そのベースの上に機能性成分があるわけです。決して、単一の栄養素や特定の食品のみで人間の健康を語る事は出来ません。
いろいろな栄養素を含む様々な食品をバランス良く摂取することが大切なのです。特に、食事の中における穀類・野菜の役割は非常に大きいものです。
1980年頃の日本の食生活は、炭水化物・たんぱく質・脂質のエネルギー比率が適正で、米を中心として、魚・肉・卵等たんぱく質給源食品、野菜などを使用した副食によって構成されており、バランスの良い食事でした。
しかし、1980年代以降になると、脂質のエネルギー比率が高くなります。それは主食である穀類の摂取量が少なくなったことが影響しています。こうした状況の中、長野県は野菜の摂取量が全国で一番多いという結果になっています。長野県のこのような食文化が健康長寿の一要因なのではないでしょうか。
長野県の伝統的な食事を大切にするとともに、課題である塩分は抑え、さらに、新しい知見を活かしバランスの良い食事を心がける事が重要でしょう。
 信州大学医学部 |
長野県の平均寿命を男女別に見てみると、男性が全国1位、女性が5位※と健康長寿の県であることは間違いありません。しかし、塩分の過剰摂取などの課題もあります。減塩運動によって塩分摂取が減った現在でも、県民の約9割が目標値を超えている、という調査結果もでています。県民の塩分摂取量が多い要因としては、濃い味を好む食文化から醤油や味噌を多く使う傾向が考えられます。また、漬け物などの加工品からの摂取も多くなっています。
そのため、高血圧による脳血管疾患は全国平均よりも高くなっており、今後更に、塩分を抑えるようしていかなくてはいけません。
県民は、野菜の摂取量が全国一位と非常に多い結果になっています。しかし、若年層では、少なくなってきており、心配な点でもあります。また、外食は野菜が少なくなり、脂質の摂取量が増加してしまう傾向にあります。脂質の中でも、LDLコレステロールの増加には注意が必要です。LDLコレステロールは血管に溜まり、動脈硬化を進行させるのです。LDLコレステロールの合成を促すのが、飽和脂肪酸です。これは、お肉などに多く含まれています。バランス良く、食生活を考えていくことが重要です。
しかし、すぐに摂取制限をするというのは、大変なことです。長期的なスパンで考えて、末長く個人の行動変容を促していく事が重要だと思います。
また、何事も早期発見することが重要ですので、病院への検診を受ける事も大切な事です。
※ シンポジウム時現在。 2月28日厚生労働省の発表で男女共に1位になりました
 信州大学大学院医学系研究科 |
生活習慣病の発症メカニズムは、加齢による体力低下に伴うミトコンドリア機能の劣化が全身の慢性炎症を引き起こすと考えられています。つまり、その炎症が脂肪細胞におこれば糖尿病、免疫細胞なら動脈硬化、脳細胞なら認知症、癌抑制遺伝子なら癌を引き起こすという考えが主流になりつつあります。そのため、これらを予防するためには、体力向上を目指し、ミトコンドリア機能を活性化させることが重要なのです。
私たちはこの15年間、中高年者の健康スポーツ教室「熟年体育大学」事業を運営し、5200名以上の中高年者を対象に、「インターバル速歩」を中心とした運動指導を行なってきました。その結果、体力向上に比例して、生活習慣病などの症状が改善することを明らかにしました。
しかし、日常的に運動をするのは容易ではありません。そこで、運動を楽にする食品成分について研究を行っています。今回は、ALA(5ーアミノレブリン酸)という成分について報告いたします。
 信州大学大学院医学系研究科 |
高齢者のALA摂取が運動時の仕事効率を上昇させ、生活習慣病の改善が期待できるかについて調べました。
ALAを摂取した人にインターバル速歩という運動を行なってもらった場合とプラセボ条件(偽薬を摂取)で運動を行なった場合の比較を行ないました。その結果、高齢者がALAを摂取することで、運動時の仕事効率を上昇させ、また、速歩運動トレーニングの量を亢進させることが分かりました。このように、生活習慣病の改善効果を加速することが期待できることを明らかにしました。

信州大学副学長・農学部長
中村 宗一郎
専門分野:食品化学、2005年~信州大学農学部教授
講座には、120名余りの参加者が集まり、健康や機能性食品に対する市民の意識の高さが感じられた。
参加者からは「信州大学が今回のような講演会等で市民へフィードバックしてくれることで新たな知識を発見出来、頼もしい」との声が多かった。同講座では、質疑応答も活発に行なわれ、大学と市民が一体となり、知識を深める講座になった。講座の参加者らが、今回の知識をそれぞれの地域へ持って帰り、地域全体で元気になっていくことを期待したい。
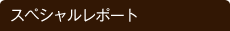
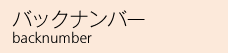
 信大には、独創力を育む環境がある。
信大には、独創力を育む環境がある。信州大学伝統対談 Vol.2 濱田州博学長×スタジオジブリ 宮崎吾朗さん
 どくとるマンボウと信大生のDNA
どくとるマンボウと信大生のDNA信州大学特別対談 山沢清人学長×エッセイスト齋藤由香さん
 信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力
信大発夏秋イチゴ「信大BS8-9」の魅力北海道から九州まで、全国へ栽培拡大!
 信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム
信州大学 SVBL 設立10周年記念シンポジウム理念と信念を持って行動 経営者に聴く、起業の心構え
 CITI Japanプロジェクト
CITI Japanプロジェクト研究倫理教育責任者・関係者連絡会議