

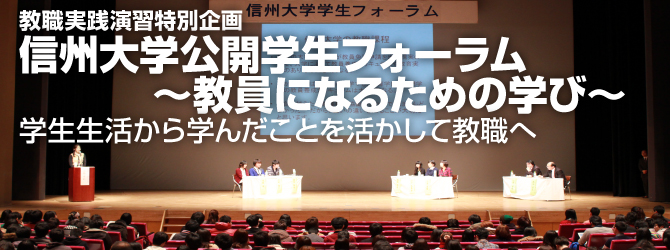
平成26年1月22日(水)、教職実践演習特別企画「公開学生フォーラム~教員になるための学び~」が、ホクト文化ホール(長野県民文化会館)にて開催された。教育学部と専門学部(人文・理・工・農・繊維)の教職課程で学ぶ学生や教職員ほか、総勢420名が参加。学生たちは学部を越えて大学生活で学んだことを振り返り、語り合った。
(文:中山万美子)
教職実践演習とは、教育職員免許法改正により、今年度からあらたに4年次の必修となった新設科目で、1)使命感・責任感・教育的愛情、2)社会性や対人関係能力、3)幼児・児童生徒理解、4)教科等の指導力 など、教員として必要な知識・技能を習得しているかを振り返り、課題を自覚し、必要に応じて不足したものを補い、教員生活をより円滑にスタートできるようにと開設されたもの。
初年度、学生達はどのようなことを思いながら授業に参加していたのだろうか。その思いを語ってもらおうとフォーラムが企画された。しかし4年生にとって、この時期は卒論を仕上げる時期と重なってくる。フォーラムを担当した教育学部臨床教育推進室の伏木久始教授は「あらかじめ形をつくり学生たちの負担を減らすことを考えていましたが、彼らは座談会形式で行いたいといい、自ら表現する場として活かしてくれました」という。
プログラムの前半は、パネルディスカッション「Topics1 4年間の大学生活で取り組んだこと」。ゲストコメンテーターとして長野県教育委員会教学指導課課長武田育夫氏、長野県上高井PTA連合会元会長の小平昭哉氏を迎え、司会は三石早紀さん(教育)、パネリストには6人の学生が登壇した(全員4年生)。
プレゼンのトップバッター、北見聖(あきら・教育)さんは4年間、より多くの出会いを心がけ、子ども、地域、仲間との関わる中から様々なことを学んできた。今、あらためて自分が子どもとの関わり方として、教師という立場が最適なのかを考えているという。
月岡優介さん(教育)は、部活の幹部やバイト、大学周辺から全国に及ぶ子どもに関わる活動の経験などから、自ら“楽しむ”重要さを知り、子どもたちに会いたいという気持ちだけで動ける仲間を得る。影響を与え続けることができる人間になりたいと語った。
富永翔馬さん(教育)は、いろいろな子ども達と触れ合う体験をしながら、自分の心の中には子どもが不在だったと感じた。「子どもに合わせる…」と言いながら、実は自分のためだけの学びをしていたと気づいた。これからは「本当の意味で人に目を向けて」いき、学問、臨床双方の教育を重視する教師として歩んでいきたいという。
長坂朋美さん(教育)は、高校生の頃から中高生のボランティアに関わってきた活動について、また震災被災地の宮城県女川高校の取り組みなどを紹介した。中高生の思いを感じ取り、そっと後押しする教師になりたいと話す。
山下美都香さん(農)は、農場の野菜作りや調査活動で知った「食と農の偉大さ、大切さ」、大規模なサークルで学んだ人との関わり、子ども達の学力支援ボランティアなど、すべてが進路に影響したと語った。
小室良枝さん(繊維)は、工業高校から繊維学部に進み、モノづくりを学び続けてきて、学生ベンチャー企業のコンテストへの挑戦などの経験を持つ。しかし自分が本当にやりたいことを考え、研究者ではなく教育の道を選び、4月から教育大学の大学院へ進学する。
精一杯の4年間を過ごしたパネリストたちの振り返りは、会場に参加する人々を刺激し、各自の振り返りにつながったようだった。
Topics1を終えると、全学教育機構小山茂喜教授、教育学部谷塚光典准教授による信州大学の教職課程の説明が行われ、引き続きディスカッション「Topics2 これからの教員養成に必要な学びとは」が始まった。ここでは、双方向のコミュニケーションができるオーディエンスレスポンスシステム(ARS)を使用し、フロアの4年生(およそ280名)の意識調査をしながら行われた。
「卒業に対する思い」、「今の自分に足りないもの」「1年生からもう一度大学生活をやり直せるとしたら何を頑張るか?」ほか、教職課程において教員として必要な資質を身に付けられたかなど、7つの質問を参加者に問い、質問ごとにARSで集計したグラフがスクリーンに映し出された。機転の利いたユーモアで盛り上げる司会の三石さんが和やかなムードで会場とステージを一体にする。マイクを向けられた学生たちも忌憚なく本音を語った。
「1年生から…」の質問では「サークルや部活動」と、「留学」を頑張りたいという回答が共に27%、また「幼児・児童・生徒理解」が「まあまあ身に付いた」と「どちらとも言えない」が共に29%で最多。また「卒業に対する思い」の回答からは、漠然とした不安を抱えている学生が多いことが浮かび上がった。
一方、「必要な学びとはなんでしょうか」という司会の質問に、パネリストからは「一人ひとり違うから、それぞれに合ういい刺激を受けること」(北見)、「与えられた環境で、その場を楽しむ心が大事」(月岡)、「変化に対応できる力をつけること」(富永)、「疑問に思う気持ちをもって学ぶこと」(長坂)、「体験する、現場のことをよく知ること」(山下)、「やる気、貪欲な意欲が大事」(小室)等、前進を感じさせる力強い言葉が聞かれた。

まとめにゲストコメンテーターの武田氏は「長野県は教員を大事にしてくれる土地柄。いろんな批判が出てもそれをエネルギーに変えていくたくましさを身に着けていってほしい」、小平氏は、「社会人になるのは不安だと思うが、不安だから謙虚になれる、自分の常識が通用しないからこそ謙虚さを覚える。5年頑張れば、きっと何かを得られる」と、それぞれに会場の4年生へエールの言葉を送った。
「授業の一環として行なわれたフォーラムだったが、司会者、登壇した学生たちの進行や議論は、予想以上に優れていた。ARSを用いたことでフロアの学生たちの参加意識を高めていた」と振り返る伏木教授。「教育学部と専門学部はそれぞれキャンパスも異なり、距離があるが、学部を越えて学び合う場を設ける意義は大きかった。今後は授業の一環としてではなく、有志による学生フォーラムの企画を検討したい」と話している。

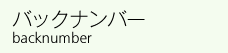
 平成26年度環境教育海外研修報告
平成26年度環境教育海外研修報告エネルギーの行方。資源産出国「タイ」で学ぶ環境と資源
 第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト
第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト若者の日本酒離れに歯止めをかけ、地域の酒造メーカーを支援しよう
 多様化する金融犯罪とどう向き合うか
多様化する金融犯罪とどう向き合うか―関東財務局・長野県警との連携特別講義、経済学部で開催―
 グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力
グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力現地の声を聞き、外の世界に目を向ける
 信州大学環境教育海外研修(6)
信州大学環境教育海外研修(6)開発途上国が抱える環境問題―ネパールを訪ねて―