



国外の環境先進国や開発途上国を訪れ、現地で学ぶことで環境に対する多様な視点を持ってもらうために、本学では環境教育海外研修を行っている。単なる知識を得るだけでなく、自分で考え、実践出来る人材を育成することが目的だ。第4回目となるこの海外研修が、平成24年2月25日~3月4日に渡って行われた。今回の研修は「環境とエネルギー」をテーマにイタリアの3都市を巡った。その内容を広く還元するため、6月18日環境教育海外研修報告会が開催され、多くの学生・教員らが参加した。その模様をレポートする。

信州大学 工学部 電気電子工学科情報通信
田中 清教授
1989年に防衛大学校理工学研究科を修了。
1992防衛大学校情報工学科助手。
1995年より信州大学に勤務2006年より現職。
多目的最適化、画像・映像処理、情報セキュリティ、スマートグリッド

「工学部として、環境について何を考えていかなくてはいけないか。やはり、エネルギーだと思いました。昨年の震災による原発事故のこともあり、“環境とエネルギー”をテーマにしました」と引率教員の田中清教授は話す。イタリアというのは、エネルギー自給率が15%と低く、日本とほぼ同水準である。さらに、火山国であるという点も、日本と類似している。「日本と似た環境にあるイタリアがどのようなポリシーでエネルギーを研究し、環境について考えているかについて知る事は重要なことだと考えました」。今回の研修では、信州大学と2010年より学術交流協定(Memorandum of Understanding)を結んでいるベニス カ フォスカリ大学やパドバ大学などに協力してもらい、現地視察を行った。
イタリアでは、再生可能エネルギーの研究が盛んに行われている。さらに、福島第一原発の事故を契機に、イタリア国内でも脱原発への動きが高まっており、特に、太陽光発電や地熱発電への取り組みが注目されている。2011年度には太陽光発電導入量が世界第2位になるなど、着実に成果も現れてきている。
「今回は、エネルギー問題や環境問題に取り組んでいるベニス カ フォスカリ大学を初め、パドバ大学やローマ大学、イタリア国立先端技術エネルギー研究所(ENEA)、トスカーナのラルデルロ地熱発電所、ヴェネチア市役所を訪れました。ベニス カ フォスカリ大学のAlvis Benedetti教授を初め、お世話になった方々に心から感謝したい」と話した。
「今回の研修を通して、イタリアも日本も目指している方向は同じだということを実感しました。今後は信州大学としてもベニス カフォスカリ大学やパドバ大学との国際交流を深め、協力して研究を進めていきたいという思いがあります」と田中教授。イタリアの研究者は、環境そしてエネルギーへの意識を高くもって研究に励んでいると感じたという。その思いに刺激を受け、「学生達も、行く前と行った後では、意識が変わり大きく成長したことを感ずる。やはり、自分の足を使い、目で見て考える、ということが大切。今回の研修は、学生達にとって非常に大きな財産になったのではないでしょうか。4名は、それぞれ学部もやりたいことも違いますが、今回感じたことを生かしていってもらいたい」と語った。
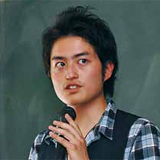
|
この94%という数字は何を示しているでしょうか。これは、2011年にイタリアで行った原発の是非を問う国民投票で原発反対票の割合です。それだけでなく、もう一つ意味を持っています。それは、再生可能エネルギー発電施設をもつ市町村の割合です。
この数字だけ見ると、イタリアは、国民の殆どが原発に反対していることが分かります。しかし、ベニス カ フォスカリ大学で交流した学生達に同じアンケートを取ると、7人中3人しか反対ではなく、国民投票の結果と異なりました。
イタリアでは、1990年に国内の原発全4基が閉鎖しています。しかし、スイスやフランスからの輸入電力に頼っているのが現状です。フランスは原発推進国であり、輸入電力に頼っていることで、原発から脱却出来ないでいる構図になってしまうのです。学生の意見としては「エネルギーの輸入は税金の無駄使いなので、今の状況では国内の原発に頼らざる得ない」という内容でした。お金などの問題ではなく、問題の本質として原発の危険性についてもっと議論する必要があると感じました。

世界で初めて地熱発電が行われたラルデルロ地熱発電所
イタリアのエネルギー事情
地熱発電はイタリア発祥の発電システムです。化石燃料を必要とせず、排出される温室効果ガスも火力発電よりクリーンであることから近年注目されています。また、安定した供給を見込めるということも長所と言えます。しかし一方で、その地点毎に水量が限られているのでいつか枯渇してしまう、ということや、表層度を汚染するという欠点も挙げられます。課題は多くありますが、地熱発電は日本でも見直されています。地質学を専攻しているので、イタリアに地熱発電の原点を見に行ったということを生かして、今後の研究などに役立てていこうと思っています。

|
イタリアは太陽光発電の導入量がドイツに次いで世界第2位です。従来のソーラーパネルの性能向上のための研究や新しいタイプのソーラーパネルの研究を進められています。
塗布する材料の化学研究を行い、次に基盤に焼き付ける技術の研究を行います。そして、特性を解析するというサイクルで、実用性の高いソーラーパネルの研究を進めているそうです。ローマ大学で現在開発中のソーラーパネルは、軽量化で薄く、自由に曲げることが出来ました。曲げられることで様々な場所に設置する事が可能になっているそうです。あらゆる場所で太陽光の力を利用出来るようになってきています。
ヴェネチアの建築は、周囲の景観に配慮したものになっています。屋根や壁の色が統一されており、美しい景観を保っていました。ヴェネチアでは、新築ではなく、再生するという考え方が息づいていました。建物の再生にしても、廃材バンクというものがあり、取り壊した建築物の廃材をストックしている場所があります。その廃材を利用して、建物を再生していきます。日本では、どうでしょうか。古くなったものは取り壊され、新築にしてしまうのが一般的です。
これからは、こういった“再生”という考え方が重要だと思います。木々を破壊して、建物を建てるのではなく、木々と共存した建築を行っていく事が大切ではないでしょうか。これからも、建築に関わり続けて共存と再生を大事にしたものを作りたいと思います。
また、イタリアでは廃材を使ったバイオマスなども盛んで、日本でもこうした取り組みが広がれば、再生可能エネルギーの考え方も一層広まるのではないかと感じました。
 Aldo Di Carlo教授のグループが開発中の |
 サン・マルコ広場の鐘楼から見た |

|
美しい町並みで有名なヴェネチアも様々な問題を抱えています。まずは高潮(アクア・アルタ)が発生するということです。この高潮が発生すると、街中が水浸しになってしまうのです。そして、アクア・アルタの発生回数は年々増加しています。1924年から観測が始まっており、10年ごとの発生回数を数えてみると、1924年~1933年は50回程度でした。しかし、1994年~2003年の間におよそ250回以上のアクア・アルタが発生しており、ヴェネチアの大きな問題となっています。このアクア・アルタは、潟から外海への水の流出を防いでいる風が季節風等の影響により強く吹くことで、潟の水量が増し、そこに満潮が重なることで発生します。
ベネト州は高潮対策として水路3カ所に可動式のゲートを78基設置するという“モーゼ計画”を2004年に立ち上げました。しかし、住民からは潟の環境を壊すとして反対意見が多く寄せられているそうです。自治体や住民との意見は折り合わず、環境問題解決の難しさを感じました。
ヴェネチアのごみ収集方法は、家の前にごみを置き、それを収集してくという方法です。これも、ごみ置き場が景観を壊してしまうという理由からです。ヴェネチアとしては、ごみによる景観破壊に注意を払っているようですが、街中にはタバコの吸い殻やペットボトル等が沢山落ちていました。このごみは、観光客が原因だそうです。観光客も一人一人が問題意識を持つ事が重要だと思います。
この研修を通じて、自分がいかに狭い視野で物事をみていたかに気付かされました。日本だけではなく広い視野で環境問題やごみ問題などを考えていく重要性を感じました。
 ヴェネチアでは、水上バスを利用して |
 観光客のごみ問題についても |

|
イタリアでは、観光客が捨てていくごみが大きな問題となっています。ポイ捨てはもちろんですが、年間4400万人が訪れるヴェネチアでは、膨大なごみの量になってしまいます。ごみの処理というのはもちろん自治体が行っています。
イタリアには来て欲しいけれど、ごみを処理しなくてはいけないというジレンマがヴェネチアにはあります。この問題について、自分は本当に考えていたか、という事に気付かされました。自分が海外に行き、そのうちの1人の観光客であることに気付きました。
現地の人たちがごみ問題についてしっかりと考えていても観光客が台無しにしてしまっているのです。自分たちが海外に行く時には、その土地の環境についてしっかりと配慮することの重要性を感じました。
ベニス カ フォスカリ大学の日本語学科の学生との交流の中で、学生たちが幼少期にどのような環境教育を受けてきたかを聞いてみると、「トウモロコシ作り」や「地球を守ることについての議論」などが挙げられました。しかし、彼らの記憶にはあまり残っておらず、環境教育の必要性の意識に差がありました。もっと記憶に残る環境教育を実践していく事が大切ではないかと思います。
ベニス カ フォスカリ大学の学生の「今のイタリアは経済問題もあり、先の環境の事より目の前の利益を追っている」という言葉が印象に残っています。“環境への配慮の差”、というのはその国が抱えている他の問題に影響を受けているということです。私たちが、環境問題について考えられるのも日本が経済的に恵まれているからだ、ということを感じました。
今回の研修を通じて、生の声を聞く事、体験する事の重要性を知りました。この経験を実際の教育現場に還元していきたいです。
 「観光都市イタリア」しかし、その裏側には |
 「環境への意識についてのアンケート」を現地学生に実施し、 |

2012年7月1日~7月8日、プトラ大学(マレーシア)から准教授と講師、学生4名の計6名の訪問団を受け入れました。昨年3月、本学の環境教育海外研修の一環でマレーシアを訪れた際、同大学にはたいへんお世話になりました。今回は、昨年とは逆に、本学の環境マインドの取組を見学していだき、学生を中心とした国際交流を深めました。
本学の環境マインドの取組の中で、プトラ大学の学生が特に印象に残ったのは、エコキャンパスカードやごみ分別の徹底、自転車利用とのこと。環境ISO学生委員会が毎年参加している全国大会に関して、今後さらに国際交流企画や国際大会につなげられないかとの意見もありました。後日、プトラ大から今回の研修報告(レポート)を送っていただく予定です。最後に、今回の訪問団受け入れにお力添えをいただいた方々に御礼申し上げます。
( 全学教育機構 環境マインド推進センター兼務教員 金沢謙太郎)

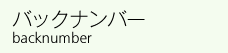
 平成26年度環境教育海外研修報告
平成26年度環境教育海外研修報告エネルギーの行方。資源産出国「タイ」で学ぶ環境と資源
 第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト
第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト若者の日本酒離れに歯止めをかけ、地域の酒造メーカーを支援しよう
 多様化する金融犯罪とどう向き合うか
多様化する金融犯罪とどう向き合うか―関東財務局・長野県警との連携特別講義、経済学部で開催―
 グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力
グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力現地の声を聞き、外の世界に目を向ける
 信州大学環境教育海外研修(6)
信州大学環境教育海外研修(6)開発途上国が抱える環境問題―ネパールを訪ねて―