


日本は環境技術で世界をリードし、「環境先進国」とも呼ばれているが、私達には環境先進国というほどの自覚があるだろうか?
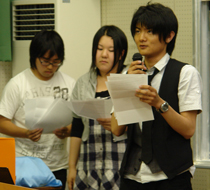
2009年3月、環境ISO学生委員会の4人のメンバーがドイツ・オーストリアへ環境教育研修に行ってきた。施設見学、ドイツの学生達との交流、街の散策や調査から学んだものは、今、彼らの環境活動の原点にもなっているようだ。
同年6月18日、共通教育の講義「環境社会学入門」(担当:全学教育機構 准教授 金沢謙太郎)で、上原麻理子さん(農学部)、森本竹洋さん(工学部)、後藤浩介さん(工学部)3名が、それぞれ農作物、クリーンエネルギー、環境意識と教育について発表した。

上原麻理子さん(農学部2年)発表内容
ウィーンで見学したゴミ処理場では、収集車がゴミを降ろす集積所の上に鳥の巣を設置し、「そこに鳥が来るか」で環境をチェックする。「有害排気などは、もちろん数値で計っていますが、生き物に優しいかどうかを、一般の人の目に見えるカタチにしていることが面白いと思いました」
リューネブルク大学でのディスカッションでは「現在の農業では、生産者と消費者の距離が一番の問題。『有機栽培』『国産』など、スーパーマーケット側からの表示しか情報がない。それをただ鵜呑みにするだけでは、生産者への興味は育たず、生産者との距離を作り、消費者の農業への無関心に繋がり、産地や成分偽装などの食品安全問題や農業後継者不足を引き起こす。また、生産現場の苦労を知らないと、作物の大切さやそれに見合った値段を見失い、作物の価値は下落する一方になってしまう」との話が出た。
ウィーン市内のスーパーで売られていたイチゴは、大小さまざまな形で、甘いものから酸っぱいものまでが混ざっている。日本では、イチゴの商品価値は「形が揃っていて、甘い」ことなので、これでは商品にならず、捨てられてしまうことも。手間、肥料、温室を温めるエネルギーなどがすべて無駄になってしまうが、ウィーンでは他の果物や野菜もふぞろいなままスーパーに並んでいて、農業の生産システムに無駄がないと感じた。

森本竹洋さん(工学部2年)発表内容
風力による発電量は、ドイツが世界で一番多く、風車の数は約2万基。南部フライブルクから北部ハンブルクまでの列車の中からでも、約50基を見つけた。日本は1500基しかない。風車は景観を損なうと言われるが、自分には格好の良いものに感じた。しかし、風車を山の頂上まで運ぶために、木を切り倒さなくてはならず、野鳥が風車に衝突して死んでしまうということや、騒音の問題もある。野鳥の衝突に対しては、風車から超音波を出すという方法が考え出されてきている。これらの問題を解決していくことが風力発電を発展させるために重要だと感じた。
太陽光発電の導入量もドイツが世界一。町を歩いていてソーラーパネルを見つける頻度は日本とそんなに大差がない気がしたが、ビルの側面に設置されていたり、看板の裏など目に付きにくいところにあったり、設置の仕方に工夫を感じた。
現在ドイツは電力の27%を原子力発電でまかなっている。その廃棄物であるウランで環境汚染が起きたことなどから、この27%を洋上風力発電などのクリーンエネルギーでまかなうという政策がある。しかし、他国での原子力発電がクリーンであるという声の高さに、政策変更もありうるという。

後藤浩介さん(工学部2年)発表内容
音楽の都ウィーンの地下鉄構内にも、日本と同じように落書きはあり、環境都市と言われるフライブルクの道路にもゴミは捨てられていて、「環境意識が高い」とは感じず、また「意識が高ければいいというものでもないのかな」と感じた。意識ではないとするとどこが違うのか。環境教育か。
リューネブルク大学の環境教育は1年の前期から環境科目が始まる。1週目から7週目の間に「自分と持続可能な社会との関わりを見つける」。信大の全学教育機構の講義のような形で、持続可能な社会の「役割」「機能」「政治」などの自分との関わりについて学び、8週目からは自分の興味のある仕事などの現場に行き、実際に見て体験し、そこでの「持続可能な社会」との関わりを自分達で見つけ出す。最後の15週目は3日間連続のグループ発表と学生同士の討論をすることで学生の環境意識を高める。
2年生は環境科学か環境社会学を必ず学ぶ。学生食堂ではオーガニック食品も使っているが、これは学生たちが近郊の大学と連携して実現したものだ。さらに、学生の寄付によって、学内にソーラーパネルを設置。また学生同士がカーシェアリング(車の共同利用)できるシステムもあるなどその行動力には目を見張るものがある。このような環境に配慮する数々の取り組みが、現在ではリューネブルク大学の“ウリ”になっている。信大もそうなるためには、学生が主体となって大学に働きかけることが重要と学んだ。

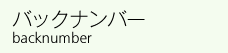
 平成26年度環境教育海外研修報告
平成26年度環境教育海外研修報告エネルギーの行方。資源産出国「タイ」で学ぶ環境と資源
 第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト
第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト若者の日本酒離れに歯止めをかけ、地域の酒造メーカーを支援しよう
 多様化する金融犯罪とどう向き合うか
多様化する金融犯罪とどう向き合うか―関東財務局・長野県警との連携特別講義、経済学部で開催―
 グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力
グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力現地の声を聞き、外の世界に目を向ける
 信州大学環境教育海外研修(6)
信州大学環境教育海外研修(6)開発途上国が抱える環境問題―ネパールを訪ねて―