


教育学研究科の心理教育相談室で開かれた、「第1回しんしんゼミナール」。
地域の人と、心理学のおもしろさを共有する場を作りたいという願いから立ち上がった、相談室初の試みだった。
「しんしんゼミナール」と相談室の取り組みについてご紹介する。
・・・・・ 信州大学広報誌「信大NOW」第64号より

ゼミナールは、5~7月の各第4土曜日に開催。「A子どもをのばす・子どもを育てるコース」・「Bちょっと気になる子どもへのサポートコース」・「C毎日子どもに楽しく出会うためにコース」というように、毎回内容が異なり、教育学研究科の教員が、大学での講義を濃縮した内容で行った。
なぜこのゼミナールを企画したのかー。
「今、社会的に心理学の認知度が高まり、勉強をしたいと関心をもっている人がたくさんいるのに、なかなか一般の人が学べる場所がないのが現状。そんなニーズに応える場を、私たちが提供できたらと思いました」と、教育学部の島田英昭先生。教育学部では、学部、大学院で心理学専攻を持っている。その持ち味を生かし、「子どもへのかかわり」をベースとした内容を用意したところ、主に教員や発達相談員など、教育や発達心理の分野に携わる人が多く集まった。
1コースにつき、3人の講師が講義を担当。例えばAコースでは、「子どもにとってわかりやすい説明とはなにか」「子どもの学ぶ意欲を高めるには」「子どもの言葉の能力と創造性を育てる」という3つのテーマを取り上げた。聞いて理解するスタイルや、ロールプレイなどの体験学習を取り入れた参加型スタイルなど、教員の個性が表れたユニークな内容ばかり。参加者からも盛んに意見が飛び交い、活気ある講義となった。
ゼミナールが地域との接点となり、生涯学習の欲求に応える場となるよう、今後も更に充実した企画を検討していく予定だ。
心理教育相談室の主たる取り組みは、もちろん「相談業務」。発達障害やいじめ問題、友達関係や職場での対人関係の悩み、うつ、子育て不安、当事者の家族や教育・福祉・医療・産業などの分野における関係者の援助指導など、その内容は幅広い。子どもから大人まで、長野県内さまざまな地域から相談者が訪れる。
プログラム内容は人それぞれ。話を聞いてもらったらスッキリしたと、1度で終わることもあれば、何年間かにわたり、相談者のライフステージに応じてプログラムを組み、見守り続けていくこともある。また場合によっては、専門機関につないだり、学校と連携しながら対応を考えるなど、地域の関係機関の調整役を務めることもある。相談したいけど、病院は敷居が高い…。相談室なら行きやすいかも、と地域の人に身近に感じてもらえる相談室を目指している。
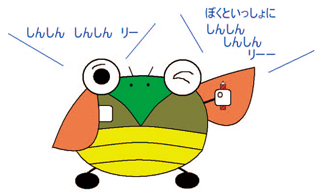
相談室は、臨床心理士を目指す大学院生が実践を積むトレーニングの場でもある。
自ら相談員であり、学生の相談役でもある教育学部の上村惠津子先生はこう語る。「学生は時間的余裕があり、とても熱心。個々の相談者を大切に思う気持ちに、ハッとさせられます。子どもの相談の場合、視点が近いので、親近感をもたれやすいというメリットも。知識・経験不足の面は、私たち教員が責任をもってバックアップしています」
臨床心理士とは、「人間の“こころ”の問題にアプローチする“心の専門家”」。信大教育学研究科は、臨床心理士養成機関第一種指定大学院に認定されており、修了生は県内外で多く活躍している。また、社会人入学も多い。そのことからも、社会のさまざまな場面で心理学のニーズが高まり、その必要性を感じている人が増えていることがうかがえる。
「心理学」を通して地域とつながり、人々の学びを支える場所ー。相談室は、そんな存在となることを目指している。

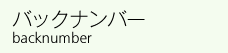
 平成26年度環境教育海外研修報告
平成26年度環境教育海外研修報告エネルギーの行方。資源産出国「タイ」で学ぶ環境と資源
 第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト
第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト若者の日本酒離れに歯止めをかけ、地域の酒造メーカーを支援しよう
 多様化する金融犯罪とどう向き合うか
多様化する金融犯罪とどう向き合うか―関東財務局・長野県警との連携特別講義、経済学部で開催―
 グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力
グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力現地の声を聞き、外の世界に目を向ける
 信州大学環境教育海外研修(6)
信州大学環境教育海外研修(6)開発途上国が抱える環境問題―ネパールを訪ねて―