


「スペシャルオリンピックスで学ぼうゼミ」(担当:佐藤陽子非常勤講師、SO長野松本プログラムメンバー、コーディネーター:矢部正之教授)は、主に1年生が学ぶ全学教育機構(共通教育など)で、前期に開講している科目の一つ。スペシャルオリンピックス(SO)という知的発達障がい者たちのスポーツ活動に参加しながら、ボランティアや知的障がい、SOについて理論と体験で学ぶ実践的な授業だ。

7月26日の4限目(14:40~16:10)。体育館に行くと、にぎやかな「松本ぼんぼん」の曲がかかり、学生と障がい者の方々が輪になって踊りの練習をしていた。ゼミ最後の授業は、夏祭りに参加する知的障害者の福祉施設「四賀アイアイ」の方々と、踊りとフロアホッケーの練習をする実技だった。
「~ぼんぼん松本、ぼんぼんぼん、…さあ、いくよ、シュワッチ、シュワッチ…」
踊りの輪の中心で、中村嘉也非常勤講師(SO日本長野松本プログラムメンバー)の元気で張りのある声が何べんも響き、和気あいあいとしたムードを盛り上げている。シュワッチ、シュワッチというのは、振りの一部がウルトラマンのポーズに似ているからだ。
学生たちは障がい者の方々とペアを組み、動きに合わせてフォロー。すっかり意気投合してノリノリで楽しく踊るペアもいれば、大学の体育館という慣れない環境のためか、輪からはずれて休んでしまうペアもいる。学生たちはそんな時にも慌てず、ゆっくりと障がい者の方々に寄り添う。大方のペアはテンポのよい曲とは少し違う、ゆったりした動きで回っていた。
踊りの練習の後は、フロアホッケーの練習をして、締めくくりに、川上都子非常勤講師(SO日本長野松本プログラムメンバー)が、おいしいかき氷を作って参加者に振舞った。

スペシャルオリンピックス(SO)とは、知的発達障がい者たちの世界的なスポーツ活動で、地域では日常プログラムとしてトレーニングや競技会がある。ほぼ毎週末に公共の体育館などで日常プログラムが行われており、松本のプログラムにはフロアホッケー、バスケットボール、水泳がある。ゼミではこの日常プログラムへ3回以上の参加を条件としているが、毎回のように参加している学生もいるという。
ゼミの開講は、2005年に長野でSO冬季世界大会が開催されたことがきっかけだ。その前年、世界大会を前に矢部教授が事務局長となり信州大学SOボランティア事務局が発足し、初の「ボランティア教育」を目的とした正式な授業科目が登場した。当時、履修登録をした学生は171人もいたという。世界大会終了後も、ボランティアや障がいについて、SOの日常プログラムを取り入れながら学ぶゼミが開講され、現在に至っている。

全15回の授業の前半は、講義が中心となる。障がいやボランティアの概要、アスリートや障がい者の在宅生活について、またノーマライゼーション(障がいのあるなしに関わらず、ともに助け合い暮らしていく社会であろうとする考え方)などが丁寧に解説される。後半の授業ではグループに分かれ、学生たちはさらに深めたいテーマを選んで調査研究をし、プレゼンテーションをする。その間に日常プログラムのボランティア実習もこなす。
今年度の4グループが取り組んだテーマは「スポーツでできるボランティア」「ダウン症について」「発達障がいについて」「アスリートを取り巻く環境について」。
それぞれのプレゼンテーションの資料作りは、入学したばかりの1年生にとってはなかなか大変な作業で、実はこのプレゼン方法を学ぶことも、授業の大切な要素の一つとなっている。
プレゼンの1回目は附属中学校の中学生を対象に授業として行われ、2回目は公開授業として一般の参観者を教室に招いた(7月12日、19日)。
発達障がいについて調べたグループは、アメリカの俳優や元大統領ら、発達障がいがあっても立派な仕事をする有名人を挙げたり、「障がいには一つとして同じものはなく、本人の特性にあったサポートが必要であること」などと発表。「偏見や先入観は相手との関わりを心の中で断ち切ってしまうものだと思いました」、「付き合ってみれば、障がい者と私たちと何も変わりない。『変わりない』ということを、今まで誰も言ってくれなかったと思いました」との感想も飛び出した。
また、知的発達障がい者を取り巻く環境、主に就労の状況について調べたグループは、「制度としては整い始め、一見雇用率もアップしているものの、実態は依然として課題が大きい」と発表。仕事を工夫し、社員の70パーセントが障がい者という日本理化学工業株式会社の例を挙げ「人を理解するコミュニケーション力があれば、知識がなかったとしても障がいを持つ人々と共に仕事ができるのだと知りました」とまとめた。
参観していた伊藤紫一郎さん(SO日本長野松本プログラム代表)からは「SOのプログラムに熱心に参加している学生さんたちを頼もしく感じた。このゼミで学んだことを、今後障害者と社会との関わりにある様々な問題を考えていく上でのきっかけとしてほしい」との感想をいただいた。
「学生たちには漫然と過ごすわけには行かず、大変な授業だと思いますが、アスリート(知的発達障がい者)やその家族と触れ合い、この授業でなければなかなか知ることができないことを経験します。苦労しただけのことは得られると思います」と矢部教授。佐藤非常勤講師(元医学部教授)は「子ども達は小学校から障がい者と分かれて教育され、障がい者と触れ合う機会はほとんどありません。一人でも多くの学生が、同じ人間同士としてきちんと理解し、付き合えるようになってほしいと思っています。学生たちは初め戸惑いを見せますが、最後にはこの授業に対して満足感のある表情に変わっていきます」と語った。

かき氷を食べ、授業を終えた学生たちに感想を聞いてみた。
「障がい者のことを知らずに社会へ出たくなかったんです。日常プログラムでアスリートと関わるうちに障がいは“個性”と思えてきました」(農学部・川上春佳さん)、「バスケットを一緒にやったら楽しくなって、違和感もなくなりました。アスリートも自分も全力でプレーしています」(教育学部・石原昌さん)、「面と向かうとうまくいかなくても、スポーツなら意気投合してがんばれる。スポーツの可能性を追究したいと思っています」(教育学部・丸山健一さん)、「実際に関わってみないとわからない。冗談を言い、笑い合い楽しかったです。自分達で調べたことがそのまま実際に活かす場があってよかったと思いました」(教育学部・片山莉沙さん)
体育館の外は、雨があがって青空が広がっている。四賀アイアイの方々は、かき氷を食べ終わると施設に帰るためにバスに乗り込んだ。笑顔で手を振って見送る学生たち。そのすがすがしい笑顔には、授業をおえた達成感がみえた。

講師陣。左から矢部教授、佐藤講師、川上講師、中村講師
「学生たちにとって、とても良い経験になると思います、この経験を活かしていって欲しいですね」と、日常プログラムに参加する学生たちをフォローする川上講師。「やっぱり体験することが一番ですね」ゼミ開講当初から学生もアスリートも指導してきた中村講師。

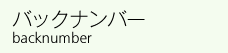
 平成26年度環境教育海外研修報告
平成26年度環境教育海外研修報告エネルギーの行方。資源産出国「タイ」で学ぶ環境と資源
 第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト
第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト若者の日本酒離れに歯止めをかけ、地域の酒造メーカーを支援しよう
 多様化する金融犯罪とどう向き合うか
多様化する金融犯罪とどう向き合うか―関東財務局・長野県警との連携特別講義、経済学部で開催―
 グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力
グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力現地の声を聞き、外の世界に目を向ける
 信州大学環境教育海外研修(6)
信州大学環境教育海外研修(6)開発途上国が抱える環境問題―ネパールを訪ねて―