


本学「環境マインド推進センター」主催の平成22年度第3回環境教育海外研修が、2月27日から3月11日まで行われた。これは、国外の環境活動について学ぶことで、環境に対する多様な視点を持ち、考え、実践する人材の育成と本学の環境活動の推進のために行っているものだ。
「環境マインド」は信州大学が掲げる目標のひとつ。すべての構成員に等しく参加資格があることから、参加者は公募で、書類審査と面接で選考された。今回のマレーシア研修の特徴は、「環境先進国から一方的に学ぶ」のではなく、「共に学び合う」「交流する」という関係性にある。自然の多様さと偉大さを知ると同時に、日本が大量消費するパーム油の巨大プランテーションを視察したことは、「環境マインドを持つ意味」を見つめ直すものだった。
参加者の現地での活動を、引率した金沢謙太郎准教授(全学教育機構)に聞いた。

1968年生まれ。長野県出身。上田高校卒業後、東京外国語大学ヒンディー語学科、筑波大学大学院環境科学研究科修士課程、東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻博士課程で学ぶ。博士(学術)。神戸女学院大学准教授などを経て、2008年秋より現職。
環境社会学、ポリティカル・エコロジー論
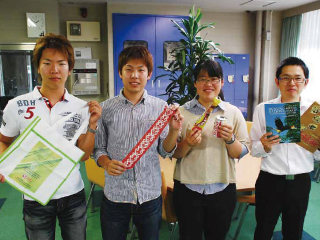
小田原 啓太さん (経済学部2年)
早川 暖さん (工学部2 年)
木本 海花さん ( 工学部2年)
新川 竜悠さん (環境施設部職員)
マレーシアは東南アジアのマレー半島南部とボルネオ島北部を領域とし、クアラルンプールを首都とする人口2750万人の立憲君主制連邦国家だ。
金沢准教授は15年前からサラワク州の狩猟採集民・プナン人の森林資源利用の調査、研究を行っている。自らのフィールドということに加えて、「初回のドイツ研修、2回目のアメリカ研修を踏まえて、アジアで候補地を探しました」。2010年8月には本学とプトラ大学が学術交流協定を結んでいることから、今回の研修先としてプトラ大学に打診。そして、本学への留学経験のあるヒサム准教授にコーディネーターとしてご協力いただいた。
プトラ大学は16学部を擁する総合大学だ。研修前半(3月4日まで)は同大工学部、環境学部、農業食料科学部へ。工学部では同学部の学生と交流し、学内を見学。マーケティング・コミュニケーション局を訪問して、環境の取り組みについての意見交換を行った。
環境学部では授業に飛び込み参加し、本学のすべての施設が環境マネジメントシステムの国際規格ISO14001を取得していることなど環境活動を紹介。環境意識向上のためのエコキャンパスカードやエコバッグの配布、節電啓発のポスター作りなどの取り組みには、プトラ大生から「マレーシアには節電やエコ温度という意識がない。そういう意識を学生自らが持って実行していることに驚く」との感想が出た。

プトラ大学の農業食料科学部は、世界第3位の面積を誇るボルネオ島にあり、海を隔てる。本学も農学部は長野市から88km離れた南箕輪村にあるが、その比ではない。(地図参照)
ボルネオ島はオランウータンやテングザル、世界最大の花ラフレシアなど希少な動植物が息づき、世界遺産の国立公園が2つもある多様な生命の宝庫。半面、その真逆にあるアブラヤシの大規模プランテーション化が進む島でもある。
「ランビル国立公園は生物多様性の研究拠点であり、52haに何種類の樹木があるかを調べる国際的な調査では1200種以上を数え、世界最高です。同様に、グヌン・ムル国立公園には数え切れないほどの昆虫や鳥、動物が棲息している。その豊かさを目の当たりにし、自然の世界の奥深さや、いまなお未知な部分が多い自然そのものを知り、『環境を守る』とは、どういうことか、どこに繋がっているのか、自分のこととして意識できたのではないでしょうか」と金沢准教授。遮るものの何もない360度の空を、龍の形を描いて舞う20万匹のコウモリ。「乱舞するその姿に、羽音に、住処である世界最大の洞窟自体にも、自然の豊かさや力を感じたのでは」と語る。
農業食料科学部の学生と一緒に農作業をしたり、学内キャンプ場の東屋建築の手伝いをしたり。植物油の中で世界で一番需要が多いパーム油の原料、アブラヤシを効率的に育てる大規模プランテーションも見学。画一化が及ぼす生態系への影響や、農薬による河川や土壌の汚染の実態を学んだ。
「多様性の価値はまだはっきりしていませんが、多様であればお互いにカバーしたり、修復したりできる可能性があります。その可能性をゼロにしてしまう『画一化』のリスクをどう考えるのか。アブラヤシから取れる洗剤は人と環境に優しいと言われますが、生産地の環境を考えるとどうなのか。『環境を考える』ことは、地域やそこで生きる人々の暮らしまでを考えること。環境、地域、人の関係性を広く、深く考えることなのだと思います」
研修後半は金沢准教授のネットワークを生かし、ロング・イマンというプナン人の集落でホームステイを体験した。サゴヤシの髄からできた、水飴状のデンプン質の主食を食べ、川で身体を洗い、若者たちとサッカーに興じた。現地の人々と関わり、その暮らしを体験することで、生まれる関係性。サゴヤシのありかを把握し、次世代に悪影響を及ぼさない量を採集し、再生のサイクルを考えて移動するプナン人の生活を知れば、合板を作るための森林伐採や大規模プランテーションが、彼らの生活に及ぼす影響を考えることができる。
「『多様な生物の中の人間。人間の中の多様な文化』を感じてもらえたのではないでしょうか。」マレーシアと日本は木材やパーム油などの「輸出国と輸入国」の関係でもある。「町には安い家具やファストフード、スナック菓子が溢れています。今、手にしているものが『どこから来たのか』にこだわること、その地で行われていることに思いを馳せ、関係性を見つめ直すことが、環境問題に繋がります。一部分だけではなく、広い視野で見つめ、深く考える機会になったなら、うれしいですね」
今後、プトラ大学との共同研究や信大への短期研修プログラムも視野に入れ、今回築いた関係性を育んで行く考えだ。


最終処分場では、手作業によってゴミの分別が行われている
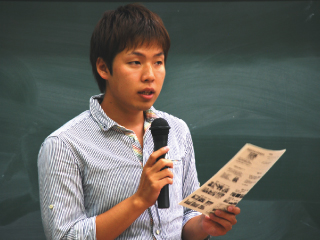
早川 暖さん(工学部2年)

土を濾している様子

集合写真。日本の大学と比べて女性がとても多い

小田原啓太さん(経済学部2年)

デパートのマイボトル売り場

プトラ大学でのプレゼンテーション

新川竜悠さん( 環境施設部職員)

アブラヤシのプランテーション

牧草を植える実習にて
分別することは当たり前だと思っていました。
木本海花さん(工学部2年)
信州大学工学部では7種類のゴミ分別があります。分別をする際の指標として材質の識別マークを見ます。私は、この環境負荷低減の方法の1つである環境ラベルに注目しました。分別をすることは当たり前だと思っていました。しかしこの海外研修を通して、国によってリサイクルの回収システムが異なることに大変驚きました。マレーシアではビンの1種類のみ分別し、その他の燃えないごみと燃えるゴミはすべて一緒に捨てます。
このような現状ですがマレーシアの行政はいろいろなイベントや展示会を企画し、学校での環境教育を行うことで環境意識を高めているようです。またプトラ大学にも訪問し、学生の環境活動を紹介していただきました。自然公園へ赴き、樹木の観察や清掃活動などを行っており、学生一人一人が環境活動に熱心に取り組んでいる様子も直に感じました。
国は違っていても、同じ地球上に生まれてきた者として、未来の地球のために、地道な環境配慮活動を共に考え、実行していきたいと強く思っています。
マレーシアの学生は「とにかく元気」です。
早川 暖さん(工学部2年)
マレーシアの学生は、日本の学生と比べると「とにかく元気」です。環境マネジメントの講義に参加させていただいたのですが、学生が発言しまくりますし、人見知りせずにガンガン話しかけてくる感じです。環境活動も学生自ら行っていることが多く、日本が初めて行った「EM菌を用いた水質浄化活動」については、プトラ大学の学部生が飛び込みで発表してくれました。
この学生は私たちと同じ年齢だったのですが、流ちょうな英語で、原稿も何も見ずに発表を行いました。マレーシアの母国語(マレー語)ではないので、英語力は日本人の自分たちと大して変わらないだろうと高をくくっていたので、これはかなり衝撃的でした。やはり私も英語やらなきゃダメですね。環境問題とは、地球全体の問題です。
日本もマレーシアも、その過程こそ違え、ゴミの分別やエコバッグの利用など、行っていることはほとんど変わりません。すべての人が自分ができることを考え、実行していくことが、地味ですが最も大切なことだと今回の研修で改めて実感しました。
経済格差の問題を目の当たりにしました。
小田原啓太さん(経済学部2年)
私は今回の研修で日本とマレーシアにある経済格差の問題を目の当たりにしました。「経済の発展と環境問題の解決」は正反対のものであるといわれています。なぜ経済を発展させつつ、環境問題を解決する方法がないのかずっと疑問をもっていました。
マレーシアではアブラヤシのプランテーションや森林伐採により、土地を追われた民族を見ました。そこで見たものは、環境問題を考える以前に、「人々が生活するために、森林開発やプランテーションが行われている」現状でした。
日本では企業や一般の人々が環境問題を意識する機会が多いと思います。一方、マレーシアはごみを分別する習慣や環境問題を考える人々が少ないように感じました。
そしてマレーシアでなによりも強く感じたのが、プトラ大生の勉強へ取り組む積極的な姿勢と学生一人一人のモチベーションの高さでした。日本の大学とは授業が想像以上に異なり、まさにゼミといった印象を受けました。
マイボトルの普及率の高さも強く感じました。これはマレーシアが赤道直下の熱帯気候であることも関係すると思いますが、「持っているのが当たり前」という感覚で使用されていました。
多くの自然を犠牲にしていると思うようになりました。
新川竜悠さん( 環境施設部職員)
ボルネオ島で飛行機に乗ったときに、窓から見渡す限り原生林が続いているなぁ、と思っていたら飛行機が向きを変えると、反対側にはアブラヤシのプランテーションと木材伐採が同じように見渡す限り続いていたことに驚きました。アジアに自然がこれだけ残っていることに感動すると同時に、我々先進国の要求によって引き起こされた自然破壊の現状を目にしました。
この現状を見て、現在の便利になった生活を続けていくためには、多くの自然を犠牲にしていると思うようになりました。そして、日本で普通に生活していることによって、決して目が届かないどこかで意図せずに自然破壊を引き起こしていることを理解しなければならないと思いました。油を使えばアブラヤシのプランテーションが大きくなり、家を建てれば木が伐られ、靴を履けばゴムのプランテーションが・・・直接破壊をしていないだけでどんな人であっても意図せずに自然破壊をしているのに等しいと思いました。
人類が生きていくことによって、自然が破壊されることはどうしても避けられないことでしょう。ただ、そんな中で自然がすぐに復元できないところは植林をしたり、少しでも環境負荷を少なくするために自然エネルギーを検討したり、ちょっとでも地球にとって負荷を少なくすることが、これから大事になると思いました。
環境教育海外研修の報告会が開催されました
平成23年6月27日松本キャンパスにて、今回の環境教育海外研修の報告会が開催された。会場には約220人の学生・教職員が詰めかけ、研修に参加した4人の学生・職員による報告を熱心に聞き入っていた。アンケートによる質疑応答では、「シャワーが無いということだが女性はどうしていたのか?」といったユニークな質問から、「信州大学側のプレゼンテーションに対するプトラ学側の反応はどうだったのか?」などの質問もあり、今回の海外研修に対する関心の高さがうかがえた。
| 2月27日 | 成田泊 | 3月5日 | ビンツル→ミリ:アブラヤシ・プランテーション見学 |
| 2月28日 | 成田→クアラルンプール(マレー半島) | 3月6日 | ミリ→ムル:グヌン・ムル国立公園(世界自然遺産)見学 |
| 3月1日 | プトラ大学工学部 | 3月7日 | ロング・イマン訪問:狩猟採集民(プナン人)集落ホームステイ |
| 3月2日 | プトラ大学環境学部 | 3月8日 | ロング・イマン→ムル→ミリ |
| 3月3日 | クアラルンプール→ビンツル:プトラ大学ビンツル校農業食料学部 | 3月9日 | ミリ市役所:ごみ埋め立て(最終)処分場見学、環境施策聞き取りミリ→クアラルンプール |
| 3月4日 | プトラ大学ビンツル校農業食料科学部 | 3月10日 | クアラルンプール→成田 3.11着 |

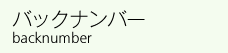
 平成26年度環境教育海外研修報告
平成26年度環境教育海外研修報告エネルギーの行方。資源産出国「タイ」で学ぶ環境と資源
 第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト
第1回地元酒造業者支援スピーチコンテスト若者の日本酒離れに歯止めをかけ、地域の酒造メーカーを支援しよう
 多様化する金融犯罪とどう向き合うか
多様化する金融犯罪とどう向き合うか―関東財務局・長野県警との連携特別講義、経済学部で開催―
 グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力
グローバル卒業生に学ぶ社会人基礎力現地の声を聞き、外の世界に目を向ける
 信州大学環境教育海外研修(6)
信州大学環境教育海外研修(6)開発途上国が抱える環境問題―ネパールを訪ねて―