

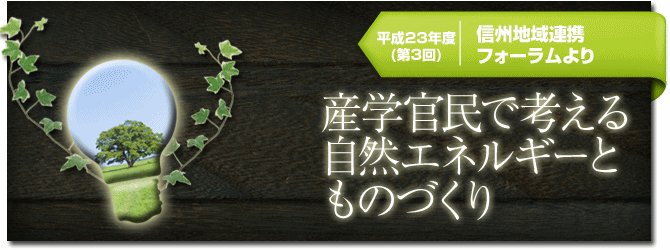
再生可能な自然エネルギーを様々な方面から考える信州大学地域連携フォーラムが3月17日、信州大学工学部(長野市)で開催された。 この地域連携フォーラムは毎年ホットな学術テーマをめぐり、キャンパスを変えて開かれる。3回目となる今回のフォーラムをレポートする。
 会場には多くの方が参加した |
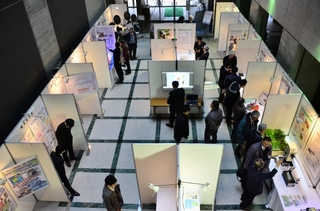 会場前のロビーではさまざまな展示も行われた |


東日本大震災・長野県北部地震から1年が経ち、世間ではエネルギーに対する注目が高まっている。特に、原子力発電所が全機停止中にあることもあり、今後のエネルギーを見直す時期だとの考えのもとに、今回は「自然エネルギーを活かした私たちの暮らし」をテーマにした。工学部天野良彦教授が開会宣言を受け、山沢清人信州大学長が「将来を見通して、長野らしいエネルギー政策を議論する場になってほしい」と語ってフォーラムは開演。
基調講演Ⅰでは、NPO 法人環境エネルギー政策研究所の松原弘直主席研究員が「自然エネルギーへの大転換」と題して各地の事例等を紹介した。続いて、基調講演Ⅱでは関東経済産業局の斉藤雅昭課長補佐が今年の7月から始まる「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」について、今後の展望と課題について講演を行った。昼休みには、4つの研究室を公開し、見学者は50名に上った。
午後からは、長野県内の自然エネルギーや環境への取組みについての事例報告が行われた。フォーラムの最後には信州大学地域共同研究センター副センター長の松岡浩仁准教授が先進地域の視察報告として、現在の「国内におけるスマートコミュニティ構想」を紹介。
最後に三浦義正副学長が「エネルギーのもとは色んな所にあります。それを生かしていくには、それぞれの取組みが重要です。大学に出来る事と、出来ない事がありますが、企業や地域の人と共に共同していきたい」とまとめた。地域住民をはじめ企業や行政などから総勢150名が参加し、長野県、ひいては日本のエネルギーの今後を考える場となった。
基調講演Ⅰ 自然エネルギーへの大転換
NPO法人 環境エネルギー政策研究所
主席研究員 松原 弘直氏

松原氏は「世界で今、何が起こっているのかを考える必要があります」と切り出した。地球温暖化が進み、世界各地でハリケーンや干ばつなどの異常気象が起こっている。それにも関わらず、世界のCO2排出量は増加の一途をたどっている。石油の生産量が今後減少していくのも明白。「化石燃料の価格は今後も上昇し続けると予想出来ます」と松原氏は話す。特に日本では、化石燃料のほとんど輸入に頼っている状態にあり、エネルギー自給率はたったの4%。「今後、再生可能な自然エネルギーへのシフトが必須なのです」。
明るい兆しもある。欧州などでは自然エネルギーが加速的に増えてきており、自然エネルギー市場は爆発的な成長を続けている。松原氏は「長期的なビジョンで持続可能な社会の姿を想定することが大切。そこから現在を振り返り、今何をすればいいかを考える。つまりバックキャスティングしていくことが重要です」と語った。
しかし、日本の自然エネルギー市場には課題や制約も多い。まずは電力会社の系統制約や技術的な課題がある。また鳥や景観、低周波といった社会的課題もある。それらをクリアしていくためにも「国内外の動向や成功事例を知り、環境エネルギー政策やエネルギー需給の仕組みを見直す必要がある」と締めくくった。
基調講演Ⅱ 再生可能エネルギーの固定価格買取制度について
関東経済産業局 資源エネルギー環境部エネルギー対策課
課長補佐 齋藤 雅昭氏

2012年7月1日から「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」が始まる。固定価格買取制度とは、再生可能エネルギー源(風力、太陽光など)を用いて発電された電気を、一定の期間、固定価格で電気事業者が買い取る事を義務づける制度である。この自然エネルギーの買取費用は電力を使う国民が賦課金として全国一律で負担する。
齋藤雅昭課長補佐は「日本は化石燃料への依存度が非常に高く、化石燃料の輸入を減らすため、再生可能エネルギーの振興は重要だ」と話す。現在、日本の電力の約9割は火力発電で賄われている。再生可能エネルギーは、全体の10%に満たない。更に、水力発電を除くと約1%しか残らないという。この制度が始まる事で「再生可能エネルギーによるビジネスを考えている事業者が計画を立て易いというメリットがあります」と言う。しかし、再生エネルギーの普及には規制や制度上の課題も多くある。例えば、農地等を転用することへの制限やコスト面、技術面などでもまだまだ改善、発展していく必要がある。
だが、再生可能エネルギー事業が増えていく事で、CO2排出量の減少や国内の自然エネルギー産業の振興に繋がることは間違いない。「再生可能エネルギーによる発電をきっちりと安定供給化し、電力の柱として位置づけられるようにしていきたい」とまとめた。
他地域に真似の出来ない
信州型のスマートコミュニティを創ろう
フォーラムの最後に、信州大学地域共同研究センター副センター長の松岡浩仁准教授が、先進地視察報告として、現在のスマートコミュニティ構想 の実証地域として神奈川県横浜市、愛知県豊田市、けいはんな地区、福岡県北九州市を紹介。そして他地域に真似の出来ない信州型のスマートコミュニティが出 来るのではないかと提言を行った。

「スマートコミュニティというのは、家庭やオフィス、商業施設など全体のエネルギーの最適利用を地域レベルで進めよう、という考え方です」と松岡准教授。つま り、スマートグリッド(次世代送電線網)を用いて、供給側と需要側のミスマッチを減らしていくということだ。本来であれば足りる筈の電力が、夏場の冷房や 冬場の暖房など、ある時間帯に集中してしまうことで、足りなくなってしまう。その需要の部分をIT技術によって平均化することで、電力の無駄を無くす。こ のスマートグリッドには、エネルギーマネジメントシステム(EMS)というものが重要であり、EMSはエネルギー消費機器をネットワーク化し、自動制御す る働きを持っている。
このスマートコミュニティには大きく4つの狙いがある。
1つ目はエネルギーの「見える化」である。スマートメータを使い、太陽光による発電量や家庭内のエネルギー使用量を目に見える形にすることで、利用者が省エネの取り組みを積極的に行うように促す。
2つ目は、最適なエネルギー管理である。電力の優先順位をつけ、電力が余っている時間に不要不急の家電製品などを動かすという考え方である。
3つ目は、機器単位から地域単位へ変えていく取り組みだ。機器単位の省エネ化は進んでいるが、これを家単位で考え、家庭内のエネルギー利用を効率化していく。そして更には、地域単位でのエネルギーの最適化を図っていく。
4つ目が需要と供給側と需要側が対話するということである。エネルギーの過不足を需要側に伝え、エネルギーの節約を促し、余っている部分で、出来る事をやるという仕組みである。
しかし、これらはITで管理するため、「セキュリティ面などで課題もある」と松岡准教授は話す。
広域大都市型である横浜市スマートシティプロジェクト(YSCP)は、横浜市と民間企業が協働し、再生可能エネルギーやエネルギーマネジメント等に取り組ん でいる。けいはんな学研都市では、関係大学・企業・行政が共同で研究を行い、様々なエネルギー使用主体と新たなエネルギー供給設備をネットワーク化するこ とで、安定的・効率的なシステムの確立を目指している。豊田市実証住宅においては、HEMS(Home EnergyManagement System)によって、家庭内の太陽光電池、エコキュート、EVやスマート家電をつなぎ、家庭単位での電力需給や機器制御の最適化と見える化を実施して いる。
北九州市は季節や時間帯に応じて電気料金の単価が変動する「ダイナミック・プライシング」という考え方を日本で唯一取り入れている。これは、系統電力に頼らず、新日本製鐵が出資し、運転管理に携わる東田コジェネが発電した電力供給によって実現した。
長野県には、水力や風力など自然エネルギーが数多くある。小さな範囲でもマイクロ水車などを活用出来る場所が沢山ある。そういったものを取り入れていくこと で、「他に真似が出来ない長野県らしいスマートコミュニティに繋がっていくのではないでしょうか」と松岡准教授は話した。エネルギーの使い方、使われ方と いう点も都市と長野県では違う。そういった違いを生かしていくことが重要。
節電というのは、個人の努力で出来る。しかし、それ以上となる と全体を俯瞰するところが必要になってくる。それを日本の得意なITでやっていく必要がある。「今のように、無駄を背負って歩いている状態でいいのだろう か。勇気を持って無駄を変えていく必要がある。それを考えるのに“今”というのは良いときなのかもしれない」と松岡准教授が力を込めた。そして「参加者に とって、今回のフォーラムがこれからの生活を考えるきっかけになれば嬉しい」と締めくくった。
 事例報告Ⅰ 長野県内における協働による自然エネルギーの普及
事例報告Ⅰ 長野県内における協働による自然エネルギーの普及自然エネルギー信州ネット 事務局長 宮入 賢一朗氏
 事例報告Ⅱ 再生可能エネルギーで地域を元気に!
事例報告Ⅱ 再生可能エネルギーで地域を元気に!須坂市産業コーディネーター 山口 光彦氏
 事例報告Ⅲ 諏訪湖畔の味噌工場における自然との共存
事例報告Ⅲ 諏訪湖畔の味噌工場における自然との共存タケヤ味噌 株式会社竹屋 取締役社長 藤森郁男氏

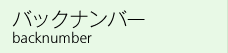
 "辛口"研究で地域を熱く!とうがらしWORLD
"辛口"研究で地域を熱く!とうがらしWORLD季節の七味シリーズ「信州七味」
 多様な連携協力を可能にして地域の保健活動を推進
多様な連携協力を可能にして地域の保健活動を推進医学部地域保健推進センター
 進化したインターバル速歩 i-Walkシステム
進化したインターバル速歩 i-Walkシステムビッグデータで予防医学の未来を変える遠隔型個別運動処方システム「i-Walk System」が登場!
 技術シーズ展示会2014
技術シーズ展示会2014”気づき”を新しいカタチに
 信州の「知の森」を歩く「第1回 信州大学見本市 ~知の森総 合展2014~」開催
信州の「知の森」を歩く「第1回 信州大学見本市 ~知の森総 合展2014~」開催信州大学の研究効果、一挙公開