

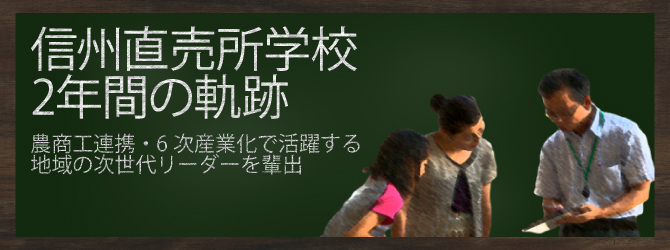
農商工連携・6次産業化で活躍する地域の次世代リーダーを輩出
信州大学では平成22―23年度の2年間にわたり、農商工連携・6次産業化を進める次世代リーダーの育成を目指して、信州直売所学校を開校してきた。※
産学官連携推進本部地域ブランド分野が中心となり、長野県農政部・長野県産直直売連絡協議会・JA長野中央会・長野大学・松本大学の教員等とも協力して進めてきたこの事業では、農家や、農業との連携を目指す企業の方、また行政や教育関係者などに広く門戸を開放し、2年間で延べ80人のキーパーソンを育ててきた。
2年目終了の節目にあたり、その成果と意義を振り返る。(文・毛賀澤 明宏)
※中小企業庁が所管し、全国中小企業団体中央会が統括する「農商工連携人材育成事業」の採択を受けて実施した。


安曇野市の豊科交流学習センター「きぼう」で3月10日、今年度の信州直売所学校の修了式と修了生による活動事例の報告会が開催された。
定年を機に東京から信州にIターンして小さなジャム工房を立ち上げ、地元農家との協力関係を模索する団塊世代の男性。松本市奈川の直売所を運営し、直売所学校で巡り合った人々と連携を深めながら地域おこしに力を入れようとしている若い女性。直売所学校で学んだことを活かし、昨秋より農水省の6次産業化プランナーとして活躍している女性。そして、遠く和歌山から信州に通いながら、障害者施設が運営する直売所を立ち上げ、活発に事業を展開している男性…など。報告に立った修了生は、皆、熱い思いを込めて活動状況を報告し、今後の事業計画を語った。
今回活動報告を行ったメンバーだけではなく、修了生のほとんどが、直売所学校での研修内容を活かして、それぞれの地域と持ち場で新たな事業活動を開始している。直売所や加工所の立ち上げや改善のサポート、各種新商品開発と販路拡大。福祉の領域に複合化した農業を持ちこむ「農福連携」の模索…、平成22年度の第1期に続き、第2期も、信州直売所学校は、新たな・若々しい農商工連携・6次産業化の事業の種と、それを進める人々を大量に創出したのである。

平成23年度の第2期信州直売所学校は、春、受講生を公募したところ、定員を大幅に上回る80人もの応募があり、厳正な書類審査等を経て40人の受講生を決めた。
そのうち、直売所や加工所の開設を希望する等の農家が25%、直売所や加工所の運営者・スタッフが25%、連携コーディネーターへのスキルアップを目指す人や関連事業への就職を希望する学生などが25%、そして農商工連携・6次化を進める中心的役割を担おうとしている行政関係者や高等学校の教員・NPO等関係者が20%。UIターン希望者が5%(以上概略)。―。
この受講生が、およそ半年間で、開講日10日、講義および実習で31単元の研修を経て、現場で事業を牽引するキーパーソンとして巣立って行った。
平成22年度の第1期でも、同じく定員を大きく上回る応募者から選ばれた40人が受講したが、初めての試みということもあり、直売所への農産物出荷を希望する農家や、加工事業に着手するためのイロハを学びたい女性など、いわば基礎的知識と経験の習得を目指す受講生が多かった。これに比して、第2期は、「応用編」と位置付けた関係もあり、より明確に農商工連携のキーパーソンや6次産業化のコーディネーター、直売・加工事業の牽引者になることを意識的に目指す受講生が多かった。
そして、受講生が、農水省認定の長野県6次産業化プランナー(4人)の1人として活躍していることに象徴されるように、「応用編」にふさわしく、次世代リーダーの育成に大きな成果を得ることができたと言えよう。

受講生が、研修修了後ただちに―いや、研修中からも―、それぞれの持ち場で新たな実践的試みを開始できたのは、受講生の目指す課題が明確であったからである。だが同時に、直売所学校の研修プログラムがきわめて実践的だったことによるところも大きい。
実際、本事業では、この種の人材育成事業にありがちの農業経営学や農業経済学、また加工学やマーケティング理論などの座学による研修にとどまることなく、長野県の活発な直売所や加工所の現場の経験に学ぶことを心がけた。県内各地の直売所8カ所の客層分析や店舗運営の評価・検討を行い、運営者と意見交換をする実地研修にも取り組んだ。
農産加工については、「農村受託加工」というビジネスモデルを初めて構築した下伊那郡喬木村の小池芳子氏の経験に学んだ。そしてそれを基に、新たな展開をもたらす可能性が高い酵素技術を応用した加工法を工学部天野良彦教授から指導してもらい、実際にそれを活用した試作品も作った。受講生の中の有志は、課外活動として、この試作品を実際に商品化して、テストマーケティングまで行ったメンバーもいたのだ。
その他、伝統野菜や特産トウモロコシを活用した農業振興、伝統文化を活かした地域づくりの視点などを信州大学の教員が話し、受講生の取組みの質的高度化に資した。新商品開発、地域振興の戦略構想、直売所ネットワーク形成の必要と方向性などについても、長野大学、松本大学、首都圏在住の専門家などを招いて研修した。
農商工連携・6次産業化に関わる実践と理論。この両者を融合し、実践に理論を適用することで実践の高度化を図り、理論を実践で検証することによって理論の高度化を図る―このようなプログラムの構成が効果を発揮したということができよう。
信州直売所学校のもう一つの特性は、この人材育成事業の場そのものが、農・商・工の、そして産・学・官の新しいネットワーク形成の場として大きな役割を発揮したことである。
先に述べた工学部天野教授の下での加工技術の研修は、加工の新技術を求める人々の新たなつながりとなって動き始めている。伝統野菜や在来品種の選抜に関わる農学部大井美知男教授や松島憲一准教授の講義は、地域資源開発と地域おこしの新たな連携の輪を広げている。
また、受講生の中の障害者福祉に関わるメンバーが直売所や加工所との連携を広げたり、同じく受講生だった農業高校の教員の方々が、県内大学の教員とのつながりや、地元農家や直売所との協力関係を構築したり―というように、受講した一人ひとりが様々な人的ネットワークを広げ、活躍の領域を拡大して行ったのである。もちろん、その輪は、第1期の修了生にも広がり、第1期、第2期合わせて総勢80人の修了生を核にして、新たな胎動が生まれようとしているのである。
このような実践的なネットワークの形成が可能になったのは、そもそも、本人材育成事業の推進に当たり、信州大学を中心にして、長野大学や松本大学(松商短期大学部)の教員等が参加し、長野県、長野県産直直売連絡協議会、JA長野中央会という関連諸機関が共同して運営委員会を構成してきた、その連携の力が深部にあったからに他ならない。
こうした成果を教訓と引き継ぎ、信州直売所学校はさらに新たなステップアップにむけて準備を進めている。

松本市ながわ山菜館店長 一志 千春さん
奈川地区は平成17年の松本市との合併以降も人口減少が進み、高齢化率は40%以上。この地で直売・加工施設を運営するのは、農業振興と雇用の確保のためですが、山深い地でもあり困難が多いです。直売所学校で学んだことを活かし、知り合った人々の力も借りて、「ながわ山菜館友の会」の充実や、特産行者ニンニクを使った新商品の開発を進めています。「人と人の交流の場」、「ただモノを売るのではなく商品を介して気持ちが行き交う場」として直売所を発展させていきたいと思います。

佐久市 ジャム工房「ル・コタージュ」 依田 守正さん
定年退職後に横浜から佐久市駒込の山間集落に引っ越し、妻と二人で小さなジャム工房を立ち上げました。右も左も分からずいたところ、県から信州直売所学校の紹介を受け、受講しました。そこで、様々な知識、人脈、出張販売の経験等を得、それを活かして、今、駒込地区の農家の方々と共に、近くにある荒船別荘地の皆さんに野菜や果物・花等を共同販売するグループづくりを始めたところです。自分のジャム工房で使う素材の提供もお願いしています。「よそ者」だからできる地域への貢献を考えたいと思います。

和歌山県 社会福祉法人一麦会(麦の郷) 柏木 克之さん
和歌山県から通わせてもらいました。麦の郷は12年前から農福連携に取組んできました。障害を持った皆さんが進める事業として、地域の農水産物を活かした食品加工業を進めてきたのですが、農業生産への協力もしくは参入、さらに直売所・食堂・宿泊所の開設など、複合化の必要性を感じて信州直売所学校の門を叩いたのです。いろいろ教えていただき、昨年8月に直売所を開設。これをステップに、外部経済に振り回されない安全安心の生活圏と、障害を持った人の職場の確保をさらに進めたいと思います。

長野市 農水省6次産業化プランナー 田中 裕子さん
長野市のリンゴ農家の出身です。8年ほど前まで東京で販売関係の仕事をしていましたが、労多くして益の少ない親の姿を見て、農業をもっと実り多い仕事にしないといけないと思い帰省しました。ネット通販等の農業ビジネスに挑戦したのですが、甘いものではありませんでした。同じ志を持つ人のネットワークが必要であり、その人たちと一緒に成長し、実際に仕事を進められ生きた交流を作ることが重要です。直売所学校はその格好の場で、6次化プランナーとして活動する現在も、私の大きな支えになっています。


信州大学農学部卒業 柳澤 愛由さん 奥田 悠史さん
もともと農業に関心があり、農に生きる方々のレポートなどをしてきましたが、直売所学校に参加して、大きな可能性を感じました。農業、地域(田舎)への見方や考え方、偏見を根底からひっくり返し、農業や地域は面白い!という大きなうねりを作り出したい―これが私たちの思いです。縁あって、今春から、直売所と小さな農業の情報発信をする産直新聞の発行に本格的に携わることが決まり、そこを拠点にして、全国の同じ志を持つ若者のネットワーク作りを進めたいと考えています。よろしくお願いします。

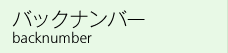
 "辛口"研究で地域を熱く!とうがらしWORLD
"辛口"研究で地域を熱く!とうがらしWORLD季節の七味シリーズ「信州七味」
 多様な連携協力を可能にして地域の保健活動を推進
多様な連携協力を可能にして地域の保健活動を推進医学部地域保健推進センター
 進化したインターバル速歩 i-Walkシステム
進化したインターバル速歩 i-Walkシステムビッグデータで予防医学の未来を変える遠隔型個別運動処方システム「i-Walk System」が登場!
 技術シーズ展示会2014
技術シーズ展示会2014”気づき”を新しいカタチに
 信州の「知の森」を歩く「第1回 信州大学見本市 ~知の森総 合展2014~」開催
信州の「知の森」を歩く「第1回 信州大学見本市 ~知の森総 合展2014~」開催信州大学の研究効果、一挙公開