


昨年8月に行われた全国国公立大学卓球大会で活躍し、国公立大学卓球連盟の海外遠征に16名の選手のひとりとして派遣された北川さん。3月10日に日本を発ち、ハンガリーのブダペスト(11日~14日)、ドイツのデュッセルドルフ(15日~19日)でトレーニングと試合をこなしてきた。卓球で初めての海外はいかに。世界を肌で感じた体験を語ってもらった。

ブダペストの大聖堂(観光) 
ブダペストの練習場 |
日本を発った翌日からハンガリーでのトレーニングが始まり、北川さんはハンガリーの代表選手らから直接コーチを受けることができた。多球練習(コーチが次々とサービスを繰り返し、ひたすら打ち返す練習)など、かなりきつい練習や地元選手との交流試合を通し、北川さんは初めて“体格の差”を感じたという。
「威圧感もありますが、ボールの伸び方、強い回転がかかりながら加速してくる感じは、体格をうまく使った打ち方だと思いました」
北川さんはどちらかというと小柄な方だが、日本では体格の差を感じたことはなかった。
強い回転というのは、打球に回転をかけるドライブという技で、ヨーロッパではこれを多用する「ドライブマン」タイプが主流だ。ラケットに貼るラバーもドライブをかけやすい裏ソフトという表面が平らになっているものを両面に使う。
一方、北川さんはバレーのスパイクのように叩きつけるスマッシュを得意とし、ラバーも片面は回転をころせるよう表面がつぶ状(表ソフト)のものを使っている。ヨーロッパでこのラバーを使う人はほとんどいないそうだ。北川さんは、かの福原愛ちゃんと同じく、「前陣速攻型」と呼ばれるタイプになる。
ほかにも、日本と違った特色がある。日本ではフォアハンド(ラケットを持つ側に来るボールを打つこと)が得意な選手がほとんどだが、ヨーロッパの多くの選手はバックハンド(ラケットを持つ側と反対)を得意とする。相手にとって返しにくいボールを打ったつもりが、お茶の子さいさい戻ってきてしまうのだ。
実は出発前にそんな話を聞いていた北川さんは、今回の派遣で「自分の卓球が通用するのか」を試そうと考えていたという。結果は「意外と通用した」し、練習も問題はなかったが、あえていうと「不合格」。やはり勝つためにはヨーロッパと日本のタイプを超越する技術がなければならない、そうでなければ世界では戦えないのだ。

ドイツで印象深かったのは、卓球プロリーグ、ブンデスリーガ観戦。
2013年4月に国際卓球連盟が発表した卓球男子チームの世界ランキングでは、1位中国、2位ドイツ、3位は韓国で、4位が日本。日本も結構強く、ドイツより上位になることもあるのだが、なんといってもドイツにはプロリーグ、ブンデスリーガがある(サッカーでよく知られているが、バスケットや卓球などもある)。
ブンデスリーガは、ヨーロッパやアジアから強豪選手が集まるという世界最高峰のリーグだ。会場はテレビ中継されて、観客は中央に置かれた1台の卓球台を取り囲むように見入る・・・その熱気はすごい。会場の外にもモニターが設置され、焼きソーセージをかじりながらビールを飲み、大勢の人が歓声をあげている・・・この盛り上がりよう・・・。
北川さんは試合そのもののレベルの高さはもちろんだが、それを取り巻く環境の、日本とはあまりに大きな違いに圧倒されてしまった。

遠征を終えて、北川さんはあらためて自分の卓球人生の進む先を考えた。
「ヨーロッパに通用するよう、タイプを超越することを考えるより、まずは日本です」
今回の遠征で「練習方法も参考になるものがありましたし、ドライブは上達しました」。それはそれで参考にして、スマッシュを得意とする「自分なりのスタイル」を崩さずに磨きをかけたいという。
小学生のころ、趣味で卓球をしていた父親に教えてもらったのが卓球人生の始まりで、それから中学、高校、大学と卓球を続けて積み上げた“北川スタイル”がある。
「コーチと一緒につかんだものを信じて、自分にしかできないものを追求していきたい」
海外遠征を経て話す北川さんの言葉には信念がこもっている。その横顔に、未来へ向かってまっすぐに進んでいこうとする確かなものを感じた。
 トレーナーとの記念写真(ブダペスト) |
 遠征の仲間たちと |

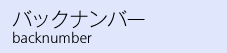
 倉田 紗耶加さん(大学院農学研究科 )
倉田 紗耶加さん(大学院農学研究科 )トビタテ!留学JAPAN 日本代表プログラム 選抜
アメリカのキノコ会社でインターンシップ
 人文学部4年 小嶋諒さん
人文学部4年 小嶋諒さん「気障でけっこうです」で小説家デビュー
 理学部2年 中嶋徹さん
理学部2年 中嶋徹さん世界で注目されるクライマー
第68回国民大会本大会「スポーツ祭東京2013」
山岳競技、リード優勝、ボルダリング2位!
 信州大学YOSAKOI祭りサークル「和っしょい」
信州大学YOSAKOI祭りサークル「和っしょい」 悲願の「どまつり大賞」を受賞!
心ひとつに よいてぇこしょ~!
 北川篤史さん(工学部4年)
北川篤史さん(工学部4年)卓球で海外遠征!
自分なりのスタイルを追求したい