


[農学部教授] 昆虫生態学
1950 年 京都市生まれ
1974 年 京都大学農学部卒業
1976 年 信州大学大学院農学研究科修士課程修了
1978 年 瀬戸内短期大学専任講師(助教授、教授歴任)
1999 年 信州大学農学部教授
2002 年 信州大学農学部付属アルプス圏フィールド科学教育研究センター長
2008 年 信州大学農学部図書館長
2012 年 信州大学評議員
・・・環境報告書2014より

長年にわたり生物多様性の保全や絶滅危惧種の保護に取り組んできた。昆虫の種類や個体数を調査・解析し、群集全体から環境の変化を評価するという目下のテーマも、自然と人の共生を探るための指標となるもの。
環境評価のなかでも物理的・化学的な方法は機械で測定ができ、定量的で比較しやすいが、測れるのは1つのファクターだけに限定される。一方、指標生物をターゲットにその増減を測定すると、複合的なファクターがとらえられる。特に体が小さい昆虫は環境の変化に敏感で、翅を持ち飛ぶことができるので、環境評価に有利な方法とされている。
たとえば、温暖化の指標生物である南方系のクロコノマチョウは、30年前まで長野県内には生息していなかったが、最近は南信エリアでも見られるようになっており、確実に温暖化が進んでいるとわかる。「生物から発せられる“危機的な状況にある”というメッセージをわかりやすく伝えることが大学人としての使命」と中村教授はいう。

研究の中でも特に高い評価を得ているのが、昆虫の増減を調査して数値化し、複数の要素をレーダーチャートにすることで環境変化が判断できるRI(Rank Index)指数という手法だ。それを進化させたグループ別RI指数法は、調査数をランク指数に変換することで、調査者のスキル、天候といった不確定な要素の影響を受けづらくなり、正確性が高まるという実用性の高いもの。いろいろなフィールドに応用できるのも特徴で、アセスメント会社からの問い合わせも多く、海洋性生物に利用したいという要請もあった。大学のホームページで一般にも公開されているが、ダウンロード数は飛び抜けているという。この研究が評価され、2012 年に日本環境動物昆虫学会賞を受賞した。
ヒメギフチョウとギフチョウが混生する稀少な環境を有する小谷村からは、天然記念物指定のための調査を依頼され、子どもたちへの授業や公民館での講演なども行った。「声高に叫んでも環境は守れません。なぜ保全が必要か理解し、納得してもらうこと、そして実情にあわせた的確なアドバイスが必要です。たとえば“農薬もだめ、圃場整備もだめ”と噛みつかれたら、農家だってたまらないでしょう。新しい農業技術を導入して生産性を上げながら、絶滅危惧種と共存するための方法や技術を一緒に考えていこうという姿勢が保護につながるのです」

国内外の調査のかたわら、生物多様性長野県戦略策定委員長をはじめとする県の要職に就き、地域の人々と一緒にチョウの保護活動に奔走しながら、幅広いネットワークを築きあげてきた。いまは、生物多様性・絶滅危惧種保全の中心となるハブ組織をつくろうという県のプロジェクトの推進役を担っている。県内各地で活動する環境系のグループは多数あるが、連携はできていなかった。縦横につながりながら情報を受発信できる組織をつくり、ホームページを立ち上げて、積極的に活動していきたい。「“保全生態学”のような研究はもちろん必要で大切だが、いままさに絶滅しそうな種がいるときは、とにかく動くこと。役所や土地の所有者や地域の人々と話し、行動する学問が必要。“臨床保全学”を、いつか確立させたい」という中村教授らしい、アクティブで柔軟な組織になるだろう。
「絶滅危惧種が増え続ければ生態系が崩壊して人間が消え、ゴキブリとネズミだけの地球になるかもしれない。そういう転換期に地球の生態系はあると思います。絶命危惧種や多様性を守れるのは人だけ。結局のところ、人間が意識を変えていくしかありません」
人間の活動によっていくつもの種が滅びる状況を目の当たりにしてきた人の、穏やかに語られる言葉は重い。
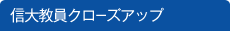
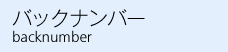
 学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授
学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授「環境文学」による環境教育プログラム
 学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授
学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授昆虫群集による環境評価
 飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授)
飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授) 流れに置くだけのEco水車
 中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)
中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)「地下水の可視化」に取り組む
 関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)
関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)環境負荷低減と生産コスト減を同時に実現する「マテリアルフローコスト会計」