


子どもにスポーツの楽しさを教える「運動遊び」の第一人者。10年間も続く教育学部の公開講座「リトルスーパーマン体操教室」や、長野市教育委員会などが主催するNAGANOスポーツフェスティバルの「親子でのびのび運動あそび教室」をはじめ、テレビなどにも度々登場する、知る人ぞ知る信大の名物教員だ。
日本経済新聞社が発行する子育て世代を対象にした雑誌「日経Kids+(ぷらす)」で「スキップの教え方」を手ほどきしたこともある。
―そんな渡辺敏明准教授に研究の特徴と目的を聞いた。
プロフィール:1962年高知県生まれ。1988年筑波大学体育研究科修了(体育学修士)コーチ学(スポーツ運動学)。筑波大学体育センター文部技官を経て、1989年信州大学教育学部助手、2005年准教授。
・・・・・ 信州大学広報誌「信大NOW」第67号(2011.1.25発行)より

子どもにスポーツの楽しさを教える―と聞けば楽しそうに思えるが、実に奥深い研究が必要な領域なのだという。
「学校体育において、子どもの体の動きをうまくさせてやりたいというのはどの教師にも共通する願いでしょう。しかし、そこが難しい。うまくできずにスポーツ嫌いになる子どももいれば、それで頭を抱えてしまう教員も多いのです」と話す。
例えば、同じ授業を受けていても、身のこなしがうまくどんどん上達する子どもがいる一方で、ぎこちない動きのままの子どももいる。その根拠は何で、どうすればその差を克服させてあげることができるのか?―このように問題を立てた瞬間に、その難しさが浮かび上がる。
良くある悪いパターンは、大人のトレーニングの子ども版をつくり、それを与えて練習させること。あるいは、完成された動きを提示して、それに近いものができるように繰り返し反復させること。しかし、身のこなしが「巧み」であるということは、教わったり練習したりする中で、自分のできる動きを、自分で質的に向上できるということであり、その「自分のできる動き」、つまり「動きのもと」を子どもたちに育むことなしには、上達する子と、しない子の差は決して埋まらないのだ。

「重要なのは、無意識的であっても、こんな風にやるのかなと、過去の経験から類似する動きの感じを呼び起こして試行錯誤できるようにしてあげることなのです」と渡辺准教授。
かつて子どもは、学校の体育の授業以外でも、日常的に野原を駆け回り、木に登り、石を投げたりして、スポーツでの体の動かし方に適用・発展できる類似経験を積んでいた。しかし、子どもを取り巻く環境は大きく変化し、経験的に身に付けた身のこなし方のパターンはかなり貧弱になっている。
そこで、特定のスポーツ種目の動きに直接結びつかなくても、それに役立つことのできる「動きのもと」を含んだ運動遊びが重要になってきているというわけだ。
例えば、3メートルほどの間隔で引いた2本ラインの中央に2人の子どもを立たせ、左右に動いてどちらかのラインに両手でタッチする「攻め」と、それ以前にラインを踏むことを目指す「守り」でゲームをさせる。この遊びで体得する動きは、ボールゲームなどで行なうフェイントの類似体験になる。
あるいは、スーパーなどのレジ袋に新聞紙を詰め込んだ「ゴミゴミボール」でキャッチボールやキックパスの遊びをさせる。これは、まだボールの早い動きにはついていけない子どもに、ボールを扱う身のこなしを育む。
このような「動きのもと」を含んだ運動遊びを考案し、それを子どもと一緒に「楽しく」進めることで、「身のこなし方」を教えることができる教員を増やして行きたい。それが渡辺准教授の目指すところだ。

その教育現場における実践的意義は高く評価されており、専門誌「小学校体育ジャーナル」(学研)にも「基本の運動で使える楽しい運動遊び」をシリーズで連載している。
筑波大学に学んだ学生時代は、体操競技に打ち込み、ナショナルチームの強化指定選手として練習に励んだ経験を持つ。その経験を元にスポーツコーチ学を学び、1989年より信大教育学部に勤務した。だが、「自分では噛み砕いて説明しているつもりでも何も学生に伝わらない限界に直面した」という。
その後、スポーツ科学の本場、ドイツのテュービンゲン大学に留学する機会があり、教える者と教えられる者との関係性において、スポーツ運動の伝承の仕方を考察する現在の現象学的運動科学の視点を獲得したと話す。
子どもの身体能力・運動能力の低下が指摘される現在、教育現場から求められる喫緊のテーマは、実践的回答のみならず深い学問的基礎付けが求められているのである。
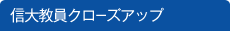
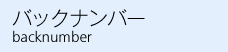
 学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授
学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授「環境文学」による環境教育プログラム
 学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授
学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授昆虫群集による環境評価
 飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授)
飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授) 流れに置くだけのEco水車
 中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)
中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)「地下水の可視化」に取り組む
 関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)
関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)環境負荷低減と生産コスト減を同時に実現する「マテリアルフローコスト会計」