


全学教育機構の副機構長も務める地質学の教授。近年、全国で異常豪雨による土砂災害が多発しているが、その現場に飛び、発生原因を分析し、防御策や発生予測を研究する。
ベースは、信州の地形を地質構造の発達史の視点から捉える地道な研究だ。1億年~1000万年単位の地質の研究が、地球環境の急速な変化にアラームを鳴らす。
プロフィール:1955年愛知県生まれ。1979年信州大学理学部卒業。1987年大阪市立大学大学院理学研究科博士課程修了。1989年信州大学教養部講師。1991年同助教授。1995年理学部助教授。2008年全学教育機構教授。
・・・・・ 信州大学環境報告書2010より

「県歌・信濃の国に歌われているように、信州は多くの盆地(平)でできていますが、どうしてこういう地形ができたのでしょうか?」。思いがけない質問から始まった。
日本列島は、太平洋プレートと大陸プレートがぶつかり合い、盛り上がってできた。最も盛り上がったのが中部高地。
そこで断層(活断層)が生じて凹部ができ、そこに土砂が堆積して盆地、つまり「四つの平」ができたのだそうだ。ちなみに、「四つの平」をつなぐ峠道も、活断層の上に延びているという。
「活断層は、内陸地震の発生源と恐れられていますが、それがなければ現在の信州の地形も私たちの生活の場も生まれなかったのです。正しい知識を持つことで、どのような地質構造のところでどういう災害が起きやすいのかを、冷静に見極めていく姿勢が育つと思うのです」と話す。

「地質構造を冷静に見極める必要性」を強く感じたのは、2006年に岡谷市や上伊那郡辰野町で発生した豪雨災害の調査の時。岡谷市で8人、辰野町で1人の尊い人命が失われたこの土砂災害では、塩嶺火山岩類と呼ばれる火山岩や凝灰角礫岩でできた山を覆っていた表土が崩れ落ちた。だが、一様に表土が崩れたのではなく、例えば被害のひどかった志平川流域では、上流から、1.表土が崩れた「崩壊領域」2.上から流れてきた泥水が単に流れ下った「通過領域」3.その泥水が沢底の堆積物をえぐり取った「侵食領域」4.前領域で増加した土砂が人家を襲った「堆積領域」-に分けられることも判明した。
「大きな岩塊を含む土砂が流れ出す、一般的な土砂流とは違う」と感じたという。
さらに調査を続けると、「崩壊領域」で、「塩嶺累層」の上に水分を多く蓄える多孔質の地層があり、大量の雨でここに蓄えられた水が、その上の表土を突き破り、噴出した痕跡が認められたという。

「地質構造は変わらなくても、環境の変化で別の反応が出ることもあるということです」。水分を蓄える多孔質の地層とそれを覆う表土は、人間の時間感覚を越えた長い間バランスを保ち続けてきた。だが、最近多発する傾向がある異常な豪雨にさらされる中で、そのバランスが崩れた。地中から吹き出す水が表土を崩壊させ、流動化した土砂が流れ下る過程でさらに表土をえぐり取るというタイプの土砂災害が発生しやすくなっていると考えられるというのだ。
「崩壊領域」のさらに上方には、かつて田畑として利用されながらも、現在では放置されている荒廃農地があることも多く、それが溜め池的機能を果たし、噴き出す水の量を増やしている傾向も認められるという。
「地質学は、長い年月の変化を追うものですから、急激な環境変化をよりビビッドに捉えることができるのです。研究を通じて、これまでの町づくりを見直す必要があることなど、社会にアラームを鳴らすことが私たちの役割です」。言葉に力がこもった。
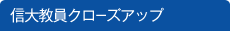
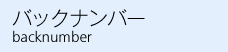
 学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授
学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授「環境文学」による環境教育プログラム
 学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授
学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授昆虫群集による環境評価
 飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授)
飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授) 流れに置くだけのEco水車
 中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)
中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)「地下水の可視化」に取り組む
 関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)
関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)環境負荷低減と生産コスト減を同時に実現する「マテリアルフローコスト会計」