


「マテリアルフローコスト会計(MFCA)」と聞いて、すぐに理解できる人は少ない。企業経営に使われる会計手法の一つで、製造業などの生産工程でマテリアル=原材料の流れを追跡し、投入した原材料の金額と重さを把握する計算方法である。
生産工程で生じた廃棄物を「負の製品」として把握し、実際に製品となった「正の製品」とともに製品の製造原価を把握することで、企業収益の向上につなげるというもの。従来から行われてきた貨幣単位の計算に、‘重さ’も考慮して計算する原価計算であり、廃棄物(負の製品)削減によって環境負荷を低減しつつ、生産コストの削減を達成できる有益なツールである。
例えば原材料費1,000円、加工費600円で生産される製品1個の原価は1,600円。ところが実際の生産工程では、必ずしもこの計算通りにいかない。なぜなら生産工程で廃棄物が生じる可能性があるからだ。上記の例で原材料100kgに対し、完成した製品が80kgだった場合、製品原価は80%の1,280円となる。では20kgの材料はどこへ行ったのか。「これは生産プロセスの中で廃棄物として処理された分が20kgあったということ。
つまり材料費と加工費それぞれの20%にあたる計320円が廃棄物の生産にかかってしまった。このように廃棄分を負の製品として原価を把握することで、廃棄分削減のための具体的なアクションを起こすことができる」と関准教授は話す。
東京都生まれ
1997 年 明治大学博士前期課程経営学研究科修了
2000 年 明治大学博士後期課程経営学研究科単位取得満期退学
2000 年 信州大学経済学部講師
2003 年 同助教授(2007 年から准教授)
・・・環境報告書2013より
MFCAはドイツで生まれた概念で、日本でもキヤノンや田辺製薬などといった大企業に導入事例があるという。その中には生産工程を細かく改良することで、「負の製品」を減らし、実際に数千万円から数億円ものコスト低減を実現した企業もあり、MFCAの効果は実証済み。しかし一方で、経営資源の乏しい中小企業は新たな会計システムの構築や環境への取り組みに消極的で、普及が難しい面もあった。実際には新規の設備投資が不要で、わずかなコスト低減が大きな収益につながり得るMFCAの導入は、「中小企業にこそ有益」と関准教授は言う。広く普及すれば資源の保護や産業廃棄物の削減につながり、「環境にやさしい」と企業イメージの向上にも役立つ。
そこで長野県は中小企業経営へのMFCA導入支援を始めた。2009年から県工業技術総合センターが実施した「環境対応型ものづくり収益普及事業」である。関准教授はこの事業に参画し、県内の中小製造業数社でMFCA導入に取り組んだ。


2009年、メッキ加工の(株)駒ヶ根電化(駒ケ根市)は、同事業の支援を受け、亜鉛メッキラインを対象にMFCAを導入した。メッキ加工業では水と薬品を大量に使うため環境負荷が大きい。このため同社は環境負荷低減や効率化、企業と人材のレベルアップなどを目標に掲げて取り組みを開始した。
導入初年度、メッキの前処理工程で使う薬液の温度を、一定幅下げた場合の生産効率はどう変化するか…といった実測を重ねながら、同時にボイラー配管に断熱材を巻いて保温効果を高めるなどの省エネの工夫を随所に行い、改善を進めた。その結果、約半年の地道な実測、作業の改善、効果測定の繰り返しにより、地下水使用量40%減、電気使用量38%減、光沢剤使用量38%減を実現、月額約50万円というコスト低減を達成したのである。また、成果が具体的な数字として表れたことで、作業意識が高まったことも収穫だった。
同社では、その後毎年プロジェクトチームを編成し、別のメッキラインを対象にMFCAを継続的に活用しており、環境保全の推進と企業基盤の強化に役立てている。
MFCAは特別な概念ではない。生産工程に投入したエネルギーや労力も含めて金額に換算し、「負の製品」コストを数値として把握する手法であり、それまで隠れていた部分を明確にすることで企業の収益を上げることが目的だ。そのために熟練作業者の「カン」に頼っていたような部分も、実測を重ねながら可能な限り数値化していく。いわば「暗黙知」で成り立ってきた工程を「見える化」することで、作業意識を高め、ムダの削減に取り組むという考え方である。

企業組織の業績測定のために使われる「管理会計」に、省エネ・省コスト・省廃棄物といった概念を組み込んだMFCAは、廃棄物処理の適正化など企業の環境対策に厳しい目が注がれる現在、各方面から注目されている。「MFCAなどの会計手法は景気が不安定なときほど注目されがちだが、企業にとって有益なツールであることは間違いない。単なるコスト削減ではなく、環境への配慮と利益向上を両立するもので、経営資源の最適・最良の状態を目指すもの。その有効性を広めるとともに、今後はどのような可能性があるのかを模索していきたい」と関准教授は話している。
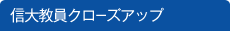
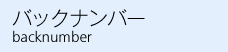
 学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授
学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授「環境文学」による環境教育プログラム
 学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授
学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授昆虫群集による環境評価
 飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授)
飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授) 流れに置くだけのEco水車
 中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)
中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)「地下水の可視化」に取り組む
 関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)
関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)環境負荷低減と生産コスト減を同時に実現する「マテリアルフローコスト会計」