

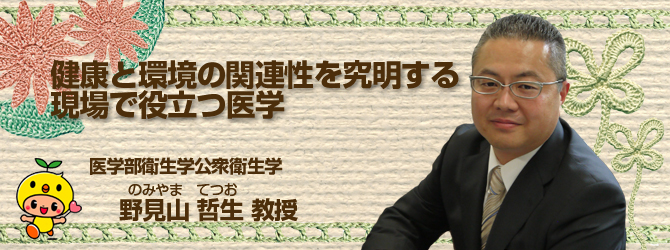
長野県生まれ
1992年 産業医科大学医学部卒業
1996年 慶應義塾大学大学院医科学研究科博士課程終了
2002年 信州大学医学部講師
2003年 同助教授
2007年 同教授
・・・環境報告書2012より

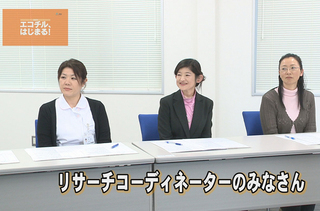
ダウン症や水頭症などの先天異常、小児ぜんそくやアトピーなどの免疫系疾患、小児肥満などの代謝・内分泌系異常、自閉症や学習障害、注意欠陥多動性障害などの神経系異常等々、子どもたちの心身の病気が増加傾向にある。遺伝、生活習慣の変化、環境ホルモンなど、実に様々な理由が取り沙汰されるが、確たる要因は明らかになっていないのが実情だ。
今年1月に開始されたエコチル調査は、子どもの成長に影響を与える可能性のある環境因子、特に化学物質との関連解明が目的。環境省が文部科学省、厚生労働省と連携し、国立環境研究所を中核に大学医療機関が調査を実施するかつてない大プロジェクトで、調査地は、都市・農漁村、寒冷・温暖地など風土が異なる全国15か所。対象は10万組の新生児とその親たち。妊娠中の母親らの同意を得ながら3年間で10万組を募集し、胎児期から13歳までの長期にわたって追跡調査を行う。長野・山梨の甲信ユニットは7,200組、うち野見山教授らが担当する上伊那地域は2,712組に協力を得るべく活動を開始。地域を挙げての理解とバックアップ体制もあって、順調に協力者を増やしているという。
膨大な調査データの蓄積によって、子どもの病気と環境因子の関連が究明されるだけでも大変な成果だが、環境・医療・教育など各分野の制度改正や行政サービスといった成育環境の向上にまでつなげられるのが、この調査の非常に大きなメリット。同時に、小児科や産科医、小児保健に関わる人材、環境医学の研究者育成という間接的な成果も大いに期待されるところ。野見山教授が言うとおり、あらゆる面でこの調査は「次世代への贈り物」なのだ。検討会から始まった準備期間に3年、募集3年、追跡調査13年、解析5年、さらにその先の体制構築まで、まだまだ先は長い。「最後まで責任を持って見届ける覚悟」という言葉が重い。
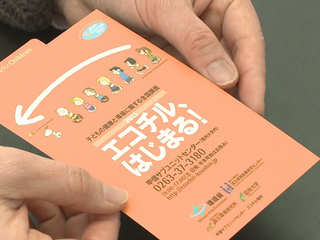
「衛生学・公衆衛生学では研究のための研究は不要。現場で役に立たなければ意味がない」と断言する。
「現場」とは社会であり、対象は病人だけでなく、病気にかかる可能性がある全ての人である。「そこが臨床医学との根本的な違い」であり、「社会との繋がりが深い社会医学という領域」なのだ。
社会医学の特徴は、必要に応じて「医」の領域外にもアプローチすること。エコチル調査がそうであるように、研究の末に環境改善の必要ありと判断すれば、行政と絡み、法規や基準の改定にも携わる。そして、臨床医学・基礎医学の研究者、医療関係者、自治体、教育関係団体など、様々な人々や地域住民と協同して、得た成果を社会に還元していく。
今年度中にもう一つ、環境省による全国的な疫学調査がスタートする。呼吸器・循環器系への影響が懸念されるものの、国内データが不足するPM2.5という微小粒子の調査で、やはり野見山教授が計画段階から関わり、講座の塚原講師が調査班に加わり、長野県でも実施する。
「環境を破壊するのは、残念ながら人だけ」。だからこそ、「高い意識で良い環境を指向しなければ、次世代にはより劣悪な環境しか残せない」。プライベートでも子育て環境の支援に携わる野見山教授が目指すのは、「病気になる人を可能な限り減らせる社会基盤づくり」。高みに挑み続けるその背中を見て、多くの研究者が育つことを期待したい。
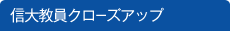
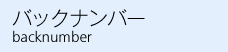
 学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授
学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授「環境文学」による環境教育プログラム
 学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授
学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授昆虫群集による環境評価
 飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授)
飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授) 流れに置くだけのEco水車
 中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)
中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)「地下水の可視化」に取り組む
 関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)
関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)環境負荷低減と生産コスト減を同時に実現する「マテリアルフローコスト会計」