

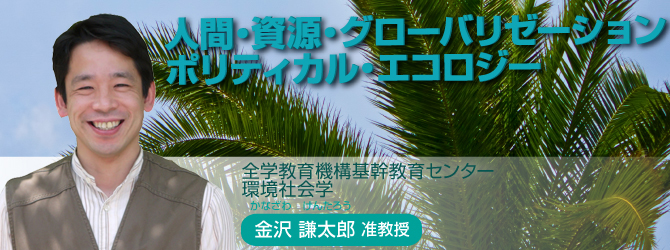
専門は環境社会学。特に、地域の人々の資源利用の変化を、その地域をとりまく国家やグローバルな政治経済の関係のなかで位置づける領域。院生時代から15年間、マレーシア・サラワク州の狩猟採集民・プナン人のもとに通い詰め、彼らの森林資源利用について調査を続ける。とりわけ強い関心を持っているのが「サゴヤシ」と「沈香」の二つだ。
長野県生まれ
1991年 東京外国語大学外国語学部ヒンディー語学科卒業
2001年 東京大学大学院総合文化研究科国際社会科学専攻博士課程単位取得満期退学
神戸女学院大学人間科学部准教授などを経て2008年信州大学准教授
・・・環境報告書2012より

「サゴヤシ」はプナン人の主食であり、重要なデンプン源。彼らが移動生活を営む最大の理由は、このサゴヤシにある。サゴヤシ採集や狩猟をしながら一か所に数週間から数ヶ月間滞在しては次へ移動するが、ただ闇雲に動くわけではない。サゴヤシのありかを把握し、生長量を予測し、同じ場所に戻るのは数年後、サゴヤシの再生を待ってからだ。
「沈香」は線香や漢方薬の原料。ジンチョウゲ科ジンコウ属の樹木が自然の事象で傷つくと、その周辺が集積凝固して樹脂となる。山奥にあって数も少なく識別も困難で、森をよく知るプナン人にしか採集できないため珍重される。採集した沈香は、近隣農耕民の仲買人と適正な価格で取引され、プナン人にとって最大の現金収入源となっている。
しかし、こうした生態はあまり知られておらず、マレーシア国内でも色眼鏡で見られることが多いという。例えば、食べ物を求めて森をうろつくその日暮らし、あるいは社会から隔離され情報を持たない人々…というように。だが、貴重で希少な森林資源の知識や独自の採集技術を持ち、無分別な採集を慎んで資源を次世代に残そうとするプナン人が、ただの「その日暮らし」だろうか。沈香の交易を通じて、何十年にも及ぶ他民族との良好なネットワークと信頼関係を築き続ける彼らが、「社会と隔離された存在」だろうか。社会学、民俗学、人類学の側面から環境にアプローチする金沢准教授の研究は、決してそうではないことを伝えている。

1970年代後半から本格化した原生林の商業伐採に対し、森に依拠するプナン人は反対運動を起こした。しかし、マレーシアの原生林は次々に剥ぎ取られ、プランテーションは増殖し続ける。大規模なプランテーションで栽培されるアブラヤシのような単一の作物の対称にあるのが、「生態資源」と言われるもの。サゴヤシも沈香も、その地でしか採集できず、そこに暮らす人々が有する知識や技術によって維持管理・利用される「生態資源」だ。森林伐採が奥地まで進み、プナン人の生活領域も彼らの生態資源も確実に脅かされている。
社会と環境を考えるとき、マクロな政治経済システムとの関係性という視点が欠かせない時代だ。日本は、マレーシアで伐採された木材や、アブラヤシからとったパーム油の大量輸入国。プナン人の暮らしと生態資源、そして私たちの生活は、確かに繋がっている。生産の現場で繰り返される環境破壊や人権抑圧といった問題に、無関心でいいはずはない。

言うまでもないが環境問題の解決は容易ではなく、その視点も方法論も一つではない。大学で担当する1年生の環境マインド教育は、環境、地域、人との関係性を考察しながら、暮らしの豊かさ、心の豊かさとは何かを問い直す内容。「広く深く掘り下げ、考えることをしなければ、本当の環境マインドではない」と金沢准教授は言う。
今でも年に1回は長期休暇を利用してサラワクに滞在する。研究のためでもあるが、「向こうに行くとほっとする」というのが正直な思い。「プナン人は主体的に彼らなりの豊かさを感じながら暮らしている。欠乏感が少ないという意味では、彼らのほうが豊かなのかも…」。静かに語られた最後の言葉が印象深い。
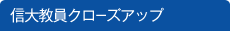
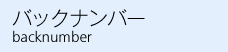
 学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授
学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授「環境文学」による環境教育プログラム
 学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授
学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授昆虫群集による環境評価
 飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授)
飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授) 流れに置くだけのEco水車
 中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)
中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)「地下水の可視化」に取り組む
 関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)
関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)環境負荷低減と生産コスト減を同時に実現する「マテリアルフローコスト会計」