


信州は日本有数の森林県。身近な平地の里山から急峻なアルプスの頂近くにまで広がる緑の森は、信州大学の学生・教職員の学びと研究のフィールドだ。この森林の状況を、デジタル航空写真を活用した最新のリモートセンシング(遠隔探査)の手法で診断する加藤正人農学部教授を紹介しよう。農学部附属アルプス圏フィールド科学教育研究センターのセンター長だ。
プロフィール…1957年北海道生まれ。宇都宮大学農学部卒業、同大学院修士課程修了。1983年から16年間北海道林業試験場に勤務。経営課長・資源解析課長などを務める傍ら、1996年北海道大学農学研究科博士課程修了。北海道大学非常勤講師を経て、2001年信州大学非常勤講師、2002年AFC助教授、2005年同教授、2010年より同センター長。研究分野は森林計測・計画学。2010年日本森林学会賞。

森は生きている。
一つの森に、どのような種類の樹木(樹種)が、どの程度の高さ(樹高)や、枝の広がり(樹冠)で、何本生えているのか?建築用材などに利用できそうな木はどこに何本あり、樹木の成長を促す間伐などの手入れは、いつから手をつければよいのか?……
こうした森の保全と活用に関わる調査・集計は、従来、もっぱら森に人が踏み込み、実際に、目で確かめることなしにはできなかった。この人手のかかる苦労の多い仕事を、人工衛星や航空機から撮影したデジタル写真をコンピューターで解析する画期的技術で革新したのが加藤正人教授だ。解析できるのは、樹種・樹冠・樹高・本数。現状では50×50cm四方で掌握できる高分解能を誇る。
「北海道林業試験場に就職して以降、25年間この方法を研究してきました。画像解像度の向上などデジタル技術の発展にも助けられ、2008年までに開発、特許も申請しました。現在、この解析ができるのは、世界で私しかいません」。言葉に力がこもった。

森林リモートセンシング(遠隔探査)と呼ばれる手法。樹木の葉が太陽光を反射する際に、葉の葉緑素や水分量・厚さなどの違いで、微妙に波長の異なる光が生じる。人間の目に見える可視域のさらに外側、つまり可視域外の波長の光までセンサーで感知して、森を構成する一本一本の樹木を見分けるのだ。
この解析データをもとにして、樹木の種類・樹冠の大きさ・混み具合などを指標に森の現状を特徴付け、区分することができる。さらに、地図上に落とし込んだ所有者や森の手入れの履歴などのGIS情報と複合して検索をかければ、急いで間伐をしなければならない森、樹木の収穫に当たる主伐を始めるべき林などが一目瞭然、デジタル図上に表示されるというわけだ。
「『ブナの大きな木が欲しい』という要求に、『この森のあそこに生えているものが適している』というように答えることもできるのです」と加藤教授。
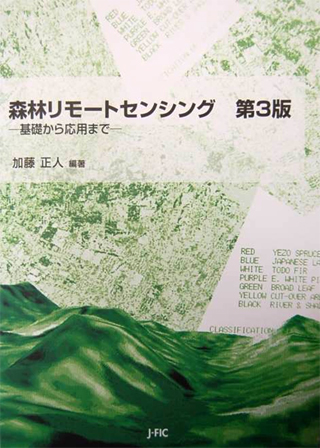
加藤教授は森林リモートセンシングの領域の第一人者。2004年に刊行した「森林リモートセンシング―基礎から応用まで―」(編著/日本林業調査会刊)は、森林関係の学部・学科を持つすべての大学で教科書として使用されている。第3版まで出されるベストセラーだ。2010年にはこの書籍を刊行した功績が讃えられ、日本森林学会賞受賞の栄誉にも輝いた。
「このところ研究ではリモートセンシングに掛かりきりでしたが、もともと森が大好き。森づくりの体験を重ねる中で、森を見る色々な視点を学んだのです」と話す。実際、北海道に所有する「自分の山」で森づくりを進め、その体験をもとにして学生には演習林で森づくりの初歩から教える。「Let’s enjoy 誰でもできる サンデー森づくり」(森林計画学会出版局刊)の著作もある。
森と共に育ち、そこに働く場を得て、実践的に研究を進めてきたからこそ、最先端のデジタル技術を駆使した森の健康診断の方法を研究開発することができたのだ。
【外部リンク】2010年森林学会賞受賞記事
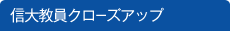
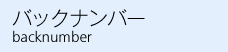
 学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授
学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授「環境文学」による環境教育プログラム
 学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授
学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授昆虫群集による環境評価
 飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授)
飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授) 流れに置くだけのEco水車
 中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)
中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)「地下水の可視化」に取り組む
 関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)
関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)環境負荷低減と生産コスト減を同時に実現する「マテリアルフローコスト会計」