


地域に残る歴史的なものや事象。それらがどうして今も存在しているのか。
地域文化をじっくり研究すると、日本全体の姿も見えてくる。
私たちが未来を展望しようとする時には、まず足元を見つめること。それは身近な歴史をよく知ることでもある。
信州のフィールドを歩き、地域文化を見つめる笹本教授が自身の研究について語る。
プロフィール...1951年山梨県生まれ。信州大学人文学部卒業。名古屋大学大学院博士課程前期修了。博士(歴史学)授与(名古屋大学)。名古屋大学文学部助手を経て、1984年から信州大学人文学部助教授、1994年教授。2009年副学長。研究分野は戦国時代史、災害史、音や色などに対する感性史。1991年「野口賞」郷土研究部門受賞
・・・・・・2010年5月24日掲載

近年歴史好きの女性が増えていて、とりわけ戦国大名が興味対象にされているようです。かっこいい戦国大名は嘘ですが、私の研究対象としているのは戦国大名が生きた時代です。
戦前を代表する東洋学者の内藤湖南(ないとうこなん)は、「大体今日の日本を知る為に日本の歴史を研究するには、古代の歴史を研究する必要は殆どありませぬ、応仁の乱以後の歴史を知って居ったらそれで沢山です」と述べました。応仁の乱から約100年間の日本の転換期が戦国時代です。
私は武田信玄などの戦国大名についても執筆していますが、それよりも社会の底辺にあった職人や商人などに興味を抱きます。一般民衆の視点から転換期である戦国時代の実態に迫ろうとしています。

私はしばしば学生に「あなたがお仏壇の前で行う行為をしてみてください」などと求めます。その上で、「どうしてそうしたことをするのですか」と尋ねます。
お仏壇のローソクの火、キンの音、お線香の煙、お線香の匂い、さらには仏壇に飾るシキミ、それぞれが意味を持ちます。
私の研究課題の一つは音や色、匂いに対する日本人の意識変化です。仏壇のキンと、神社の鰐口(わにぐち)は同じ意味を持ちます。雷が「神鳴り」で、神が鳴らした音がこの世に聞こえるのですから、この世で人間が作った音もあの世に聞こえると考えたのでしょう。神仏と人間とをつなぐのがキンや鰐口の音なのです。
神社にあった梵鐘も誓いに用いられました。武士が金打(きんちょう:*1)をして約束をするのも、この神仏をつなぐ金属音に由来します。このように、少しでも身の回りのことに何故なんだろうと思うことが研究への入口です。
*1:武士が約束として刀の刃や鍔(つば)を打ち合わせること

私は学生たちとともに祭礼などの調査に行きます。たとえば飯山市小菅では3年に1度柱松柴灯(はしらまつさいとう)が催されますが、地域の皆さんが温かく学生を迎えてくれます。小菅には工学部、農学部、教育学部といった多くの学生と教員がお世話になっています。
長く地域に入ると、これまで見えてこなかったものが見えてきます。何故ここに祭が残ったのか、何故集落の道路はまっすぐなのか、その先には何があるのか。地域の文化をじっくり研究することによって、日本全体も見えてきます。
私は飯山市以外に伊那市、坂城町、安曇野市などにも調査に入っています。その都度地域の人々の心の豊かさに圧倒されます。学生たちも人と接触することによって、本当の信州の文化を学んでいます。

私の研究テーマの一つに災害文化史もあります。災害がある場所にはたいていそれに対応する文化が生まれています。たとえば、災害の伝説を持つ地域では、それを通じて次の災害に備えようとしています。私はそうした災害に対応する文化を確認し、ソフト面から防災を考えていこうとしています。
地域作りもまずは足下の文化を確認し、地域に誇りを抱くことから始まります。都市計画も、防災計画も、過去を認識して作っていく必要があります。
歴史学は暗記するものではありません。考える学問です。同時に未来のための学問です。未来は過去と現在の延長線上にあります。しっかりと過去を認識し、未来に向かっていきたいと思います。
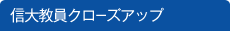
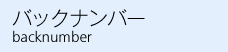
 学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授
学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授「環境文学」による環境教育プログラム
 学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授
学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授昆虫群集による環境評価
 飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授)
飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授) 流れに置くだけのEco水車
 中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)
中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)「地下水の可視化」に取り組む
 関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)
関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)環境負荷低減と生産コスト減を同時に実現する「マテリアルフローコスト会計」