


[工学部環境機能工学科准教授] 流体工学
1975 年 宮崎県生まれ
1998 年 宮崎大学工学部機械システム工学科卒業
2000 年 宮崎大学大学院工学研究科博士前期課程修了
2004 年 宮崎大学大学院工学研究科博士後期課程修了
2004 年 信州大学助手
2011 年 助教を経て、信州大学准教授
・・・環境報告書2014より
エネルギー自給率はわずか4%と低く、資源に乏しいと言われる日本。だが、世界的に見ても雨量は多く、水という資源には恵まれており、さらに高低差が大きい地形は水力発電に適している。純国産最大で再生可能な水資源を有効活用してエネルギー自給率を高めたい、と飯尾准教授がEco(エコ)水車の開発に取り組み始めたのは 10 年ほど前のこと。
従来のダムによる水力発電は多くの電気を生み出すものの、大規模な土木工事を必要とし、環境への負荷も大きい。Eco水車は「すでにある水路の流れに置くだけ」で発電するので、名前のとおり環境にやさしくCO2 排出量も少ない。小規模分散型、地産地消の水力発電が可能になる。
10 年程前までは法律の壁がEco水車の普及を阻んでいたが、2007 年に小水力発電が新エネルギーとして認められ、2013 年に河川や農業用水を利用する小水力発電が登録制になって簡素化・円滑化が図られると、風向きは変わり始めた。
Eco水車の開発は、研究室での基礎実験から水路でのフィールドテスト、実用化と着実に進んでいる。
2010 年から3年にわたる須坂市での実証試験では、約1.5km の農業用水路に4台のEco水車を設置した。
実際に活用されている水路には多様な人々が関わっているため、設置許可を得るまでの交渉は一筋縄ではいかない。まず行政と協議して話をまとめ、次に区長の許可を得、役員会での議論を経て、ようやく水利権者や水路下流の地権者たちに働きかけることができた。
導入の主体はどこか、水車の管理はどうするか、発電した電気の用途は・・・等々、関わる人々の思惑を尊重し、さらに地元にメリットのあるものでなければ設置はできない。「小規模水力発電を進めるうえで一番大事なのは地元の協力。関係者全員の合意を得ることが何より大変」という。
実証試験中には何度か問題も生じた。最大のトラブルは、水車のゴミ詰まりによってあふれ出た水で周辺の畑の土が流出したこと。同じ事態が2度と起こらぬよう、ゴミ取り装置の開発も急ピッチで進んでいる。
実験室でのシミュレーションと違い想定外の事態が発生する実証試験は「泥臭く、苦労が多い」が、「だからこそ得られる経験や成果は貴重」。3年間の試験は終了し、発電機は須坂市に譲渡されたが、発電と研究は現在も続行中だ。
高性能でありながら、製造に求められる技術レベルはさほど高くなく、費用的にも安価で製作できるというEco水車。「安い、誰でも作れるがキーワード」なのは、日本のエネルギー自給率の向上と同時に、世界の無電地帯への電気供給という目標があるから。東南アジアやアフリカでの製造・メンテナンスも想定して、構造はシンプルだ。周囲に反対されながらEco水車の特許を取得していないのも、「世界中の誰もが作り、使えるものにしたい」という強い思いから。タイの大学と連携したプロジェクトを10月から開始する。

「研究成果を製品として普及させること、出口に近いところを指向している」と飯尾准教授。「性格的にも能力的にも数学の式を駆使するような研究は向いていないし(笑)、何より利用者に喜んでもらえるという達成感は大きい」という。
「出口に近い」研究には、技術面以外の苦労も多い。水利権者との交渉などはおよそ工学部らしいものではなく、「大学の先生がなぜそこまで?」と言われることもある。が、「じゃあ誰がやるかというと、やる人がいない。だったら口火を切っていくしかない」と腹を括っている。
エネルギーの自給は果てしなく遠い理想であり、水力だけで叶うものではないが、「自給率4%が 10%になり、20、30、40%と上がっていけば世の中は大きく変わると思う。少しでもそこに貢献したい」と飯尾准教授は語る。
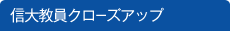
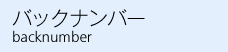
 学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授
学術研究院(総合人間科学系) 松岡 幸司 准教授「環境文学」による環境教育プログラム
 学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授
学術研究院(農学系) 中村 寛志 教授昆虫群集による環境評価
 飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授)
飯尾 昭一郎(学術研究院(工学系)准教授) 流れに置くだけのEco水車
 中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)
中屋 眞司(工学部土木工学科 教授)「地下水の可視化」に取り組む
 関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)
関 利恵子(経済学部経済学科 准教授)環境負荷低減と生産コスト減を同時に実現する「マテリアルフローコスト会計」