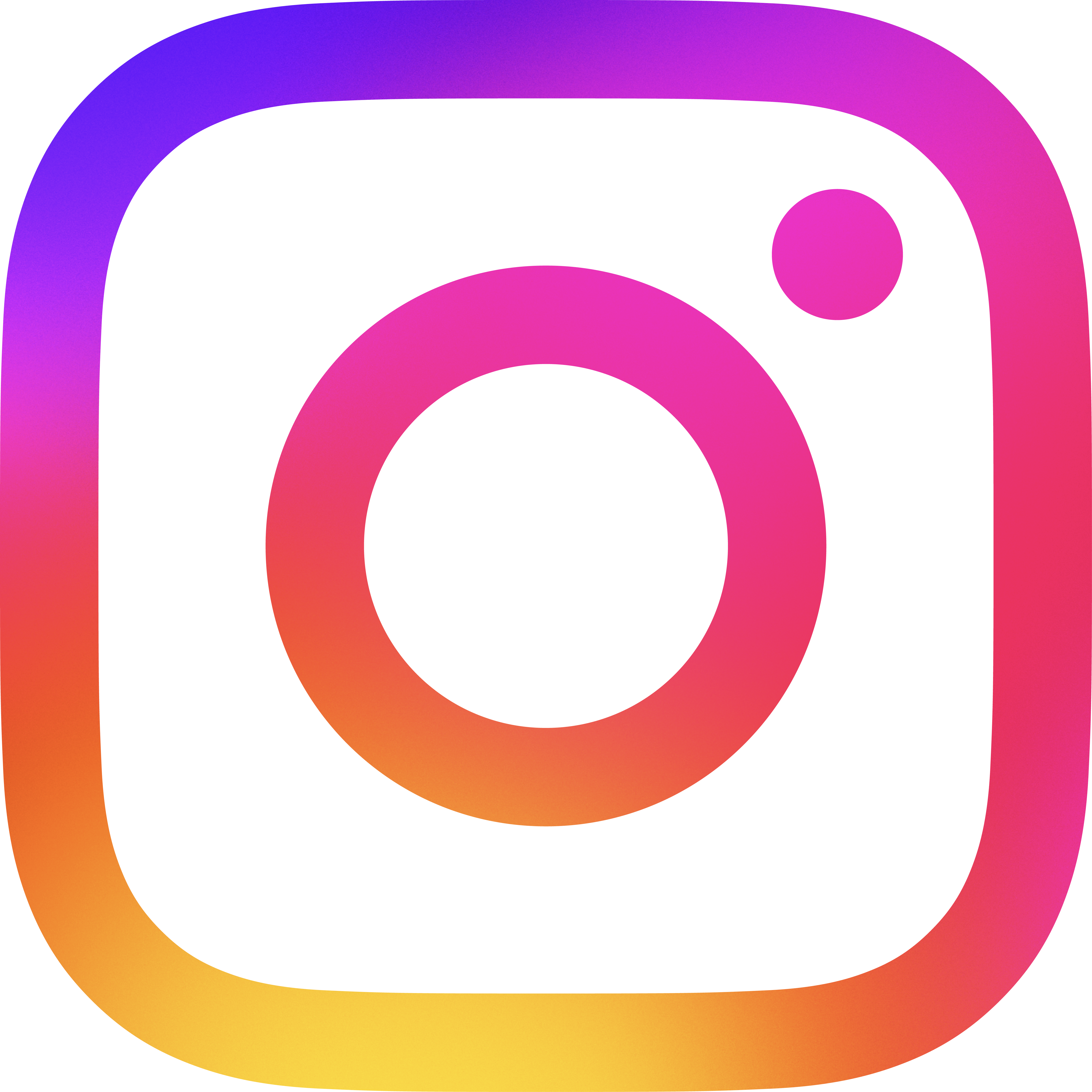文部科学省 職業実践力育成プログラム(BP)認定『地域共生マネージメントプログラム』(修士課程/社会人向けプログラム)

社会人の学び直しのための新たな教育プログラムとして、地域開発・保全など農学分野の専門技術者を育成する農学版MOT(Management of Technology)「地域共生マネージメントプログラム」として平成28年度に開設しました。本プログラムは、企業、地方自治体、公益法人、NPOに所属する職員等、地域のマネージメント及びイノベーションを担う社会人の方を対象に、設置する修業年限1年以上2年未満(最短1年で修了することが可能)のプログラムです。
本プログラムでは、1年で修士課程修了に必要な単位を修得することができます。さらに、入学時から指導教員による特定課題研究の指導を受け、審査に合格すれば、1年で修士課程を修了し、修士(農学)の学位を取得することができ、地域開発・保全など農学分野の専門技術者を育成するものです。
「地域共生マネージメントプログラム」リーフレット
「地域共生マネージメントプログラム」シラバス
- 文部科学省【職業実践力育成プログラム(BP)】の認定講座です。(平成28年4月~)
「職業実践力育成プログラム(BP)」認定時の、申請内容(様式1)はこちらです。 - 厚生労働省【専門実践教育訓練給付制度】の指定講座です。
1)専門実践教育訓練給付制度について
制度の概要、厚生労働省の制度説明サイト、講座指定番号など申請に必要な情報を記載しています。
2)明示書
地域共生マネージメントプログラム -地域で活躍するリーダーを育成します-
| 一般学生 | 社会人学生在職のまま受験可能 | |||
|---|---|---|---|---|
| ↓ | ←↓ | |||
| 通常の修学 プログラム (2年間) | 地域共生マネージメントプログラム (1年間)
|
|
||
2026年度入試案内
出願する前に、必ず「学生募集要項」を確認してください。2026年度入試情報はこちらをご覧ください。
入学資格審査申請の受付期間等 -学士の学位がない方-
2025年9月29日(月)から10月3日(金)まで(締切日の17時までに必着)
① 持参による受付は、8時30分から17時までとします。
② 郵送による場合は「簡易書留郵便」により送付してください。角形2号封筒(24㎝×33.2㎝)を用いて、封筒の表に「大学院入学資格審査申請書類在中」と朱書きしてください。
③ 提出先:信州大学大学院総合理工学研究科【農学専攻】入試事務室
入学資格審査の結果通知
申請された方には2025年10月24日(金)までに郵送します。
出願期間
2025年10月27日(月)から10月31日(金)まで(締切日の17時までに必着)
① 持参による受付は、8時30分から17時までとします。
② 郵送による場合は、「宛名ラベル」(所定書式)を市販の角形2号(24㎝×33.2㎝)の封筒に貼付し、出願書類一式を入れて「簡易書留速達郵便」により送付してください。
③ 提出先:信州大学大学院総合理工学研究科【農学専攻】入試事務室
入学試験の期日及び試験方法
| 期 日 | 集合時刻 | 試験科目 | 開始時刻 |
|---|---|---|---|
| 2025年11月25日(火) | 12時45分 | 口述試験 | 13時00分~ |
合格者の発表
2025年12月4日(木)14時
合格者には合格通知書を送付し公式発表とします。また、信州大学大学院総合理工学研究科ホームページにも合格者受験番号を掲載します。なお、電話や電子メール等による合否の問合せには、応じられません。
問い合わせ先・願書請求先
信州大学大学院総合理工学研究科【農学専攻】入試事務室
〒399-4598 長野県上伊那郡南箕輪村8304
TEL (0265) 77-1310 FAX (0265) 77-1313