もりやま しんや
護山 真也
哲学・芸術論 教授
教員 BLOG
一覧を見る新刊紹介『比較思想と世界哲学』(中島隆博編,東京大学出版会)
『比較思想と世界哲学』(東京大学出版会,2025年)目次
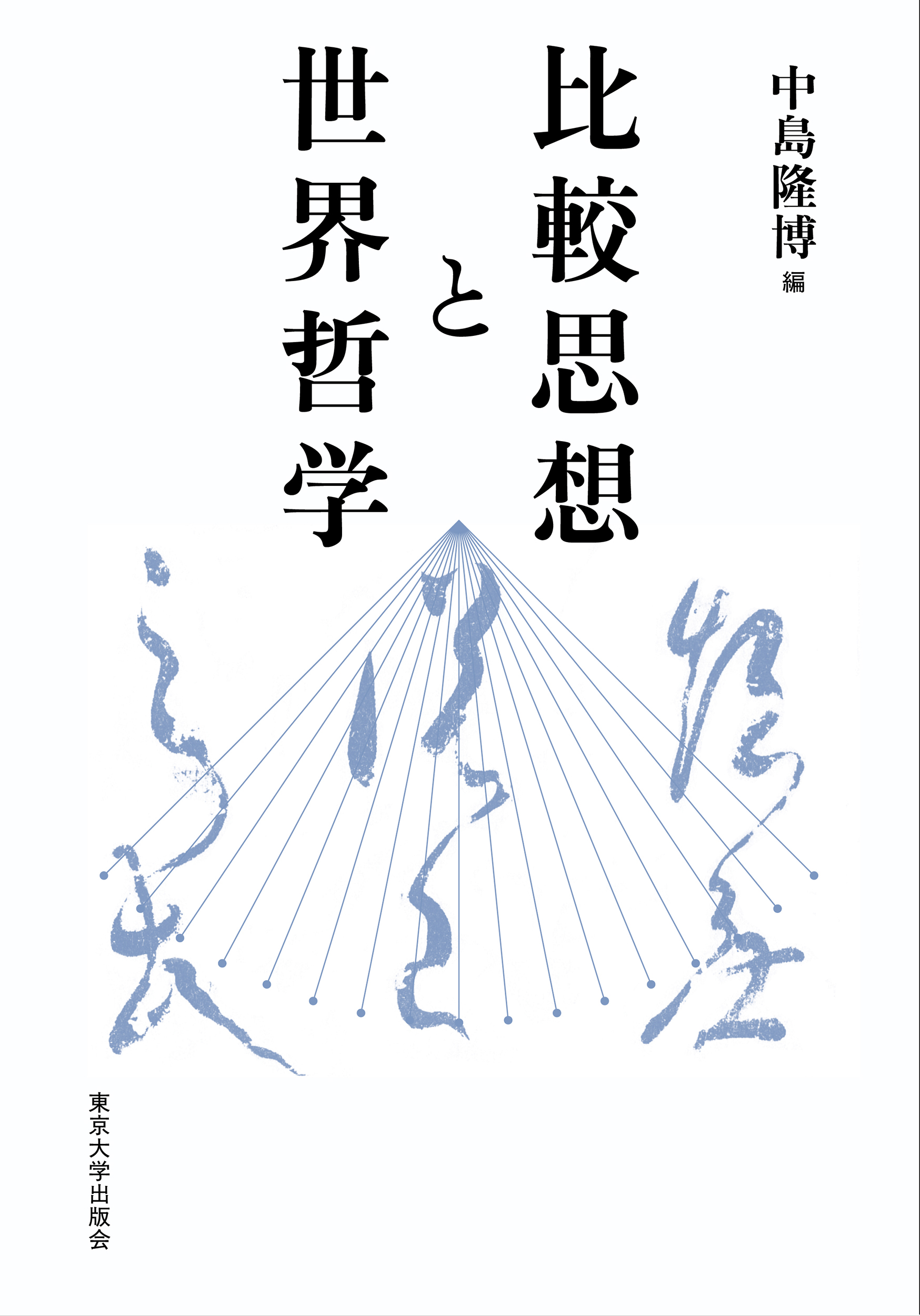
2023年7月に大正大学で開催された比較思想学会50周年記念大会における4つのシンポジウム・パネルをもとに,比較思想および世界哲学を考えるうえで貴重な論考が収録された書籍が刊行されました。私はその第IV部「普遍的思想史の夢の続きへ――中村元と比較思想研究」のパネルのコーディネートを担当しました。以下が本書の目次です。
はじめに(中島隆博)
Ⅰ 比較思想と世界哲学
第1章 文化的差異を超えて(マルクス・ガブリエル)/第2章 意味の出現から意味の到来へ(下田正弘)/第3章 ギリシア哲学とインド哲学の対決(納富信留)/第4章 中国哲学を普遍化する(中島隆博)
Ⅱ 日本哲学から見た比較思想と世界哲学
第5章 西洋哲学から世界哲学へ(ブレット・デービス)/第6章 哲学・思想の「日本性」?(板東洋介)/第7章 西田の根本経験と比較哲学の基盤(氣多雅子)/第8章 世界から自己を考える立場(板橋勇仁)
Ⅲ 空海と世界哲学
第9章 空海と世界哲学(種村隆元)/第10章 空海の思想概観(大塚伸夫)/第11章 中世インドの言語哲学から空海を読む(川村悠人)/第12章 比較思想としての天長六本宗書(師 茂樹)/第13章 霊異と即身成仏(安藤礼二)
Ⅳ 普遍的思想史の夢の続きへ――中村元と比較思想研究
第14章 普遍的論理学の夢(護山真也)/第15章 比較思想の意義とその展開(保坂俊司)/第16章 普遍思想史の構想(水野友晴)/第17章 ヴェーダーンタ哲学から普遍思想へ(加藤隆宏)
付録 1.文化とアイデンティティ(中野裕考)/2.哲学的方法を再考するために(ゲレオン・コプフ)/3.空海の思想構造――ことばと身体(阿部貴子)
あとがき(中島隆博)
人文学の目標
巻頭の論考でマルクス・ガブリエルは,「人間とは,自己自身という概念に照らして人生を送る動物である」というテーゼから出発し,その「自己自身という概念」には多様な視点があるということ,そのことに目を向ける学問こそ人文学であると述べています。
「…人間には歴史があり,ある自己概念を他の概念に重ね合わせ,それによって物語や伝統,差異や同一性,テクストや芸術作品などの複雑な網を生み出し,それによって自己概念を伝達し,凝固させ,変化させる。そして,いわゆる人文学は,自己概念の分節化とその変化を研究する唯一の学問分野であると私は考えている。それが人文学の目標体系なのだ。」(p. 8)
新実存主義から新しい啓蒙の概念へ,そして人文学の使命を語るガブリエルの言葉には,今危機に瀕している人文学の価値をあらためて考え直すためのヒントが示されています。彼が強調するのは多様性を認めることから共通の倫理的規範が確保されるということ。世界のさまざまな知的伝統の重なり合いのなかから生まれる新たな啓蒙――啓蒙(Enlightenment)とは「悟り」の訳語でもあることに彼は注意を促しています(p. 13)――の可能性を考えることは,人文学の未来のために大事なことでしょう。
「思想」と「哲学」
ブレッド・デービス「西洋哲学から世界哲学へ」は,日本における(西洋)哲学の受容とその後の「哲学」「思想」の使い分けに関する問題点を物語風の語りも交えながら,鋭く指摘しています。
「西洋独占的な哲学概念は19世紀末の産物である。皮肉にも,もし日本人が19世紀末ではなく,その100年前またその100年後に西洋の哲学概念を取り入れていたのであれば,おそらくインド,中国,日本などにも哲学は元からあった,という考え方になっていたと推測できる。なぜなら,18世紀末までのヨーロッパでは,それが主流の見解であり,また,現在の欧米においても,その見解が戻りつつあるからである。」(p. 105)
2018年に同氏がシンポジウムで述べられた内容として引用されている以上の文章は,とりわけ示唆的でした。比較哲学/比較思想を研究していると「哲学」と「思想」の違いに頭を悩ませますが,この観点を踏まえると,「比較哲学」でよいのではないか,という気持ちになります。
しかしながら,保坂俊司「比較思想の意義とその展開」を読むと,日本における比較思想研究のパイオニアである中村元が「比較思想」の語を選んだのは,既存の哲学研究の権威主義的・セクショナリズムの閉鎖性に対する異議申し立てという背景があったことが分かります(p. 297)。
中村は,「思想」を「人の考えであって,それが各個の行動を全体として指導する意義を持っているもの,人が生きて行く為の指針」として自らで定義しなおし,「哲学」との対決をしたということになるでしょう。その意図するところを読めば,その意味での「思想」とは,今展開されている「世界哲学」の「哲学」と重なることになるはずですが,「哲学」か「思想」か,その対話はまだまだ続きそうです。
比較思想/世界哲学に興味のある人には,本書の各論考に目を通されることをお薦めいたします。きっと新たな知見が得られることでしょう。
