教員 BLOG
一覧を見る自著紹介『昭和一〇年代の文学場を考える』
立教大学出版会2014年度採択新刊本自著紹介
本年3月に、立教大学出版会より刊行した拙著『昭和一〇年代の文学場を考える 新人・太宰治・戦争文学』について、下記紹介文を執筆しました。
(全文)
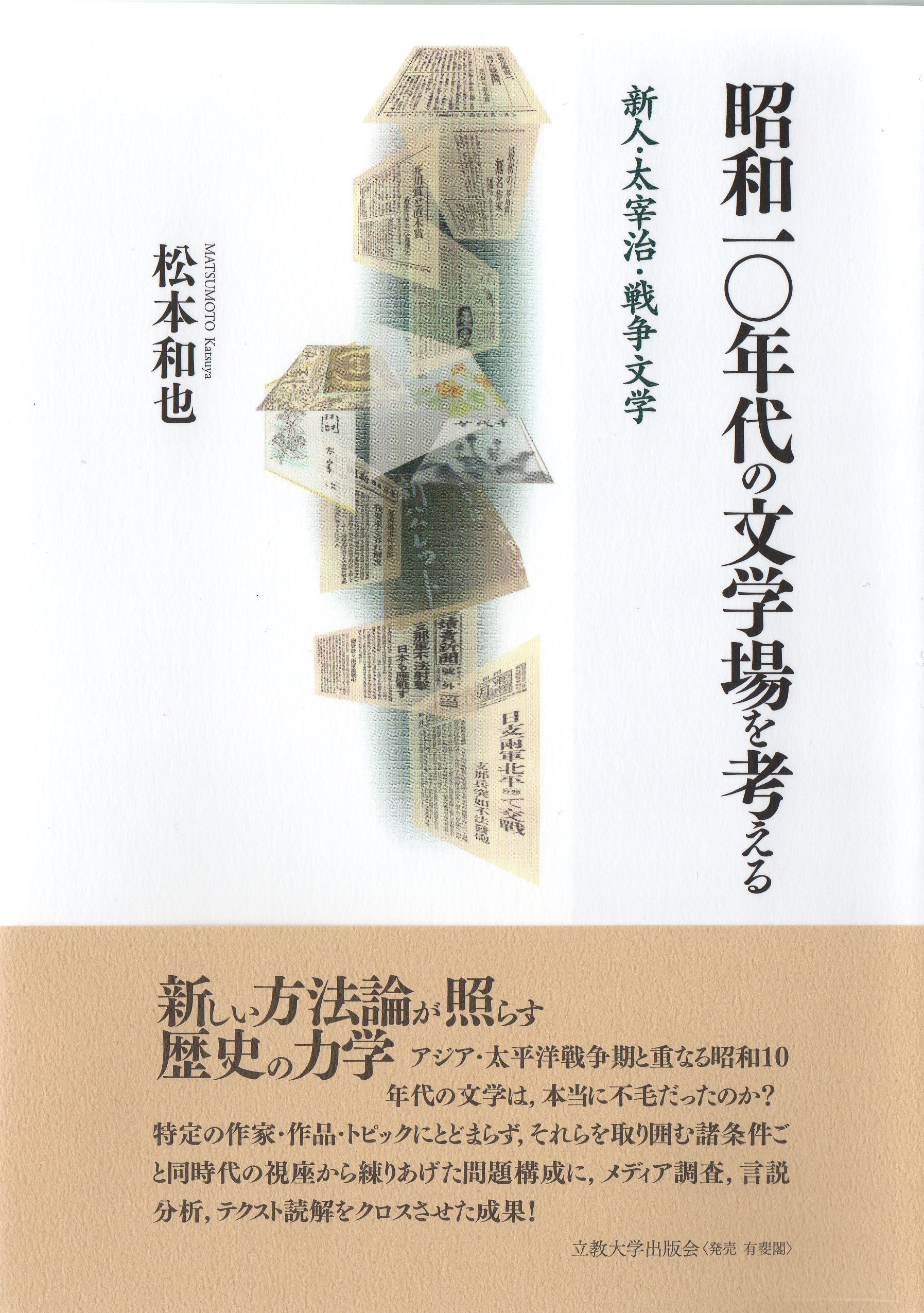
本書は、タイトル通り昭和一〇年代における文学場を考えるための議論を集めたもので、目次には芥川賞、私小説、日中戦争、報告文学(ルポルタージュ)、石川達三、小田嶽夫、太宰治(「女生徒」・「走れメロス」他)、石川淳、高見順、尾崎士郎、火野葦平、富澤有為男、田中英光、坂口安吾、といったワードが並ぶ。 それにしても、〝文学研究といえば作家・作品研究〟という見方は相変わらず根強い。それは多くの成果をもたらしてきたけれど、そうした枠組みからは見えづらく、考えにくい死角がある。個々の作品が発表当時どのように読まれたのか、その前提となった評価軸、作品に関わった多様なテクストや言説(との関係)、時局と文学を関連づけたメディアの動向、活発に論じられた文壇トピックが生みだす発想の檻、さらには文学活動を陰に陽に規定した歴史の力学──本書ではこうしたことごとを問題化するために「文学場」という概念を導入した。 一連の議論をまとめるのは「昭和一〇年代」という期間である。アジア・太平洋戦争期と重なるこの時期については、これまでの文学研究において否定的な評価が大勢を占め、論及自体も少なかった。端的に、戦局ゆえの不自由さの中で収穫に乏しかった、とみなされてきたのだ。本書は、こうした研究状況に対する実践的な異議申し立てとして、「昭和一〇年代」に展開された文学活動の再検討を目指した。 別の観点からも、「昭和一〇年代」を研究テーマとした動機を示しておきたい。 ここしばらく、(文学を含めた)人文学への風当たりが強い。さまざまな局面でしきりに問われているのは、文学の有用性なのだけれど、それが何によって要請されているのかといえば、『ヒューマニティーズ 文学』(岩波書店、二〇一二)の小野正嗣が正しく指摘する通り、市場の論理でしかない。ひるがえって、本書で検討対象とした「昭和一〇年代」の文学場においても文学(者)は時局の論理によって有用性──本書で用いた当時の言葉にすれば「社会性」──が要請されていたのだ。 そうであれば、研究対象としての「昭和一〇年代」と現代とは、およそ無縁とはいえず、むしろ意義ある先行事例/ある種の反復と捉えることができる。してみれば、「昭和一〇年代」の文学研究とは、緊要の課題にして批評的な営為でもあるはずで、今回の出版を介して、少しでも多くの方に人文学──「昭和一〇年代」の日本文学研究に興味をお持ち頂ければ幸いである。 季刊『立教』Summer・2015(発行:立教大学)233号より転載
