理学系
「なぜ?」の探求から生まれる
イノベーションの芽
社会を目指して
学術研究院理学系
竹下徹教授

トップ > 3つのキーコンセプト > 人と教育 > Case07 理学系
理学系
学術研究院理学系
竹下徹教授


高度な技術や知識、理解力を
身に付けるための改組です
2013年度に行われた修士課程の改組に続き、2018年度には博士課程の改組が始まります。信州大学総合理工学研究科では、理学としての高度な技術や知識および理解力を身に付けるためには学部の4年間だけではどうしても足りない。社会が理系の人材に求めるレベルに達するのは難しいのではと考えています。実戦的に動けるような教育ができるのは、学部レベルの能力を前提とした修士課程ということです。具体的な内容は研究室それぞれで異なってきますが、全体としては、学生と教員のコミュニケーションを強くすることと英語の強化。この2つを重視していきます。
学部4年で卒業して就職するのと、6年で修士になって就職するのとの大きな違いは、修士だと自分の好きなことをアピールして就職ができることです。就職の際の自由度が高い。これまでこんな研究をしてきました。だからここではこういうことがしたいんですというスタンスで会社に入れます。実際、修士の就職率はいいですし、決まるまでも早い。統計的な調査になりますが、もちろん修士の方が生涯年収も高いです。
理学というと「理科」のイメージが強いかもしれませんが、総合理工学系研究科の理学専攻は、数学分野と理科学分野に分かれており、数学、物理学、化学、生物学、地学など幅広いジャンルをカバーしている専攻です。学部ではそれぞれの学科がそれぞれの授業を行ういわば縦割りの状態なのですが、大学院は、それぞれの学科がバラバラにあるのではなく、中で入り混じることができるよう、総合理工学研究科という形に改組しました。
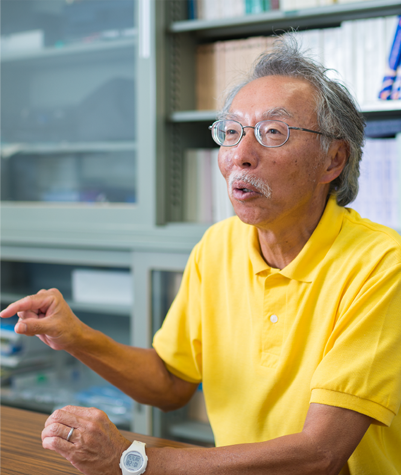

自分の専門につなぐための努力が
研究全体のレベルを底上げします
学科は違えどもお互いによく似たような研究しているというのはよくあることなんです。つまり、実験対象が違うので手法としてもまったく違うことをやっているのに、実は重なり合う部分が大きい。ひょっとすると同じことを違う角度からアプローチしているのでは、ということです。
例えば、私は素粒子物理学が専門で、粒子が飛んでくるのを捕まえる実験をしているのですが、粒子というものは「光」と関係する部分が実は大きいんです。一方で、化学の分野でもいろいろな成分を混ぜあわせる実験などをしていると、光が大きく関係してくる。素粒子物理学と化学は、光という部分で共通項があるわけです。化学の先生にとっては光を捕まえるのは大変な作業ですが、素粒子物理学では普通にやっていることです。そういう意味で、改組により専攻間の垣根が低くなると、情報交換が活発になり、大学院生にも先生にもより広い視野がもたらされるのです。
もちろん、このような交流は以前から先生同士が個人レベルでやっていたことですが、組織としてやると効果がやはり違います。専攻では別の院生が一緒に受ける授業があるのですが、自分のジャンルだからすんなりわかる生徒がいる一方で、専攻が違うこちらの生徒はちんぷんかんぷん。そういう部分も含めて混ぜあいました。それはコミュニケーション能力をあげることにもなるし、広い視野を持つことにもつながります。
例えば、生物を学んでいる修士の学生が私の素粒子物理学の授業に出ているとします。宇宙はどうやって始まったのかという内容だったとしても、その中には生物の誕生と密接にかかわる要素があります。するとその学生は、自分の興味の範囲をとっかかりに私の授業を理解しようとする。その切り口で書かれたレポートを私が読むと、今度は私に生物学の知見がフィードバックされて視野が広がります。今まで知らなかったことと自分の専門をつなぐための努力が、研究全体のレベルを底上げしていくんです。

「なぜ?」を積み重ねていく。
その上に現在の科学技術があるんです
理学にとってのキーワードは「なぜ?」です。なんでこうなるのだろう、なんでこうなっているのか知りたいという、実に単純な欲求ですね。何か役に立つものを作り出したいというのとはちょっと違います。「なぜなんだ」という自身の根源的な問いを解決するために、実験をしたり、検証できる仕組みを考えているわけです。調べれば調べるほど新たな「なぜ」に突き当たるのですが、理学専攻にはそういうことを面白いと思う人が集まっているんです。「科学」とはこのプロセスのことです。
ですので、偶然いいものができた、理由がわからないのに結果だけは出た、そういう状況はたとえそれが社会的に有益なものだったとしても理学としては満足できません。私たちは、ひたすら「なんでこうなったの?」を積み重ねていく。ここまでわかった、これもわかったという下積みがあり、その上に現在の科学技術が成り立っています。
例えば超伝導という現象は、1911年にまず超伝導というもの、水銀を冷却していくとある温度で急に電気抵抗が下がってほぼゼロになる現象があるということが発見されました。そのときはそういうことがあるというだけで原理はまったくわからなかったのですが、さまざまな実験を経て、1957年になってやっと基本的なメカニズムが解明されました。この段階では希少な物質を使わないと再現できなかったのですが、1980年代になってもっと一般的な物質でも超伝導を起こせることがわかり、そして21世紀になって超伝導技術の最先端としてリニア新幹線やMRI検査という形で実用化に結びついたのです。
この場合、超伝導という現象が起こるのはなぜなんだ、どういうメカニズムなんだという部分を一つひとつクリアにしていくこと。そして、この現象をどのように応用すればイノベーションにつながるのかという案を提示すること。これが理学の仕事だといえます。


理学はシーズのいちばんの根本。
芽が出て成長してイノベーションになります
まずは、理論あるいは実験や現象があって、それを理解し、発展させます。それを論文にして発表することで研究成果を外に出します。それに興味を持つ人が現れて、場合によっては何十年か後にやっと芽が出て、成長してイノベーションになる。ニーズとシーズでいえば、シーズのいちばんの根本。イノベーションの芽、実学の芽を出すというのが私たちの役割です。
私が所属している国際チームが2012年にヒッグス粒子を発見し、その存在が確かめられたことにより、50年前にヒッグス粒子の存在を予言した先生にノーベル賞がもたらされました。今回の成果により50年前の論文がノーベル賞になる。そういう世界です。
一言でいえば、ヒッグス粒子は物質に質量を与えている存在なのですが、今回の発見がどんなイノベーションに結びつくかはまだ皆目見当が付きません。
ヒッグス粒子の発見は、私たちにとっては質量に関するひとつの議論が検証されました、ということです。これが何の役に立つかというモチベーションではないんです。100年くらい経ったら大きなイノベーションにつながるとは思いますけどね。ただ、こういう基本的な部分をやっていかないといずれシーズはでてこなくなってしまうんです。
総合理工学研究科として目指しているのは、教員の方々など生徒に語りかける立場にある教育現場の人たちに、私たちの最先端の研究の成果や知見をできるだけ多くフィードバックしていくということです。実際、総合理工学研究科に通う社会人学生には、理科や数学の先生が多いんです。
最先端がどこなのか、科学の世界では何に興味が持たれているか、それらを教員の方々などに伝えることで、若い世代にも興味を持ってほしいですね。
若い世代に理学の「なぜ?」という部分の面白さを伝えていきたいです。