社会科学系
より高度な専門知の習得と、
専門知を現実社会で活かす
応用力を身に付ける社会科学教育
学術研究院社会科学系
広瀬純夫教授
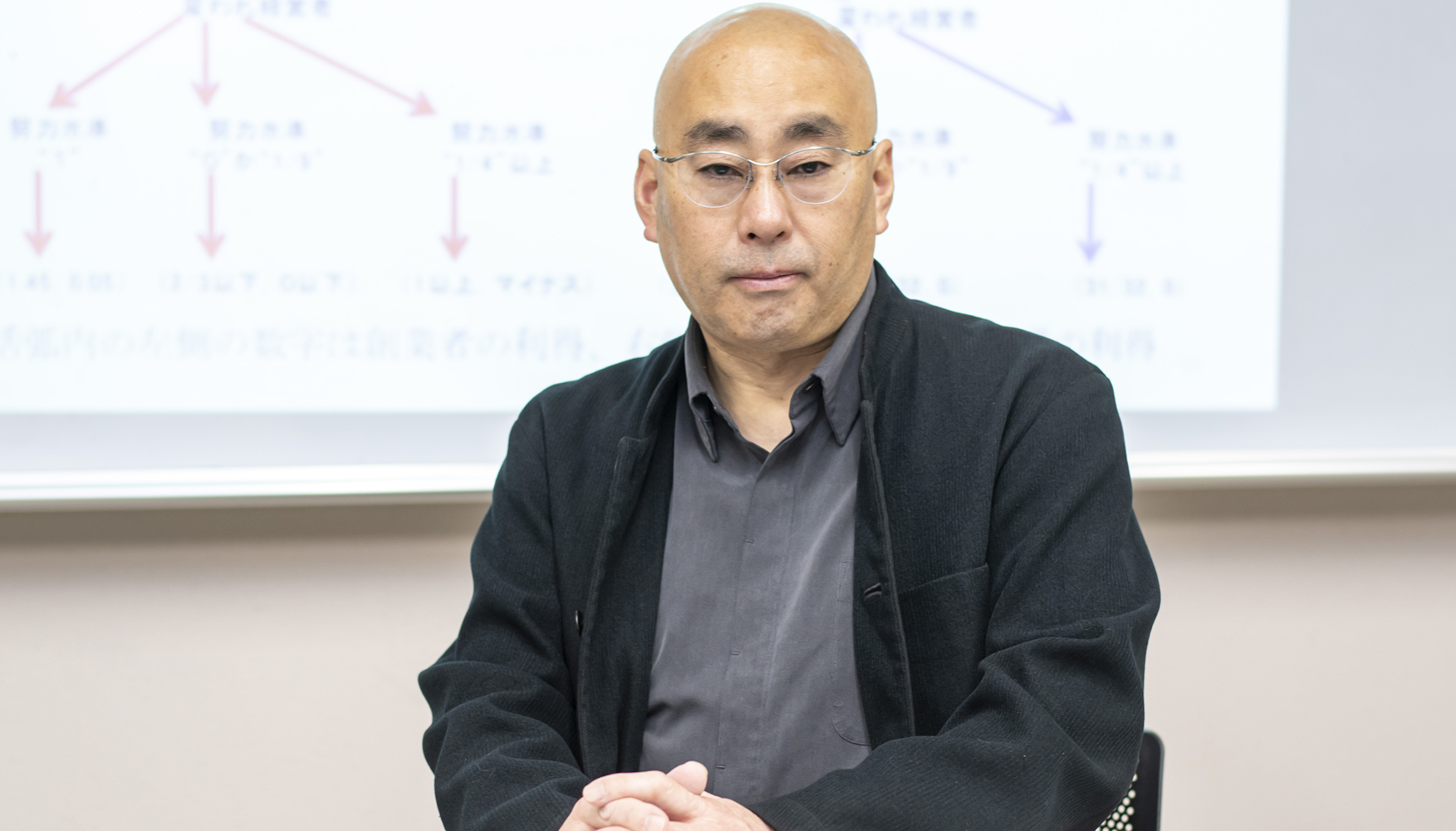
トップ > 3つのキーコンセプト > 人と教育 > Case03 社会科学系
社会科学系
学術研究院社会科学系
広瀬純夫教授
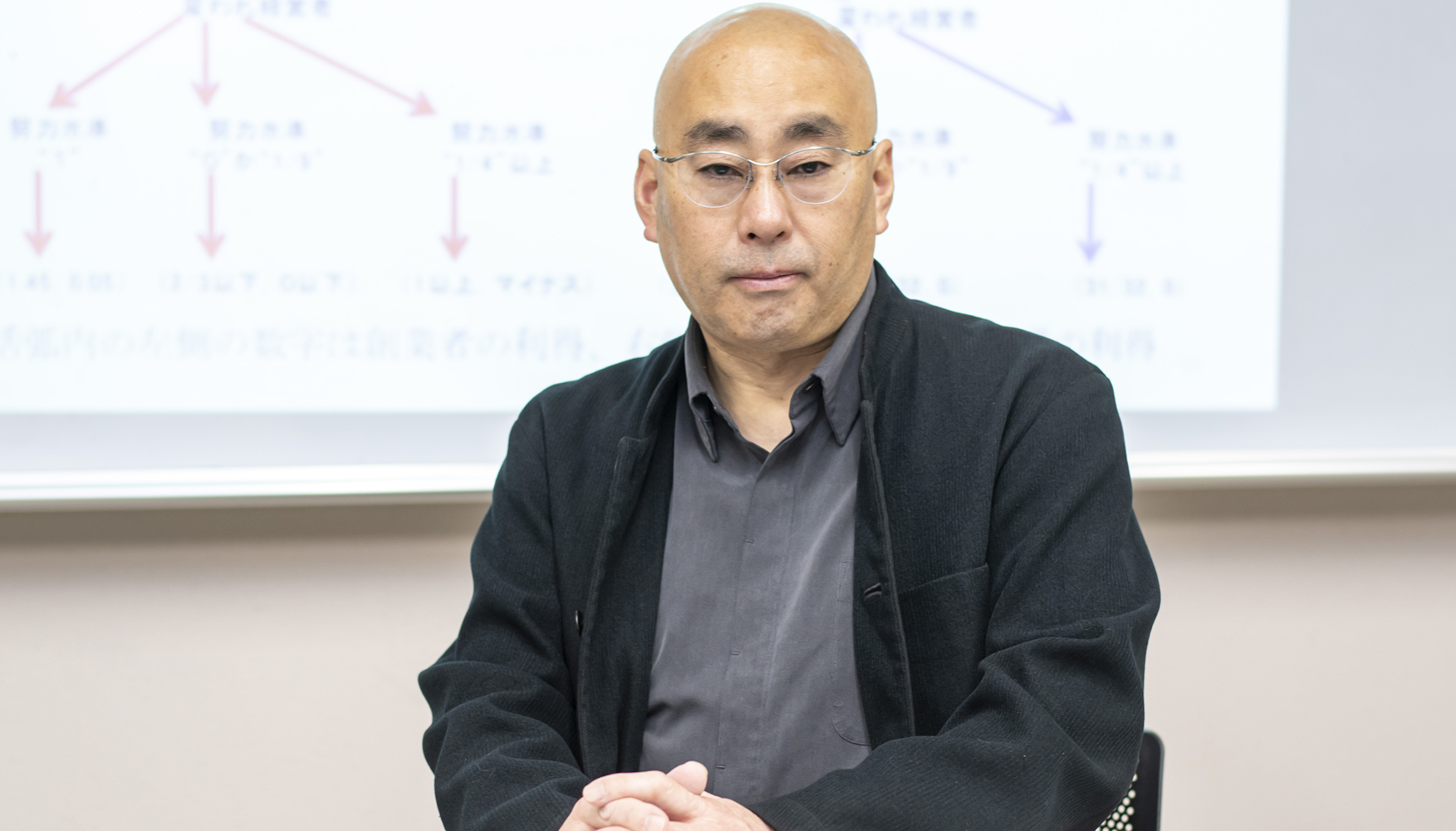

幅広い学問分野をカバーする利点を活かした教育体制
信州大学での経済学分野および法学分野の大学院教育は、総合人文社会科学研究科(総合人文社会科学専攻)の中で、実施されています。この研究科は、経済学、法学だけではなく、人文科学から社会科学にわたる幅広い学問分野を網羅する、文系の総合大学院です。
令和2年4月1日に、既存の人文科学研究科、教育学研究科(学校教育専攻)及び経済・社会政策科学研究科を統合再編して、「総合人文社会科学研究科(人間文化学分野、心理学分野、経済学分野、法学分野)」として誕生した、新しい大学院です。
文系総合大学院として、幅広い学問分野をカバーする利点を活かして、地域が抱える問題を解決できる人材育成を目指しています。今日の社会問題の多くは、様々な要因が複雑に絡み合っており、その解決には、多角的な視点が求められる面があります。そこで、自分の専門領域だけではなく、他分野の仲間と議論をする機会を設けて、他の専門領域の視点をも交えて、社会課題の解決に、総合的に取り組むことができる能力を養うことを目的として、設置されました。
このため、自身の専門領域の知識に加えて、複数の学問分野にまたがる総合的な知見をもととして、客観的に分析解析する能力と、全体を見渡せる俯瞰力、他分野への応用力を備え、他分野のメンバーとも協働して課題解決のための方策を提案することができる人材育成を目指しています。
これを実現するために、統計的分析などの基礎的な解析手法を習得する「解析手法論」や、様々な分野の大学院生が入り交じって、分野横断的な視点で、社会課題の解決方法について、グループワークを通じて検討する「社会課題別PBL」など、ユニークな科目を開設しています。「解析手法論」の授業を受けた経済学分野の学生から、「小説や映画の分析など、今まで持つことの無かった視点で物事をとらえることが出来るようになった」との感想も聞かれ、新たな知的刺激を受ける機会になっているようです。また、研究者としてのマナーを身につける「人文社会科学研究者倫理」を必修科目としていますが、この授業を受けると、「自分も研究者の仲間に加わったという実感が湧いてきた」と、嬉しそうに話を聞かせてくれます。

週1の授業受講という新たな学びのスタイルの提案
より高度な学びを求めて、社会人の方が、仕事を続けながら大学院で学ぶということが、増えてきています。大抵は、仕事が終わった(無理に切り上げた)後の夜、あるいは、週末に大学に通うというスタイルでしょう。仕事と学びの両立に、苦労されている方が多いと思います。東京であれば、オフィスの近くに、大学のサテライト・キャンパスがあって、通学に便利な場合もあるかもしれませんが、地方では、なかなか、恵まれた環境には、遭遇し辛いかもしれません。
片や、企業の側でも、働く人が、より高度な専門知識を習得することが、職場の生産性を改善するはずだと考え、大学院で学ぶことを応援したいというところが、少なくないようです。急速に技術革新が進展する中で、リカレント教育(社会人再教育)が注目されていることも、その現われでしょう。
こうした状況を踏まえて、経済学分野・法学分野では、週に1日、月曜日に授業を集中して開講するシステムを採りました。大学院での学習で、時間的な制約が生じるのは、授業への出席です。これを1日に集約し、職場の方でも、「この日だけは、大学に通うことを認めてあげる」という形にしてもらえれば、大学院で学ぶハードルも下がるのではないか、という、新たな提案です。加えて、長野のキャンパスや、軽井沢のサテライト・オフィスなどに、遠隔で授業を受講できるシステムを導入し、身近に、経済学や法学を学ぶ大学院が無くても、授業を履修できる設備を整備しています。この結果、初年度から、長野県庁の方、軽井沢町役場の方など、大勢の社会人の方が、経済学分野、法学分野に入学してきています。
一方で、学部から、純粋に大学院生として進学した場合、「授業が週1日だと、どうなるんだろう」という不安が、あるかもしれません。でも、そうした心配は杞憂です。残りの時間は、指導教員のもと、自身の研究テーマに即した学習を、フレキシブルに進めています。指導する側でも、授業がない日に、どのような学習をすべきか、気を配って指導を行っています。希望すれば、指導教員の研究を手伝ったりする時間も作りやすいので、「専門的な研究とは何か」を、オン・ザ・ジョブトレーニングのような形で、学ぶことができています。また、社会人の学生との議論を通じて、大学院での学びを、実践的な知識に結びつけることにも役立っています。日々の仕事の中で、相手に説明をして説得させる経験を積んできた社会人の方のプレゼンテーションのスキルは、大変、参考になっているようです。


データサイエンスを駆使する経済学の専門家養成
近年、Evidence Based Policy Making(証拠に基づく政策)という考え方が、重要視されるようになってきています。意思決定に際して、客観的な証拠による裏付けが求められることは、公共政策の場に限らず、企業経営にもあてはまります。こうした社会的ニーズを考慮して、経済学分野では、実証分析手法の修得に力を入れています。講義での計量経済学手法の学習に加え、指導教員の下で、統計ソフトを用いて、実践的な計量分析の手法を身に付けることができます。また、マクロ経済学の授業の中では、ソローモデルや、ラムゼーモデルを理解するために、Pythonを使って数値計算も試みたりしています。経済学の考え方が、現実の経済を説明できているのか、それを確かめるためには、社会データを用いた、実証的な検証が不可欠です。このため、思考の枠組みとして経済学を学ぶのと同時に、考え方の妥当性を検証する実証分析の手法を使いこなせるようになるための教育を実践しています。ビッグデータの時代に、データサイエンスを駆使して、経済学的アプローチから、様々な社会問題の解決に挑むことができる人材育成を目指します。

税理士資格取得を目指す社会人の受入れを積極的に展開
法学の大学院といえば、ロースクールが、すぐ思い浮かぶと思います。本研究科の法学分野の位置付けは、ロースクールとは、異なります。近年、官公庁、あるいは、民間企業の法務部門など、高度な法律の知識を求められる仕事が増えていて、それに対応する人材へのニーズが高まっています。法学分野では、法曹とは異なる立場で、法律の専門知識を駆使して働く人材の養成を、目的としています。具体的に取り組んでいる例として、税理士を目指す方のために、税理士試験の税法科目の免除が受けられるカリキュラムを設けています。働きながら税理士試験を目指している方々から、大きな関心を寄せて頂いています。
