

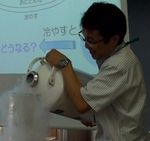
| 信州大学学術研究院教育学系 理科教育グループ 准教授 | |
| 専門分野: | 低温物理学 |
|---|---|
| 研究テーマ: |
|
物質を極低温に冷却すると,これまで熱振動によって平均化され覆い隠されていた物質の本質(個性)が姿を現してきます。騒がしい人ごみの中で一人一人の声は聞き取れませんが,静かになると一人の声が耳に届くようになるのと似ています。低温実験は物質本来の姿を知ることにつながっています。液体窒素(77 K)やGM冷凍機(3 K)を使って,低温をキーワードにした実験研究をしています。テーマの概要は以下の通りです。
さらに詳しく知りたい方は以下のメールアドレスまでご連絡ください。
kambaraアットマークshinshu-u.ac.jp
(アットマークを@に変換してください。)
金属線を引き伸ばして破断寸前にすると,電気伝導が古典論では説明できない量子化された値を示すようになります。このMCBJ法は簡易な方法ながら,原子レベルでの接合を形成することができます。かたまり(バルク)の試料の測定では電子の振る舞いは平均化されてしまいますが,接合部分を作ることで,局所的な情報としてミクロな電子の振る舞いを調べることができます。単純な金属の他に,強磁性体や超伝導体に応用して,興味深い輸送現象を調べています。
液体窒素を用いて超伝導状態となる高温超伝導体を用いて,超伝導という現象を小・中・高校生に広く実感してもらえるような演示実験教材の研究もしています。
電子が超伝導状態になると,電子の対(クーパー対)を形成します。通常はスピンの向きが反対の2電子が対を形成しますが,極低温下において,ごく稀な物質ではスピンの向きがそろった対を形成することが知られています(スピン3重項状態)。このような超伝導体はクーパー対が内部自由度を有しており,通常の超伝導体には見られない新しい超伝導現象の出現が理論的に予測されています。それを電気伝導測定(電流-電圧特性)により見出すことを目指し,研究を行ってきました。
走査トンネル顕微鏡(STM)は,原子や分子1個1個を直接観察することができる究極の顕微鏡です。STMを使って局所的な電流-電圧特性を調べる(トンネル分光)と,電子の局所状態密度が分かります。局所状態密度の分布は量子力学における波動関数(|Ψ(r)|^2)を直接観測していることに対応します。低温環境下で走査トンネル分光を行い,これまでに超伝導体の不純物周辺の状態密度の変化やグラファイトの磁場中状態密度の変化を調べる研究を行ってきました。