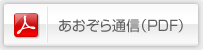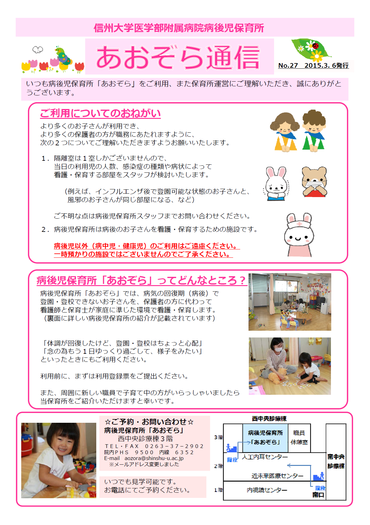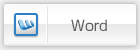理念・特色
女性スタッフのライフステージを通じた支援策として「女性スタッフ支援センター」を設立し、既存の子育て支援組織、勤労女性支援組織、ベビーシッター派遣組織等の情報を収集・整理し、全県下で効率よく機能させる「スマートグリッド機能」を持たせる。
-
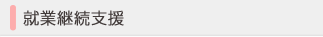
-
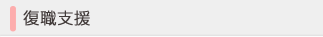
-
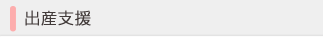
- 不妊治療に対する支援
- フレックスタイム制度の利用促進
就業継続支援
フレックスタイム制度を試験的導入
遠隔システム作成中。ワークシェアリングは平成16年から実施中。
テレワークシステム(在宅カルテ参照システム)
テレワークシステムは、自宅に専用ノートPCを置き、院内とほぼ同じ条件で、担当患者の情報をリアルタイムに確認することが可能な在宅カルテ参照システムです。セキュリティは万全で、患者情報が医師以外の家族などの目に触れることがないように、静脈認証を取り入れています。利用者IDとパスワード、さらに本人の静脈認証がないと、専用PCにログインできないのです。また離席した場合もスクリーンセーバが作動し、再度静脈認証しない限り、診療情報の参照は続けられない仕組みになっています。
託児所へのお迎えや夕食作りなどのために病院を離れた後でも、自宅で患者情報を入手することで、病態の把握と整理、必要なら電話での指示出し、翌日の診療の準備、などを行うことが可能となり、育児中の医師がモチベーションを維持し、仕事を続けていくことに繋がります。
テレワークシステムを利用して

産婦人科女性医師(5才児の母)
非常勤医として、大学勤務が可能となり、通院治療室における外来化学療法を担当しています。
勤務医(小児科医)の夫と幼稚園に通う5歳の娘との3人暮らしで生活しているため、幼稚園のお迎え時間には帰宅しなければなりません。
そこで、テレワークシステムを利用させていただくことになりました。
テレワークシステムは、自宅でカルテを閲覧できるので、家事が一段落したところでノートパソコンを開き、当日診察した患者さんのカルテや検査データを確認しています。
カルテ情報は病院にいる時と同様に閲覧可能なので、気になっていた点を確認し、次回の診療に向けた準備をします。
カルテへの記載はできませんが、メモを送信しておくことで記載漏れなどが防止できるので便利です。
また、CTなどの画像チェックなども時間に余裕がある時に落ち着いて行うことが可能です。
当日の対応を必要とする場合などは、カルテを確認し、病院に電話をして相談・対応をお願いすることもあります。
テレワークシステムの活用で、時間を有効に利用できているように思います。
復職支援
病(後)児保育所開設
本院内に病後児保育所を設けております。
病後児保育の詳細・希望を申請する場合は、下記の手順のとおり申請してください。
病後児保育所あおぞらの利用に関わる手続きの流れ
-
(1)事前登録
利用登録票をご記入いただき、病後児保育所までご提出ください。
※1年に1度ご提出いただければ結構です。
利用登録票ダウンロード
-

(2)受入基準に合うか確認
下記の条件をすべて満たす必要があります。
病後児保育所受け入れ基準
(1)病気の回復期であり、かつ他児に感染させる危険性が低いこと。
(2)当日朝の体温が38℃未満であること。
(3)経口水分摂取が可能であること。
(4)嘔吐や下痢が頻回でないこと。
(5)呼吸困難がないこと。
(6)易感染性を呈する状態(例;先天性免疫不全症、免疫抑制剤服用中)でないこと。
(7)熱傷、骨折など外科的疾患の場合は病状が固定していること。
(8)感染症罹患児童の受け入れの可否の決定に際しては当日の隔離室の利用状況を勘案する。
(感染症受け入れ基準を参照)
(9)かかりつけ医を受診していること。 -
(3)事前予約
信州大学医学部附属病院病後児保育所 0263-37-2902
※病後児保育所不在時にはPHS 9500へ転送されます。
※予約受付時間 7時30分から18時まで(18時から7時30分までは留守番電話) -
(4)持ち物準備
*病後児保育所書類
(1)利用申込書
(2)こどもカルテ
(書類等はあおぞらホームページよりダウンロードできます。)
*処方薬(内服薬・坐薬など)、着替え1組、パジャマ1組(おむつ・おしり拭き・おむつ交換用敷きタオル含む)、よだれかけ、粉ミルク(冷凍母乳可)、哺乳ビン、飲み物(経口補水液OS1等)、おやつ、アレルギー食など持ち込み可、コップ、歯ブラシ (特別食の方は昼食をご持参下さい。なおご自宅での調理では食中毒にご留意願います。)
*お子さんの好きなおもちゃ、DVDなど持ち込み可(お名前の記入をお願いします。)
利用申込書ダウンロード
こどもカルテダウンロード
(5)あおぞら通信
託児所設置
県内で開催されている周産期に関係する学会・研修会で託児所を設けております。
学会・研修会における託児希望を申請する場合、下記の手順のとおり申請してください。
なお、申請する際には学会会場と併せて託児所として使用できる会場の確保が必要となります。託児会場の広さ、託児可能人数については下記に記載しておりますのでご参照ください。
-
(1)保護者用の様式を学会・研修会参加予定者に配布、記入提出
保護者用
-
(2)保護者用の様式を集計した結果をまとめ、開催者用の様式に記入学会開催日の1ヶ月前までに当事務局(信大・産婦医局内)まで提出
※託児人数が確定しない場合には多めに想定してください。開催者用
- (3)当事務局より託児所に依頼(託児所AかBか託児会場の大きさと託児人数により、事務局で判断いたします)
- (4)その後、依頼先の託児所を連絡いたしますので、開催事務局と託児所で詳細を決定
開催事務局は当日の開催会場で対応できるよう必ず担当者を決めてください。
ご不明な点がありましたら、当事務局までご連絡ください。
≪託児所A≫
【託児会場の広さ】最低基準は以下の通り。
| 満2歳未満 | 一人につき1.665平方メートル |
|---|---|
| 満2歳以上 | 一人につき1.98平方メートル |
【託児可能人数】特に制限なし。人数によりシッター数を増員。
≪託児所B≫
【託児会場の広さ】人数にもよるが最小でも8畳(13.2平方メートル)程度が望ましい。
【額時可能人数】平日20名程度、土日5名程度まで可能
過去の託児所設置学会・研修会名
- ・長野県母子衛生学会
- ・信州産婦人科連合会
- ・小児科学会甲信地方会
- ・新生児呼吸療法モニタリングフォーラム
- ・産科診療研修会