医局員募集
脳神経内科、リウマチ・膠原病内科では、新入医局員を募集しています。
見学希望・医局員募集に関しては、統括医長(信州大学医学部 内科学第三教室)までお問い合わせください。

お問い合わせ
プログラム概要は信州大学医学部附属HP 卒後臨床研修センターの「医科専門研修」ページより、専門研修プログラム[内科]をご覧ください。
脳神経内科の魅力

脳神経内科は、脳・脊髄・末梢神経・神経筋接合部・筋肉に関連する広汎な領域をカバーする診療科です。対象とする疾患も頭痛、めまい、認知症、脳卒中、てんかんなどのcommon diseaseから世界で数例の稀少疾患まで多彩です。超高齢化が進む日本において、アルツハイマー病、脳卒中、パーキンソン病などの神経疾患の患者数は加速度的に増加しており、これらの疾患を抱える高齢者を総合的に診療できる脳神経内科医には、非常に大きな社会的なニーズがあります。
脳神経内科の最大の魅力は、問診と神経診察により病巣と病態を絞り込み、診断をつけることが可能な点です。これは今後どんなにAIが進歩してもとって代わることのできない領域です。数年前に病棟から異動になる看護師さんが、「脳神経内科の先生は名探偵です。先生方のカルテを読んで謎が解けていくところがとても好きでした」と言ってくれました。近年は、画像技術や遺伝子解析技術の進歩により、脳神経内科医の臨床診断を科学的に検証することも可能になっています。また、診断により疾患修飾療法が可能な神経疾患も年々に増えています。脳炎・髄膜炎などの神経感染症、多発性硬化症・重症筋無力症・ギラン・バレー症候群などの神経免疫疾患、脳血管障害に対して、多くの疾患修飾療法が開発されているのは皆さんご存じと思います。これに加え、治療が困難と考えられていた、アミロイドーシスや神経変性疾患においても近年有効な疾患修飾療法が開発されています。具体的には、遺伝性ATTRアミロイドーシス(家族性アミロイドポリニューロパチー、FAP)に対する肝移植、TTR四量体安定化薬、siRNAによる遺伝子治療や、脊髄性筋萎縮症に対する遺伝子治療(アンチセンスオリゴヌクレオチドの髄注)などがあります。脳神経内科医の優れた診断能力が治療に役立つ時代が今まさに到来しています。
脳神経内科のもう一つの魅力は、裾野が非常に広く専門医となった後も様々な進路を選択することができる点です。以下に代表的なキャリアプランを示します。
- 地域の総合病院や大学病院で幅広い神経内科疾患の急性期医療を実践する
- 大学で、最先端の神経内科医療を実践しつつ、基礎研究や臨床研究に挑戦する
- 地域の高齢者医療のリーダーとして、認知症やパーキンソン病などの神経変性疾患を有する患者さんの総合的な診療に従事する(勤務医としてあるいは開業医として)
- 神経難病の患者さんの在宅医療(訪問診療)を専門的に実践する(開業医としてあるいは勤務医として)
- 脳卒中の専門家として、tPAや血管内治療を含めた急性期の脳卒中治療を極める
- てんかんの専門施設で、高度なてんかん診療に従事する
- リハビリチームのリーダーとして神経疾患の患者さんの社会復帰を支援する
脳神経内科には他にも様々な選択肢があり、必ず自分に合った脳神経内医としての進路が見つかるはずです。また、このような多様な選択肢があるため、女性も働きやすくキャリアを継続しやすい分野です。21世紀は脳の時代です。また、高齢化率が30%を超えるこれからの時代において、脳神経内科は間違いなく必要とされる将来性のある診療科です。是非、私たちと一緒に信州で脳神経内科を目指しましょう!
リウマチ・膠原病内科の魅力

膠原病は免疫の異常を背景に、全身のさまざまな臓器に炎症を起こす疾患群です。症状は多彩ですが、その分学びの幅が格段に広がる分野です。
以下に当科の代表的な魅力を述べますが、一つでも当てはまれば、あなたはすでにリウマチ・膠原病内科向きです!
1. 全身を診る総合力を身につけたい
リウマチ・膠原病内科では、一つの臓器にとどまらず、関節痛や発熱をきっかけに、肺炎、腎障害、皮疹、神経症状、消化器症状など、複数臓器にわたる症状を診療する機会が日常的にあります。疾患を「臓器」ではなく「患者さん全体」として捉える習慣が自然と身につき、総合内科的な視点を持つことができるとともに、一人の内科医としての幅広い診療能力が鍛えられます。
2. 謎解きが好き

膠原病では発熱、関節痛、筋肉痛、皮疹、倦怠感といった非特異的な症状が複雑に絡み合って現れることも多く、感染症や悪性腫瘍、他の自己免疫疾患との鑑別も必要です。『今、目の前にいる患者さんに何が起きているのか』を解き明かすには、病歴や身体診察、血液・画像検査、病理など多くの情報を統合して検証する必要があり、一つひとつの情報(ヒント)を積み重ねて、診断や病態(答え)に迫っていく、という知的好奇心に満ちた過程を経験することができます。当科ではこの力を伸ばすため、定期的に臨床推論をテーマにした抄読会を行い、全員で研鑽を続けています。
3. 担当患者さんの治療に長く関わりたい
リウマチや膠原病の多くは慢性疾患であり、診断から治療導入、維持期のフォロー、再燃時の対応まで、患者さんとのお付き合いが年単位となることも少なくありません。患者さんの人生の転機(就職、出産など)を病気のコントロールを通して支えることもあります。長期的な関係性の中で信頼関係が深まり、患者さんから感謝してもらえる、ということは、医師としての大きな喜びです。
4. ほどよく手技も経験したい

一般内科として身につけることが望まれる、骨髄穿刺や腰椎穿刺といった手技は、行う機会も多くすべて習得可能です。加えて当科独自の手技として、関節穿刺や関節エコー検査、筋生検があります。関節穿刺は腫れている関節に直接針を刺し、関節液の採取・排液とともに薬剤の投与を行うもので、関節炎の診断や急性増悪時の治療として非常に役立ちます。関節エコー検査は関節炎の程度を視覚的に捉えることが可能で、診断の一助となります。また、炎症性筋疾患が疑われる患者さんに対する筋生検では、組織の採取や検体の処理、染色といった過程を経験でき、自ら得た病理学的所見をもとに診断をすることが可能です。
5. 最先端の医療に触れたい

生物学的製剤やJAK阻害薬などの登場により、かつては治療が困難だった関節リウマチや膠原病も寛解が目指せる時代になりました。それに伴い、薬剤の選択肢や投与方法も多様化しています。それはこれから先も続いていきます。当科では、患者さん一人ひとりの病状やライフスタイルに応じた個別化医療の提供を心がけています。治療戦略が日々進化していく中で、医療の最前線に身を置きながら、その変化と進歩を実感できることは、この分野の大きな魅力の一つです。
おもしろそうだけど大変そうだな…と不安になる必要はありません。リウマチ・膠原病内科は若い医師が多く、面倒見のよい指導医ばかりです。また、医局の雰囲気もとてもよく、皆で成長しようという気概にあふれています。将来的なキャリアプランとしても選択肢が豊富で、臨床を究めて地域の柱となって働くもよし、県外の仲間と臨床研究を行うもよし、海外留学や基礎研究の世界を覗いてみるもよしです。また、膠原病は女性の罹患率が高いという背景もあり、当科では女性医師の育成にも力を入れています。出産後も育児と両立しながら、地域の最前線で活躍している先輩もいます。
今こそ、魅力にあふれたリウマチ・膠原病内科の世界に飛び込んでみませんか? 一人前になるまで、我々全員で皆さんをしっかりサポートすることを約束します!
教室の様子・概略
私たちは、個々の教室員の自主性を尊重し、個人の目標をサポートし助け合える、教室を目指しております。最先端の研究を行うことはもちろんのこと、医学生・大学院生の教育にも力を入れています。クラブ活動も積極的に行っており、年1回開かれる将棋大会では、名人位をかけて白熱した戦いが繰り広げられます。普段はハンマーより重いものを持つ機会に乏しい私たちですが、医局対抗野球大会にて4回の優勝経験があります。
信州大学・長野県で専門医として活躍することの意義
長野県は全国有数の長寿県であり、認知症や血管障害などの患者さんが急増していることから、多くの病院で神経内科専門医が必要とされています。リウマチ・膠原病内科については、長野県内に専門医が非常に少なく、若い専門医が県内の専門医療の中心になると強く期待されています。

筋生検
関節診察
神経診察
髄液検査
取得できる専門医、資格など
- 日本内科学会総合内科専門医
- 日本神経学会神経内科専門医
- 日本リウマチ学会リウマチ専門医
- 日本認知症学会認知症専門医
- 日本脳卒中学会脳卒中専門医
- 臨床遺伝専門医制度委員会臨床遺伝専門医
- 日本臨床神経生理学会専門医

これまでの国内留学先
- 国立循環器病院センター
- 虎ノ門病院分院(腎センター)
- 国立精神・神経医療研究センター神経研究所
- 国際医療センター
- 東京都精神医学総合研究所
- 東京都老人医学研究所
- 東京都臨床医学総合研究所
- 道後温泉病院(リウマチ科)
- 筑波大学(膠原病リウマチアレルギー内科)
- 自然科学研究機構生理学研究所
- 広南病院(脳血管内科)など
これまでの国外留学先
- カリフォルニア大学サンディエゴ校(米)
- エモリー大学(米)
- マックスプランク研究所(独)
- ニューヨーク州立大学(米)
- コペンハーゲン大学(デンマーク)
- キール大学
- オックスフォード大学(英)
- インディアナ大学(米)
- スクリプス研究所(米)
- スタンフォード大学(米)
- ノースウェスタン大学(米)
- サルペトリエール病院(仏)
- ランカスター大学(英)
- ビセートル病院(仏)
- メイヨークリニック(米)
- フロリダ大学(米)など

スタンフォード大学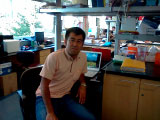
スタンフォード大学
メイヨークリニック
フロリダ大学
中途入局をお考えの方へ
長野県は全国有数の長寿県であり、認知症や血管障害などの患者さんが急増していることから、多くの病院で神経内科専門医が必要とされています。リウマチ・膠原病内科については、長野県内に専門医が非常に少なく、若い専門医が県内の専門医療の中心になると強く期待されています。
連絡先:信州大学医学部第三内科(脳神経内科,リウマチ・膠原病内科) 統括医局長
E-mail: sannai@shinshu-u.ac.jpこれまでに中途入局した3名の医師のインタビューを載せていますので、参考にご覧ください。
INTERVIEW
-中途入局して来られたA先生、B先生、C先生はそれぞれ、卒後9年目、15年目、19年目での入局でしたね。まずは入局の経緯について教えて頂けますか。
A医師:信州大学卒業後、初期研修を長野県の病院で、リウマチ・膠原病の後期研修を東京都の病院で受け、その後に勤める病院を探していました。妻が長野県出身であることや、長野県はリウマチ・膠原病内科のニーズが高く、専門医として患者さんの役に立てるのではないかと考え、母校である信州大学でお世話になることにしました。
B医師:夫が松本市内に転勤することがきっかけでした。これまでは他県の大学医局に在籍していたり、直近では東京都内の病院で勤務していたので、長野県内の医療機関との接点はありませんでした。人脈がない中でしたので、同じ分野の先生方と知り合うためには大学病院が適していると思い、入局のお願いをしました。
C医師:私は主に東京都内で神経内科医としてのキャリアを重ねてきました。専門分野が筋炎やNeuro-Rheumatologyなのですが、神経内科とリウマチ・膠原病内科が一体となっている当科は自分の専門性を伸ばし、この分野の研究を発展させることに適しているのではないかと関心をもっていました。また職業人として折り返しの時期にあたり今後のことを考えていたのですが、私は信州がとても好きで、同じようにこの土地に愛着をもっている方々、何かしらご縁があってここに暮らす方々の健康のために仕事ができれば、そのこと自体が自分のモチベーションになると思い、信州大学でお世話になれないかとご相談しました。
-A先生は社会人大学院生として在籍されていますが、普段はどのように過ごされていますか。
A医師:大学では病棟業務が中心です。病棟業務は、朝8時45分からのミーティングに始まり、通常17時過ぎには一日の診療業務を終えています。もちろん担当患者の容態などによって繁忙度に波はありますが、当番医に引き継ぐことができるので夜中遅くまで残業をしないといけないということは殆どありません。後輩や学生への指導を行う時間も確保できています。また週1~2日ほどの外勤があります。そうした診療・教育業務の合間や週末などを使って、研究活動を行っています。診療をしながら研究を行うのは時間の作り方という面で大変ではあるのですが、臨床医としての研鑽も継続できると前向きに捉えています。
-B先生はこれまで長野県や本学と縁がなかった中で入局された訳ですが、心配なことはありませんでしたか。
B医師:初めての土地、初めての職場で、たしかに不安はありましたが、入職のご相談時点から教授や医局長、秘書の方から勤務形態や外勤先のこと、生活のことまでサポートや助言をしてもらい、とても心強かったです。
-病棟業務が中心ですが、仕事のしやすさなどはいかがですか。
B医師:入職当初はやはりシステムや慣習などの面で不慣れなことはもちろんありましたが、分からないことを尋ねにくい雰囲気は全くありません。病棟医長や同僚の医師からとても親切に教えてもらっていました。A先生が話されていた通り、仕事で遅くならないのは家庭との両立という意味でも助かっています。各患者の主治医は固定されていますが、病棟医を複数のグループに分け、グループ内の医師が不在のときにはお互いカバーして診療を行っていますので、安心感もありますし、負担の軽減にもなっています。その日の病棟業務の忙しさにもよりますが、手のあいたときには、日中に論文に目を通して勉強したり、学会・論文発表の準備や学生指導の時間をとったりすることもできています。私はフルタイム勤務をしていますが、パートタイムなどの選択肢もあると聞いています。
-外来診療についてはいかがですか。
C医師:看護師や事務スタッフのサポートがしっかりしていて、とても助かっています。外来診療の中で何か急を要することがあっても、同じ曜日に外来に出ている医師がお互い協力して対応しています。大学病院特有の希少疾病から、比較的コモンな疾患まで幅広く対象としていると思います。
-当直はどのような体制ですか。
A医師:内科系の合同当直体制が取られています。以前は各科が独自に当直医を立てていたのですが、この体制の導入により当直回数が減り、負担の軽減になっています。当直回数は現在月1回程度です。当直明けの日は昼頃には帰宅しています。もちろん当直明けに外勤が入らないように配慮されています。他科が当直の日は各科がオンコール待機医を立てるのですが、オンコール当番は月1~2回です。土日・祝日の病棟回診も当番制ですが、日直医やオンコール当番医がなるべく兼ねるようにして、当番の回数が減るように考えられています。
-外勤についての印象はいかがですか。
B医師:繁忙度は日によって異なりますが、終日勤務でもだいたい16~17時には大学に戻って来られると思います。土地柄、外勤先への移動には自動車を使うことが多いのですが、長距離運転に不慣れであればなるべく近場にしてもらうなど配慮されます。また回数も個々の事情によって相談できます。
C医師:私は自動車で1時間半ほどかかる遠めのところに行っているのですが、道中に音楽を聴いたり、語学の勉強をしたりして移動時間を有効活用しています。信州の美しい山々や花、緑を眺めながらの運転は良い気分転換にもなっています。
-医局の雰囲気はいかがですか。
A医師:皆、和気あいあいとしています。神経内科医とリウマチ・膠原病内科医が日々の病棟カンファレンスで一緒に議論しているのが特徴で、双方の知恵を出し合いながら話を進めることもあります。私はリウマチ・膠原病内科医ですが、こちらにきて神経内科の同僚医師に神経学について多くのことを教えてもらい、神経学的診察の能力が向上したと感じています。また、ときどき行われる懇親会や野球大会も盛り上がりますよ。
-医局は怖いというイメージはなかったですか。
B医師:怖くはないですよ(笑)。皆さん親切で、入職初日から先生方が温かく声をかけてくださり、とてもありがたかったです。病棟カンファレンスではもちろん患者さんのことをお一人お一人、真剣に議論しているので、どこか凛とした空気は流れていますが、怖いという感じはありません。議論は建設的かつ教育的です。カンファのあとに年長の先生が若手医師や学生に補足説明をしたり、関連資料を渡してあげたりする姿もよく見かけます。
-神経内科とリウマチ・膠原病内科の合同医局ですが、印象はいかがですか
C医師:思っていた以上に両科の医師が一体となって医局や病棟を運営していることが印象的でした。たとえば筋炎や血管炎性ニューロパチーのような双方の分野の境界領域の疾患では、神経内科医が長けている電気生理学や筋病理学、膠原病内科医が長けている免疫抑制剤や分子生物薬の扱い方といった、双方の強みをうまく活かしながら診療が行われています。このようにお互いの専門性が近い距離感で活かされているのが、いわゆるナンバー内科の強みだと感じます。
-C先生は卒後20年近く経っての入局でした。当科は外からどのように見えていましたか。
C医師:当科に関心があったので、学会ではなるべく発表を見に行くようにしていましたが、それぞれが個々の診療経験を学術研究に発展させているスタイルが多いような印象を受け、そこに好感あるいは敬意をもっていました。若手の先生の発表もすごくしっかりしていて、指導が行き届いているのだろうなと感じていました。
-信州での生活はいかがですか。
A医師:自転車で通勤することが多いのですが、特に4月、5月は桜と新緑がとてもきれいで癒されます。また東京で住んでいたときよりも家賃が安くなり、非常にありがたいです。ただ、学生時代から感じていたことなのですが、冬が寒いことにはまだ慣れません(笑)。私は小さい子供がいるのですが、松本市内には大きな公園が多く、子育てもしやすい環境ではないかと思います。
-B先生、松本での暮らしはいかがですか。
B医師:パン屋さんや喫茶店、雑貨・食器・家具屋さんなどこだわりのお店が多く,楽しい街ですね。私は時間と労力の節約も兼ねて普段の買い物にはネットショッピングを組み合わせていますが、大型のスーパーも数店舗あって普段の生活に困ることはありません。街の規模は大きすぎず、小さすぎず、生活するのにちょうどよいくらいだと思います。
-「ちょうどよい」というワードはよく聞きますね。休日はどのように過ごされていますか。
B医師:休日はまず家の用事を済ますことから始まりますが、パン屋さんを巡ったり,徒歩や車で散策をしたり、いろいろと楽しんでいます。松本市内だけでなく、安曇野や八ヶ岳山麓など少し足を延ばしたところもとても綺麗ですし、素敵なお店もたくさんありますね。もちろんお蕎麦も美味しいです。民芸・工芸などの文化や音楽が根づいているところも魅力的ですし、雄大な北アルプスの風景は飽きることがなく、少し郊外にいったところで山野草をみられるのも楽しいですね。
-C先生はこちらでの生活、いかがですか。
C医師:通勤に関しては、信州に来るまで都市部で暮らしていたため混雑した電車・バスでの移動が多かったのですが、こちらでは自家用車を使うようになり、通勤は格段に楽になりました。学会や研究会への参加で東京や名古屋・関西方面に行くことがたびたびあるのですが、松本は長距離鉄道のアクセスがよいですし、さほど不便には感じていません。また福岡、神戸、札幌へは空路もあり便利です。メディカル・サイエンスの分野では、都心でなければ仕事がうまくいかないということはないと思います。むしろ自然と文化が豊かな、好きな土地で暮らしていると、気分もリフレッシュしやすく、仕事がはかどる気がします。
-休日はどのように過ごされていますか。
C医師:休日のうち半日くらいは原稿執筆や論文に目を通すなど自宅でできる仕事をしています。東京にいたときより住居費は下がり、広めの家に住むことができたので、家で仕事をしやすくなりました。その分、残業や休日出勤が減って、家族と過ごす時間を確保しやすくなっています。ジョギングが趣味なのですが、松本城や旧開智学校周辺、あがたの森公園や、薄川沿いなど平坦で走りやすいコースがあります。北アルプスも随所に見られて気持ちよく走れます。
-これまでにも長野県出身者で地元に戻ってきたという先生や、卒後しばらく他科で活躍された後に神経内科やリウマチ・膠原病内科に転科してこられた先生もおられました。経歴や出身大学はさまざまです。多様な背景をもつ医師が集まり、お互いに刺激を与え合う環境は私たちにとってもプラスになると考えています。中途入局をお考えの先生にはぜひ一度ご連絡頂き、勤務の仕方をご相談頂いたり、実際の雰囲気を見に来て頂ければと思います。










