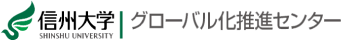令和6(2024)年度支援
研修先:マレーシア 実施部局:全学教育センター 研修期間:2025年2月19日~2月25日 5(日間) 参加者数:24(人)
Scholarships for Studying Abroad
海外留学のための奨学金
- TOP
- 信州大学生のみなさま
- 海外留学のための奨学金
- 学生の短期海外活動支援(3ヶ月以内)
国際的な視点をもった環境マインド人材育成のためのマレーシア演習プログラム
本プログラムは、全学横断特別教育プログラム「環境マインド実践人材養成コース」に参加している2年生を対象に、国際的な環境に関する課題に向き合う力を養成することを目的として実施しました。学生たちは「エネルギー政策」「パーム油産業」「エコツーリズム」「野生動物保護」「国立公園運営」の5つのテーマに分かれて約半年間の事前学習を行い、その後2月19日から25日にかけてマレーシアで実地研修を行いました。
訪問先であるマレーシア・サラワク州の州都であるクチンは、世界でも有数の生物多様性を誇る熱帯雨林が広がる地域です。この地域は、戦後の近代化に伴い、熱帯材やパーム油、化石燃料の輸出などで急激な経済成長を遂げてきた歴史があります。しかし、近年は「カーボンニュートラル」や「生物多様性保全」などに関する環境政策が重要視され始めており、社会全体が大きく変化しています。今回の研修では、 持続可能性に配慮したアブラヤシの搾油工場・農園を運営するSALCRA、化石燃料の代替として期待される藻類の培養施設 CHITOSE Carbon Capture Center、バコ国立公園、セメンゴ野生動物センターなどを訪問し、事前学習で挙げられた疑問点についてインタビュー調査や現場視察を行うことにより、さらに学びを深めました。
特にアブラヤシの搾油工場および農園の視察では、現地で実際に行われている工夫や取り組みを知るだけではなく、生産現場の方々の思いや生活など、事前には把握できなかった新たな課題にも気づくことができました。参加学生は、私たちの生活に深い関わりがあるパーム油が生産現場に与える環境負荷や社会問題について、現地の声を交えながら多角的に考察する機会となりました。また、藻類培養施設の研修では、藻類の培養や事業開発の将来性を学ぶとともに、開発段階で必須となる地道な培養作業を体験しました。これらの経験を通し、効率とコスト、環境保全と経済性のバランス、さらには地域社会との関係性といった多様な視点から環境課題を考える重要性を認識しました。
このプログラムは、「①訪問先が抱える環境に関する課題を主体的に調査し、日本とのつながりや違いを具体例を含めて述べることができる。」「②環境問題に対する国際的な潮流を理解し、自身の興味や専門分野と結びつけて説明することができる。」という2点を達成目標に据えて実施してきました。研修後の成果報告会では、訪問先が抱えている環境課題を自分ごととして捉えて積極的に議論する様子が見られ、これら目標を自ずと実践できている姿がありました。今回の研修で得られた一連の学びが、参加学生の今後の研究活動やキャリア形成に活かされることを期待しています。
【学生の声①】
バコ国立公園では、野生動物が非常に近くにまで来るため、観光や学習などの観点では柵越しでは得られない経験をすることができると感じました。しかし、散見されるゴミや近すぎる野生動物との距離は国立公園における環境や野生動物への人間による影響は無視できないと感じました。
この演習では、マレーシアと日本の共通点や人の温かみなどを感じると同時に、食事やトイレなどの生活スタイルや自然環境などの違いも感じました。言葉の壁はありましたが、ジェスチャーを交えた交流などを通して環境と雇用・経済との結びつきや相互の影響など様々なことを学ぶことができました。海外での活動を行ったからこそ日本の環境への働きかけや私達が普段からできることを見つめなおすことができ、環境への配慮と経済成長を両立することの難しさを実感しました。
【学生の声②】
アブラヤシ農園と工場を見学し、現場の実態とネット上の情報に大きな差を感じました。人力作業の負担や人材不足の課題を知り、表面的な知識だけでは解決にならないと実感しました。現場の障害を考慮し、具体的な解決策を考える重要性を改めて感じました。
マレーシア研修を通じ、環境問題の解決には政策立案者と現場の労働者の意見を調和させることが重要だと学びました。知識だけでなく、現地の声を聞くことで、人材確保や機械化の難しさなど、実際の課題を理解できました。解決策を実行可能にするには多角的な視点と現場との対話が不可欠であり、今後は課題の背景を深く考え、働く人々の意見も踏まえたアプローチを意識していきたいと思います。