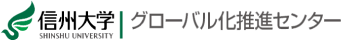令和6(2024)年度支援
研修先:シンガポール 実施部局:医学部保健学科 研修期間:2024年8月11日~8月16日 6(日間) 参加者数:10(人)
Scholarships for Studying Abroad
海外留学のための奨学金
- TOP
- 信州大学生のみなさま
- 海外留学のための奨学金
- 学生の短期海外活動支援(3ヶ月以内)
夏期海外研修保健医療スタディツアープログラム (シンガポール)
学部間交流協定を基盤として、保健学科学生が、シンガポールの保健・医療現場、教育施設を見学・体験することにより、将来国際保健・医療を担うことのイメージを広げることを目的としたプログラムです(学科共通専門科目「海外研修ゼミナール」の受講者を対象として実施)。ネイティブ教員による英会話レッスンを含む、研修までの事前学習を経て、研修を実施、帰国後は授業内で研修の振り返りや事後学習として報告会や成果報告書の作成を行いました。また、12月にSITからの学生受入れを実施した際に、グループワーク等や学生対応等の交流に主体的に関わりました。
SGHは、シンガポール最大の医療機関グループであるSingHealthにおいて中心的な病院で、東南アジア地域を医療圏としており、拠点集約型の高度医療が展開されています。全員での見学のほか、4専攻で分かれ、SGH内の各部門やSingHealthを構成する他の施設を見学する機会が設けられました。アジア先進国の保健医療の現状を理解し、シンガポールの保健医療施策や課題について学びを深めることができました。
SITでは、大学やシンガポールのヘルスケアシステムに関する講義の後にキャンパス見学ツアーとして、教育設備を見学しました。人体解剖模型とともにバーチャル解剖表示装置が導入されており、CTなどの画像診断を学ぶイメージングの端末が多数備わる教室が近接し、解剖と画像診断を照合することが容易であるため、効果的な学修が可能と考えられました。現地の学生とは、ウェルカムランチや、イベントを通じた交流ができ、前年度12月に本校を訪れた学生さんとの再会を果たすこともできました。最終日には、1週間のまとめを英語でプレゼンテーションを行いました。急遽であったものの、日本とシンガポールの比較を研修で体験したこと等の学びの面だけでなく、現地の食べ物や文化、日常での発見等を盛り込んだ内容で、現地教員からも好評でした。
事前学習で実施した英会話レッスンは、渡航での自信につながった様子が伺え、前述のプレゼンテーション対応においても役立ったという意見もあり、研修後に実施した語学力測定にて、全員研修前より向上が確認できました。
【学生の声①】
今回の研修では、同じ作業療法学を専攻しているシンガポールの学生と交流したり、日本で学んでいる作業療法学の知識と、シンガポールで学んでいる知識について共有し学びを深めたいと考えていました。また、シンガポールの医療についても興味があり、自身の専門である作業療法についてだけではなく、他にも広い知識を得られることを楽しみにしていました。
実際の研修では、シンガポールの医療を主に担うSingapore General Hospital、Singapore Institute of Technology、Outram Community Hospital、Rainbow Centreなどの施設に行かせていただきました。それぞれの施設について、その施設でどの様な医療が提供されているか、どの様な設備があるか、何を目標にこれから行っていくのかなど、多くのことを説明していただきました。このシンガポールでの研修を通して、医療にする知識がより深まったと感じるとともに、現地の方との交流を通して、自分の英語力を上げることにもつながったと感じています。この研修で学んだことを普段の実習や、将来の臨床場面でも活かしていきたいと感じています。
【学生の声②】
昨年、シンガポール工科大学(SIT)の学生が本学に来た際、言いたいことがうまく言えず後悔したので、今回の研修では、伝えることをあきらめずにコミュニケーションをとろうという気持ちで臨みました。現地研修で見学したSingapore General Hospital (SGH)の理学療法士 (PT) はベッドやトレーニング用具が設置されている個別で診察する部屋を担当していました。その中で、患者の近況伺いや患者に見合ったストレッチを行った後、個室の外にあるジムで大きな器具を使ってリハビリを行うという流れでした。患者はPTの時間が終わり次第、ジムを自由に使うことができ、自主的にリハビリに取り組める環境であることを知りました。SGHに勤務するPTは、一日に最大17人の患者を担当し、一人あたり最大40分の問診とリハビリの時間が与えられていました。また、シンガポールのPTは英語だけでなく中国語を話すことが前提となっていました。これは、多言語の対象者を支援するシンガポールならではの特徴だと感じました。この経験を活かして将来の理学療法、リハビリについて多様な切り口から考えられるようになりたいです。また、コミュニケーションで悔しい思いをしたため、さらなる英語力向上を目指したいです。