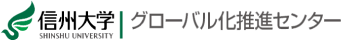令和5(2023年度)支援
研修先:ドイツ 実施部局:全学教育センター 研修期間:2024年2月17日~3月9日 21(日間) 参加者数:8(人)
Scholarships for Studying Abroad
海外留学のための奨学金
- TOP
- 信州大学生のみなさま
- 海外留学のための奨学金
- 学生の短期海外活動支援(3ヶ月以内)
「ドイツ環境ゼミ」:環境マインドをもったグローバル人材育成のためのドイツ視察研修プログラム
2/17: 羽田⇒ミュンヘン
2/18: ミュンヘン市内視察~レーゲンスブルクへ移動
2/19~3/1: 語学研修(Sprachschule HORIZONTE),環境視察
3/1~3/5: 個人視察および移動
3/6~3/8: ハノーファー市内にて団体視察
3/9: フランクフルトへ移動,フランクフルト市内視察
3/10~3/11: フランクフルト⇒羽田(解散)
レーゲンスブルクにあるホリツォンテ語学学校にて2週間のスタンダード・コースに参加しました。各自の語学能力に従ったクラスに分かれ、実践的なドイツ語運用能力の向上につとめました。期間中は、ホームステイ先の家庭や学校の寮に滞在しました。
語学研修期間中は、部屋にこもらずにとにかく積極的に街に出て、ドイツでの生活や習慣などに慣れることに各自で取り組みました。
平日の授業後(午後)の空き時間や週末は、各自のテーマに従ってレーゲンスブルク市内・近郊や他の都市に足を延ばし、部分的には教員が引率して環境関連施設や博物館などを視察・見学しました。
例:東バイエルン自然誌博物館、レーゲンスブルク市um:welt(エネルギー教育センター)、バイエルンの森国立公園センター、Bayerisch-Eisenstein駅(チェコとの国境駅)、パッサウ市街地など
2) 個人研修
各自のテーマに従って出発前に(指導を受けつつ)作成した計画を修正しつつ、各自あるいはグループでドイツ国内を回って視察を行いました。各自のテーマに従ってグループ活動や個人視察を組み合わせながら、広範囲にわたって有意義な視察を行うことができたようです。
3) 団体研修(ハノーファー市内)
本学の卒業生でもありドイツ在住で主に環境をテーマとしたジャーナリストとして活動している田口理穂氏と、ライプニッツ大学ハノーファーのフランツ・レンツ教授のサポートによって、ハノーファー市内及び近郊の各所を視察しました。訪問したのは、次の各所:
3/6:ハノーファー市立学校生物センター、ライプニッツ大学ハノーファー訪問(レンツ教授の講義を含む)、学生や一般市民との交流会
3/7:Tare Tag社(商品の包装容器のごみ削減を目指す企業)、ハノーファー市内の文化・歴史視察(ドイツ社会の平和やエコに関するテーマをからめて)
3/8:IGS Hannover-Mühlenberg ミューレンベルク統合学校、ハノーファー市気候保護局
【学生の声①】
ドイツ環境ゼミでは、自分でテーマを設定した環境問題とドイツ語について学ぶことができました。語学学校では、教科書に依存せず、実際に生活で使うフレーズや単語を学び、会話の機会が非常に多かったことが印象に残っています。日本でのドイツ語授業で学んだ文法の重要性も、語学学校での実践を通じて再確認できました。ホームステイ先との会話も徐々にドイツ語でスムーズに行えるようになり、その成果を実感できました。また、ドイツ語を学ぶさまざまな背景を持ったクラスメートとの交流を通じて、価値観や考え方の違いを理解することができました。
環境施設の個人視察では、自分のテーマに沿って視察先を決定しました。他言語の国で自分だけで行動する経験は初めてだったので、最初は不安でしたが、小さな成功体験を重ねることで自信をつけることができました。団体視察では、旅行では訪れることのできない場所や、普段は聞けない話を聞くことができ、非常に貴重な経験になりました。ドイツでの出会いに加え、一緒にドイツに行った仲間との交流や、日本とは異なる文化や街並み、考え方を知ることで、自分自身の成長を実感できました。
【学生の声②】
初めて海外に渡航した機会であったので、日本語以外の言語でコミュニケーションを取りながら生活をすることが新鮮でした。ドイツ語を勉強することは大学の講義や自主的に行うことができるが、現地に行くことでドイツ語の勉強だけでなく日本との風土や文化の違いを肌で感じることができました。特に、日本との相槌の打ち方の違いや様々なことに対する考え方の違いなどを現地の方とコミュニケーションを取ることで学ぶことができました。また、このゼミに参加したことで、普通の海外旅行では巡れないようなドイツの農山村を巡ることができました。森林の国立公園やドイツの農山村に足を運び、ドイツ人と森林の密接さを感じることができました。これは、自分でテーマを設定し外語でコミュニケーションを取りながら、自分のテーマを調査をするというこのゼミの課題でなければできない貴重な経験であったと考えています。